お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
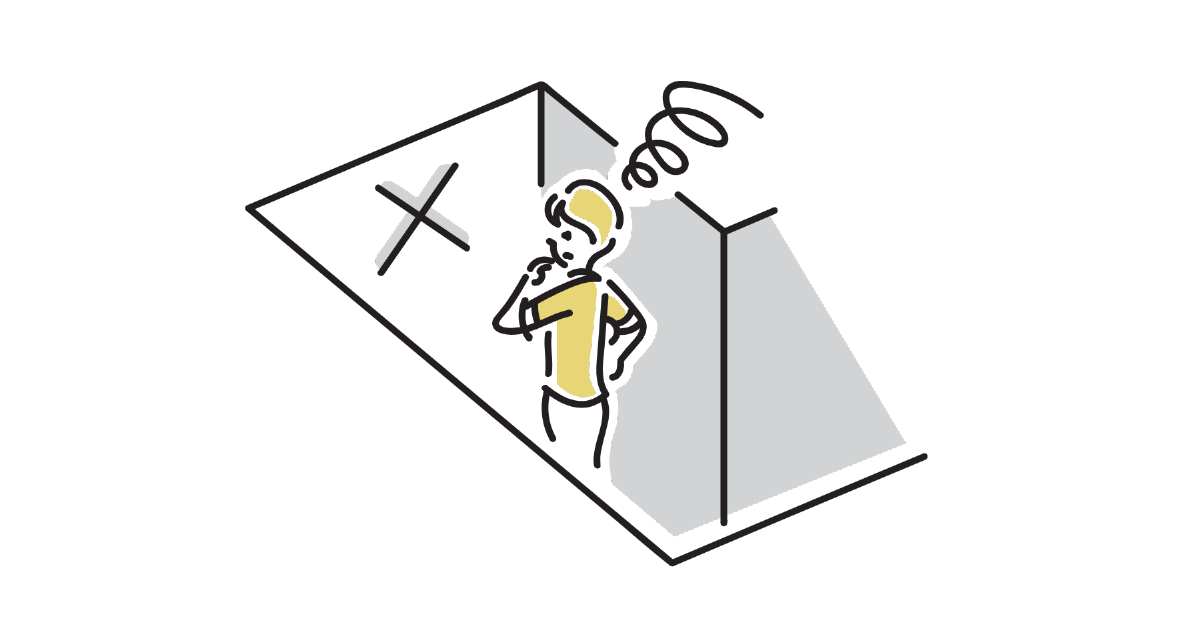
有期雇用の労働者であっても、期間満了に伴って雇止めを確実にできるわけではありません。
更新が繰り返され事実上無期雇用と変わらないケースや、労働者が雇用継続への期待を抱いて当然のケースでは、雇止めには正当な理由が必要です。
能力不足、勤務態度不良、会社の経営不振などが理由になり得ます。
ただし、解雇と同様に厳しい規制があり、問題の程度が低ければ雇止めはできません。
違法と判断されれば、職場復帰や未払い賃金の支払いを強いられ、企業にとって大きなダメージになります。
会社としては、正当な理由があると確認したうえで、手続きを踏んで進めなければなりません。
今回は、雇止めできる正当な理由になることや、理由証明書などについて解説しています。
有期雇用の従業員の雇止めを考えている会社経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
雇止めと解雇の違いなどについては、以下の記事で解説しています。
参考記事:雇止めとは?解雇との違いや有効要件・手続きを弁護士が解説
雇止めが問題になる場面

弁護士
岡本 裕明
まずは、雇止めが問題になる場面を簡単に見ていきます。より詳しく知りたい方は、以下の参考記事をお読みください。
参考記事:雇止め法理とは?適用されるケースや対策を会社側弁護士が解説
事実上無期雇用と変わらない
判例を明文化した労働契約法19条1号・2号において、雇止めが問題となる場面が定められています。
労働契約法19条1号に規定されているのが、過去に繰り返し更新され、事実上無期雇用と変わらなくなっているケースです。
更新の回数・期間の長さだけでなく、契約更新手続きが厳格になされているかなどを考慮して、労働契約法19条1号に該当するかが判断されます。
更新手続きをしていない、形骸化していたといった事情があれば、事実上無期雇用と同じだとみなされます。
雇用継続への期待がある
更新手続きは確実に行っていても、従業員の側が「雇い続けてもらえる」と考えているケースがあります。
そこで労働契約法19条2号に規定されているのが、労働者が更新を期待するのがもっともであると認められるケースです。
労働契約法19条2号に該当するかは、以下の要素を総合的に見て判断されます。
- 業務内容(常にある業務か)
- 更新回数・通算期間
- 更新を期待させる会社の言動の有無・内容
更新回数は考慮されますが、1回も更新していない段階で労働契約法19条2号に該当すると認められるケースも存在します。
雇止めできる正当な理由

弁護士
岡本 裕明
雇止めをする際には、能力不足、勤務態度不良、病気・ケガ、会社の経営不振など、様々な理由があるでしょう。正当な理由と認められるかはケースバイケースであり、一概には言えません。
雇止めは解雇の場面と似ており、おおむね同様の物差しで判断できます。もっとも、あらかじめ契約期間が決まっている以上、解雇と比べると会社側に有利な判断がなされる場合もあります。
では、雇止めができる理由について見ていきましょう。解雇の場面も参考になるため、以下の記事もあわせてお読みください。
参考記事:解雇できる理由は?ケースごとのポイントを会社側弁護士が解説
能力不足
作業が遅い、ノルマを達成できない、ミスが多いなど、能力不足を理由として雇止めを検討するケースは多いでしょう。
能力不足により与えられた仕事をこなせない場合には、程度次第で雇止めが考えられます。
ただし、単に能力がないだけでなく、指導による改善を図っても効果がなかった、他にできる業務もなかったなどといった事情も必要になります。
チャンスを与えずに雇止めしないようにしてください。
勤務態度不良
無断遅刻・欠勤を繰り返す、上司の指示を無視するなど、勤務態度に問題があるために雇止めをする場合もあります。
程度によるものの、勤務態度不良でも雇止めは可能です。
ただし、能力不足の場合と同様に、いきなり雇止めをするのではなく、繰り返し指導を行うようにしてください。
病気・ケガ
メンタルヘルスなどの病気や、プライベートでのケガにより働けなくなったケースもあるでしょう。
休んでも十分に回復せず、長期間にわたって勤務が難しい場合には雇止めが考えられます。
ただし、業務が原因となった場合には注意が必要です。
解雇に関する労働基準法19条1項の直接の適用はないものの、安易に雇止めしてはなりません。
犯罪行為
従業員が犯罪行為に及んだ場合には、雇止めの理由になります。
とりわけ、横領など社内での不正行為があった場合には雇止めが可能です(そもそも重大であれば懲戒解雇できます)。
ただし、社外で業務とは関係ない軽微な犯罪行為をしただけであれば、十分な理由にはならないと考えられます。
会社の経営不振
会社の業績不振も雇止めの理由になります。
そもそも、雇用調整しやすい点が有期雇用をする会社のメリットであるため、正社員の解雇よりも先に有期雇用労働者の雇止めを検討するでしょう。
有効性を判断する際には整理解雇における4要件が参考になりますが、無期雇用の従業員と比べて保護の必要性が薄いと考えている裁判例も多数あります(例:日立メディコ事件判決(最高裁昭和61年12月4日))。
したがって、人員削減の必要性があり、雇止めを回避するのが困難であるようなケースでは、正社員の解雇より先に雇止めを実行してもやむを得ないと判断される可能性があります。
整理解雇の要件について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:整理解雇とは?4要件や実施の流れを会社側弁護士が解説
雇止めの手続き

弁護士
岡本 裕明
事前に予告する
3回以上更新されている、あるいは1年を超えて継続して雇用されている労働者について契約を更新しない場合には、少なくとも契約満了の30日前には予告するようにしてください(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準2条)。
予告は口頭でも可能ですが、証拠を残すために書面で通知しましょう。
条件に当てはまらないとしても、トラブル防止や従業員の再就職を考えると、できるだけ早めに伝えるべきです。
なお、解雇と異なり、予告手当の支払いは必要ありません。
請求されたら理由証明書を発行する
労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なく交付してください(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準3条)。
書面に記載する理由は「契約期間の満了」以外でなければなりません。
たとえば、更新しないとの事前の合意、能力不足、勤務態度不良、事業縮小などが考えられます。
トラブル防止の観点からは、請求される前に理由を説明しておき、納得してもらうよう努めましょう。
正当に雇止めをするには弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、雇止めできる正当な理由などについて解説してきました。
雇止めの有効性は、解雇と同様の厳しい基準で判断されます。
解雇よりハードルが低いケースもありますが、無効とされると復職や賃金支払いのリスクが存在します。
トラブルを防ぐには、事前に弁護士に相談するとよいでしょう。
正しく雇止めできるかお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。ご相談いただければ、法律上雇止めができるか、どう進めればいいか、契約時の注意点は何かなどをアドバイスいたします。
もちろん、既に争いに発展している場合には迅速に対応します。
「雇止めに正当な理由があるといえるか知りたい」「雇止めした従業員とトラブルになっている」などとお悩みの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.雇止めが可能な正当な理由は何ですか?
- A.能力不足、勤務態度不良、病気・ケガ、犯罪行為(社内の重大な不正)、会社の経営不振が正当な理由です。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。

