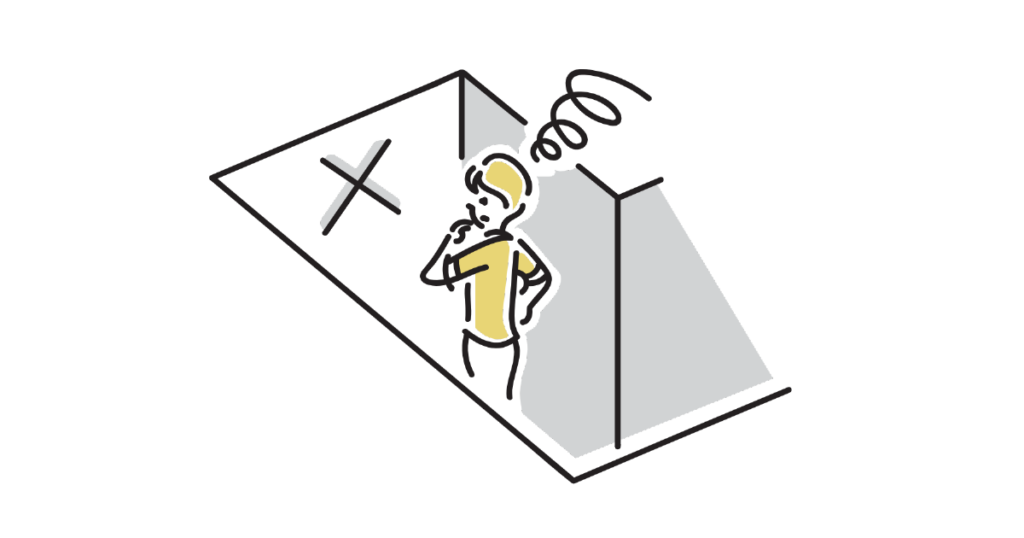お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
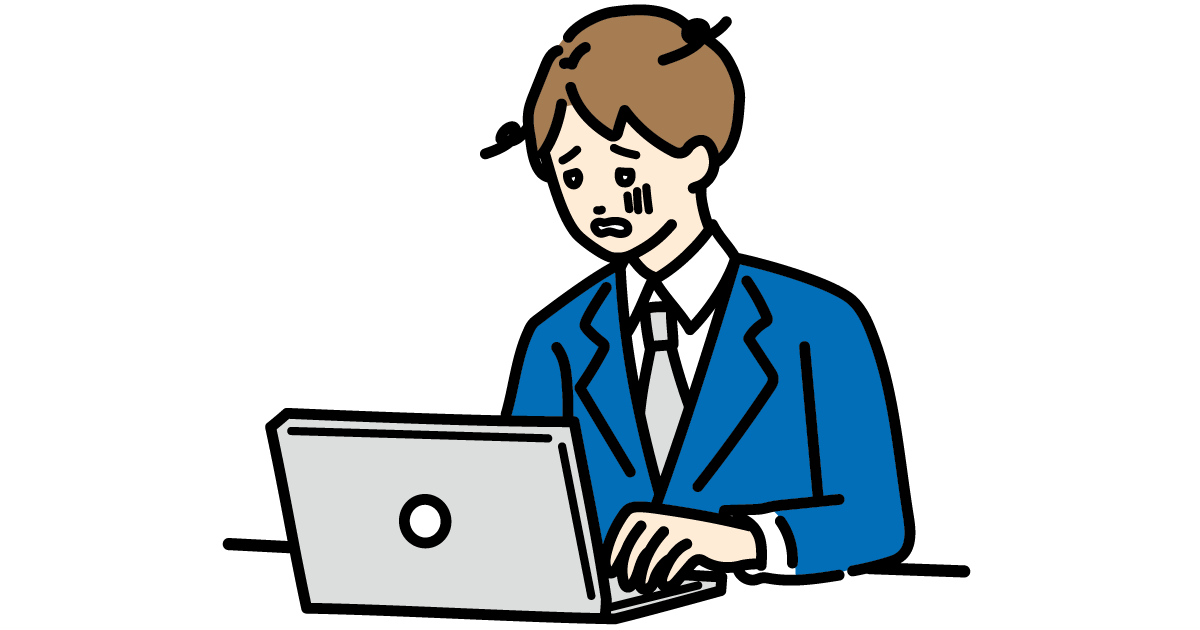
期間を定めて雇用している従業員であっても、期間満了に伴って契約を終了させられるとは限りません。
「雇止め法理」と呼ばれるルールにより、有期労働契約の終了には制限がかけられています。
雇止め法理が適用されるのは、事実上無期雇用と変わらないケースや、従業員側に雇用継続への期待が生じているようなケースです。
会社としては、雇止め法理のルールを把握するとともに、対策を講じなければなりません。
今回は、雇止め法理の概要や適用されるケース、会社がとるべき対策などを解説しています。
有期雇用の従業員を抱えている会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
雇止めと解雇の違いなどについては、以下の記事で解説しています。
参考記事:雇止めとは?解雇との違いや有効要件・手続きを弁護士が解説
雇止め法理とは?

弁護士
岡本 裕明
まずは、雇止め法理の内容を大まかに理解しましょう。
有期労働契約の終了を制限するルール
雇止め法理とは、期間の定めのある雇用契約について、終了を制限するルールです。
民法の原則によると、契約期間を定めている以上、期間が満了となれば当然契約も終わるはずです。
しかし、従業員が雇用が続くことを前提に生活を設計していた場合、契約終了により収入源を失うと生活が立ち行かなくなってしまいます。
そこで、労働者を保護するために、判例により雇止め法理と呼ばれるルールが作られてきました。
雇止めは解雇に似ているため、解雇に関する「解雇権濫用法理」と類似した規制により制限されています。
労働契約法19条で明文化された
判例により形成された雇止め法理は、現在は労働契約法19条に明記されています。
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
条文を見ても分かりづらいと思いますので、雇止め法理の要件を以下で詳しく見ていきます。
「適用される場面にあたるか」と「適用されるとして、雇止めに正当な理由があるか」に分けて考えるのがポイントです。
雇止め法理が適用されるケース

弁護士
岡本 裕明
順に解説します。
事実上無期雇用と変わらない
1つめは、繰り返し更新され事実上無期雇用と変わらなくなっているケースです(労働契約法19条1号)。
リーディングケースとなったのは、東芝柳町工場事件です。
【事案の概要】
・原告(複数名)は基幹作業に従事する臨時工
・基幹臨時工の作業内容は正規従業員と変わらない。
・契約期間2ヶ月の契約書をとりかわして雇用されたが、2ヶ月の期間満了により雇止めされた事例は見当たらず、希望して退職する者を除いてほとんどが長期間にわたって継続雇用されていた。
・採用時に「期間が満了しても真面目に働いていれば解雇されるようなことはない」などと言われていた。
・原告は5〜23回にわたって更新を重ねており、契約更新の手続きは必ずしもとられていなかった。
・業務態度不良や業務量減少を理由に雇止めされた。
【結論】
雇止めは無効
【ポイント】
原告との契約は当然に更新されており、期間の定めのない契約と実質的に変わらないケースです。雇止めは解雇の意思表示にあたるとし、解雇権濫用法理を類推適用すべきと判断されました。
事実上無期雇用と変わらないと判断されるのは、繰り返し更新されていたものの手続きが厳格になされておらず、過去に雇止めされた事例がないようなケースです。
雇用継続への期待がある
2つめは、労働者が雇用継続への期待を持つのが当然といえるケースです(労働契約法19条2号)。
時の流れにより更新手続きをしっかりと行う企業が増え、無期雇用と同視できるケースは減少しました。
そこで、判例は「雇用継続への期待があり、それはもっともだ」といえる場合にも、労働者を保護するようになりました。
代表的な判例は日立メディコ事件です。
【事案の概要】
・原告は工場の臨時工
・契約期間は2ヶ月であり、5回更新された。
・期間満了の都度新たな契約を締結していた。
・工場の採算悪化のため契約更新が拒否された。
【結論】
雇止めにはやむを得ない理由があり有効
【ポイント】
契約更新の手続きはなされており「実質的に無期雇用と変わらない」とはいえないケースでした。しかし、臨時的作業をしていたわけではなく、雇用の継続が期待されていたため、解雇権濫用法理が類推適用されるとされました。ただし結論としては、人員削減のためにやむを得なかったとして、雇止めは有効と判断されています。
更新手続きが厳格にされていると、「実質的に無期雇用と変わらない」とまではいえません。
しかし、以下の要素から「更新への期待が合理的」といえる場合には、雇止め法理が適用されます。
・業務内容(常にある業務であれば更新を期待しやすい)
・更新回数・通算期間(回数が多い、期間が長いと更新を期待しやすい)
・更新を期待させる会社の言動
労働契約法19条2号の類型については、更新が1度もないケースでも認められるなど、広い範囲で適用されています。
ただし、正当な理由があるとして、雇止め自体は有効とされるケースも多いです。
雇止め法理の要件

弁護士
岡本 裕明
合理性・相当性がない
雇止め法理が適用される場面において、雇止めが無効と判断されるのは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときです。
すなわち、有効にするためには、雇止めをしても仕方がないといえる状況でなければなりません。
客観的合理的理由や社会通念上の相当性は、解雇の有効性を判断するときと同様に判断します。
従業員の能力不足、勤務態度、病気・ケガ、会社の経営不振などが理由になり得ますが、実際に雇止めが認められるかはケースバイケースです。
ただし、正社員の解雇と比較して緩やかに判断し、会社側に有利な結論を出す裁判例も存在します。
雇止めできる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:雇止めできる正当な理由になることは?理由証明書についても解説
労働者の申込み
労働契約法19条では、上記の要件を満たしていることに加えて、労働者による申込みが要求されています。
労働者が契約更新を主張するには、以下のいずれかが必要です。
・契約期間満了前:更新の申込み
・契約期間満了後:遅滞なく契約締結の申込み
ただし、正式に書面等で申し入れる必要はありません。
雇止めに対して拒否や不満の意思を示せば要件を満たすと考えられています。
契約期間満了後についても、訴訟の提起や弁護士を通じた意思表示などで申込みと認められます。
したがって、労働者からの申込みの有無は、実際にはあまり問題になりません。
雇止め法理への対策

弁護士
岡本 裕明
以下のポイントに気をつけましょう。
契約をきちんと管理する
まずは、契約管理を厳格に行い、毎回更新手続きを踏むのが重要です。
更新を忘れていたり、手続きが形骸化したりしていると、無期雇用と変わらないと評価されてしまいます。
更新する際には、期間満了前に話し合いにより意思を確認する、契約書を作成するなど、きちんと手続きを踏むようにしてください。
更新回数や期間の上限を明示する
最初に契約する際に、更新回数や期間の上限を明記するのも有効です。
上限を超えれば雇止めをすると明確に説明して書面にしておけば、更新への期待が生じづらくなります。
とはいえ、実態として上限を超えて更新する人が多数存在していると、明示した意味が薄れてしまうので注意してください。
業務内容を正社員と変える
業務内容を正社員と変えるのも有効です。
有期雇用の従業員には一時的に発生する仕事を任せると、契約が更新されるとの期待を抱きづらいでしょう。
更新を期待させる言動をとらない
更新を期待させる言動には注意してください。
たとえば「契約期間はあるが、よほどのことがなければ更新されるので安心して欲しい」「これからもよろしく」といった言葉は、従業員に更新されるとの期待を与えてしまいます。
手続きを踏む
有効に雇止めできるケースであっても、トラブル防止のために手続きは怠らないでください。
雇止めを決めたら、早めに伝えましょう。
特に3回以上更新されている、あるいは1年を超えて継続して雇用されている労働者について契約を更新しない場合には、少なくとも契約満了の30日前には予告しなければなりません。(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準2条)。
また、理由を説明して理解してもらうのも重要です。
労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なく交付しなければなりません(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準3条)。
雇止めに関するトラブル・疑問は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、雇止め法理の内容や対策を解説してきました。
事実上無期雇用と変わらないケースや、労働者が更新を期待するようなケースでは、雇止めが無効になるおそれがあります。
終了時だけでなく、契約当初から注意してください。
従業員の雇止めについてお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
ご相談いただければ、法律上雇止めができるか、どう進めればいいか、契約時の注意点は何かなどをアドバイスいたします。
もちろん、既に争いに発展している場合には迅速に対応します。
「雇止めが法律上有効にできるかわからない」「雇止めした従業員とトラブルになっている」などとお悩みの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.雇止め法理とは何ですか?
- A.有期労働契約の終了を制限し、事実上無期雇用と同等に扱うケースで契約更新を拒否できないルールです。
- Q.雇止め法理が適用される主なケースは何ですか?
- A.繰り返し更新された契約で実質的に無期雇用とみなされる場合、または労働者が継続を期待できる合理的理由がある場合です。
- Q.会社側は雇止め法理に対してどのような対策を取るべきですか?
- A.有期契約の更新手続きを明確にし、合理的な理由を文書化して拒否する場合は社会通念上相当であることを示す必要があります。
- Q.雇止め法理と解雇の違いは何ですか?
- A.雇止めは契約期間満了時の終了であり、解雇は無期労働契約に対する意思表示である点が異なります。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。