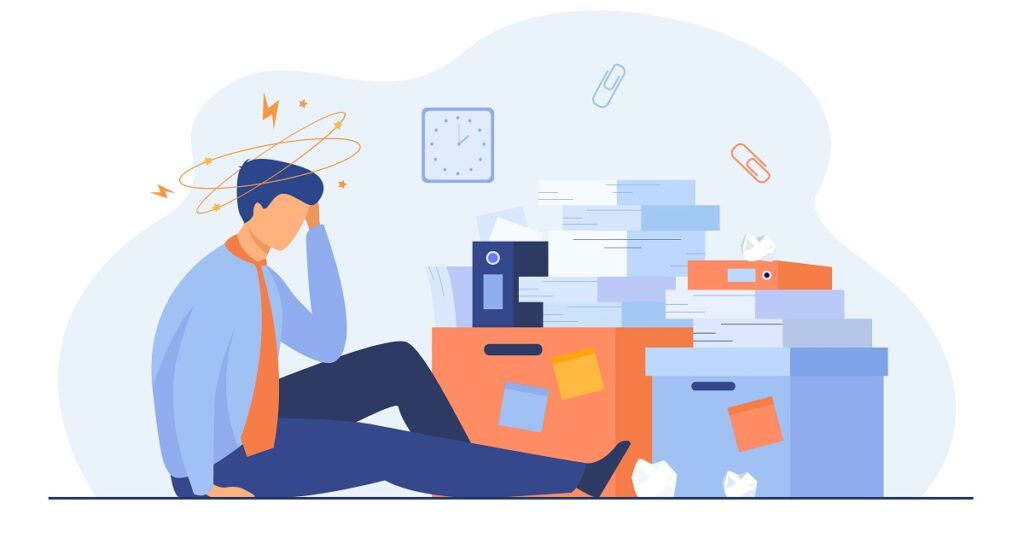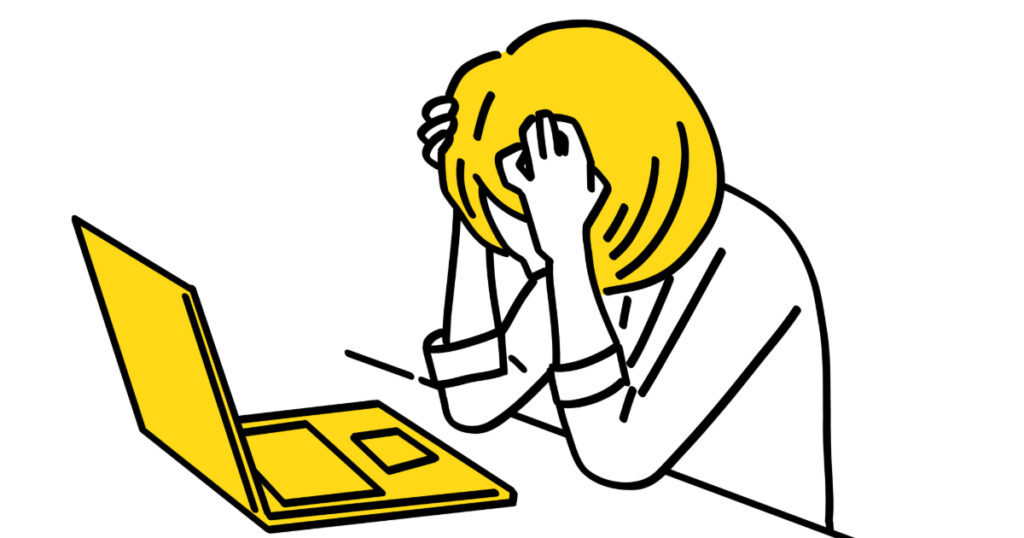お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

近年、メンタルヘルス不調を訴える労働者が増加傾向にあります。
うつ病をはじめとする精神疾患を発病している従業員が業務を続けると症状が悪化し、最悪の場合自殺に追い込まれるリスクも存在します。
従業員のメンタルヘルス不調を放置した企業の責任も問われかねません。
そこで選択肢になるのが休職です。
医師の診断をもとに、就業規則のルールにしたがって休職させます。
会社としては、休職制度を十分に理解し、復職まで視野に入れて対応を進めなければなりません。
今回は、うつ病の従業員を休職させる流れ・注意点や復職時の対応などについて解説しています。
うつ病などの精神疾患に罹患した従業員がいる会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
メンタルヘルス不調を抱えた従業員への対応全般については、以下の記事で解説しています。
参考記事:メンタルヘルス不調の従業員への対処法・防止策を会社側弁護士が解説
うつ病による休職の基礎知識

弁護士
岡本 裕明
まずは、うつ病による休職について、基本的な知識を確認しておきましょう。
そもそも休職とは?
一般的に休職とは、従業員が業務に従事できない状態であるときに、雇用契約関係を維持しつつ、会社が労働を免除あるいは禁止する制度です。
従業員は療養に専念でき、会社としては人材を直ちに失わずにすむメリットがあります。
休職は法律で定められた制度ではありません。
とはいえ、多くの会社で休職制度が存在しており、就業規則等に規定されています。
休職にはいくつか種類がありますが、うつ病による休職は傷病休職(病気休職)に該当します。
傷病休職は、業務外の事情によるケガ・病気に対して休職を認める制度です。
業務が原因でうつ病になった場合には労災に該当するので注意してください。
うつ病による労災については、以下の記事で解説しています。
参考記事:うつ病は労災認定される?認定基準や会社の対応を弁護士が解説
うつ病による休職期間
平成28年度に発表された報告によると、うつ病を含むメンタルヘルス不調による休職期間は1回目で平均107日(約3.5ヶ月)、2回目で平均157日(約5ヶ月)となっています(参考:主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究p.383)。
これはあくまで平均であり、症状が軽ければ1ヶ月程度ですむのに対し重度だと1年以上を要するなど、千差万別です。
休職期間の上限は、会社ごとに就業規則などで定められています。
勤続年数に応じて変わるとする企業も多いです。
休職期間を満了しても復職できないときは、就業規則のルールにしたがって解雇または自然退職となります。
うつ病で休職させるまでの流れ

弁護士
岡本 裕明
順に詳しく解説します。
就業規則を確認する
休職は、法律で定められた制度ではありません。
会社によってルールが異なるため、そもそも制度が存在するかも含め、まずは就業規則を確認する必要があります。
具体的には、休職の要件、期間、給与の扱い、社会保険料の負担、復職の手続きなどを確認しましょう。
たとえば、長期間の欠勤が休職の要件になっていると、うつ病の場合だと満たさずに休職を命じられない可能性があります。
休職制度の利用実績が少ない会社は、特に注意深く就業規則を確認するようにしてください。
診断書を提出させる
休職の必要性や期間を判断するために、医師の診断書を提出させましょう。
とりわけ精神疾患は外見だけでは深刻度が判断しづらいため、専門家の意見が欠かせません。
診断書で病名や労働できない期間を確認します。
精神疾患の場合、周囲から見て明らかに業務に支障が生じているにもかかわらず、病院に行っていないケースが少なくありません。
放置すると本人の症状が悪化するだけでなく会社に責任が生じるおそれもあるため、受診を促すようにしてください。
休職を命じる
休職が必要と判断した場合、会社は休職命令を出します。
後から開始時期や期間をめぐってトラブルになるのを防ぐため、就業規則の根拠規定を示して書面でするようにしてください。
期間だけでなく、給与(無給の場合が多い)、休職中の連絡頻度や方法、復職の手続き、復職できない場合の扱いなどについても、面談及び書面で説明しておきましょう。
休職する従業員は経済面でも不安を抱えやすいため、傷病手当金や社会保険料などについても説明するのが重要です。
うつ病による休職中の注意点

弁護士
岡本 裕明
休職中は、事前に決めた頻度・方法で連絡し、状況を把握するようにしましょう。
「会社に気にかけてもらっている」と思わせるとともに、復職の可否の判断材料にするためです。
たとえば「月1回・電話」といったやり方が考えられますが、難しい場合にはメールでやりとりするなど、柔軟に対応するようにしてください。
連絡する際は、具体的な業務の話題は避けましょう。
たしかに休職中は療養に専念する義務がありますが、会社が私生活に細かく干渉するのは望ましくありません。病状への配慮が求められます。
うつ病による休職から復職するときの会社の対応

弁護士
岡本 裕明
うつ病からの復職について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:うつ病の従業員を復職させてよい?流れや判断基準・注意点を解説
復職の可否を判断する
従業員から復職の申し出があった際には、会社として復職の可否を判断しなければなりません。
「復職可能」との診断書があっても、主治医が業務内容を把握していないケースや、本人に言われるがまま書いているだけのケースもあります。
診断書を提出させるだけでなく、必要に応じて主治医へのヒアリングや産業医との面談を行ってください。
元の業務への復帰が難しくても、別の業務を行わせるべき場合があります。
慎重に検討しましょう。
復職後も必要な配慮をする
うつ病などの精神疾患は再発のリスクが高いです。
復帰後も必要な配慮をするようにしてください。
たとえば、当初は時短勤務にする、負担の軽い業務から始めるといった方法が考えられます。
復職できないときは解雇・自然退職
休職期間が満了しても復帰が難しい場合には、就業規則の定めにしたがって解雇または自然退職となります。
ただし、うつ病が業務を原因とする場合には労災となり、基本的に解雇できません(労働基準法19条1項)。
トラブルになりやすいポイントなので注意してください。
休職を繰り返す従業員への対策
うつ病は再発しやすく、復職したものの短期間で休職を繰り返す従業員も存在します。
継続して業務にあたってもらえず、会社としては対応が難しいでしょう。
必要以上に休職を繰り返されないためには、制度設計に工夫が必要です。
同一・類似の理由では1回のみとする、期間を制限するなど、精神疾患に対応しやすい制度にしておくのがよいでしょう。
うつ病で休職が必要な従業員がいるときは弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、うつ病による休職について、流れや注意点などを会社の立場から解説してきました。
うつ病は外からはわかりづらいものの、現代においては深刻な問題です。決して軽視せずに、適切に休職制度を設計したうえで具体的な事案に対応しなければなりません。
うつ病により休職が必要な従業員への対応にお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。休職までの流れや適切な対処法についてアドバイスいたします。既にトラブルになっている場合も迅速に対応いたします。
「うつ病で休職させるべきかわからない」「うつ病の従業員への対処法を知りたい」とお悩みの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.うつ病の従業員を休職させる際に必要な手続きは何ですか?
- A.まず就業規則を確認し、診断書を提出させた上で休職命令を書面で出します。
- Q.休職期間はどのくらいが平均ですか?
- A.平成28年度の報告では、1回目で平均107日(約3.5ヶ月)、2回目で平均157日(約5ヶ月)です。
- Q.休職中の従業員への連絡はどのようにすべきですか?
- A.事前に決めた頻度・方法で連絡し、業務話題は避けて心のケアを行うことが重要です。
- Q.復職時に会社が判断すべきポイントは?
- A.医師の診断書だけでなく主治医・産業医へのヒアリングを行い、必要なら別業務や時短勤務を検討します。
- Q.休職期間満了後に復職できない場合、会社はどう対処すべきですか?
- A.就業規則に従い解雇または自然退職となりますが、業務原因であれば労災扱いになり解雇できません。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。