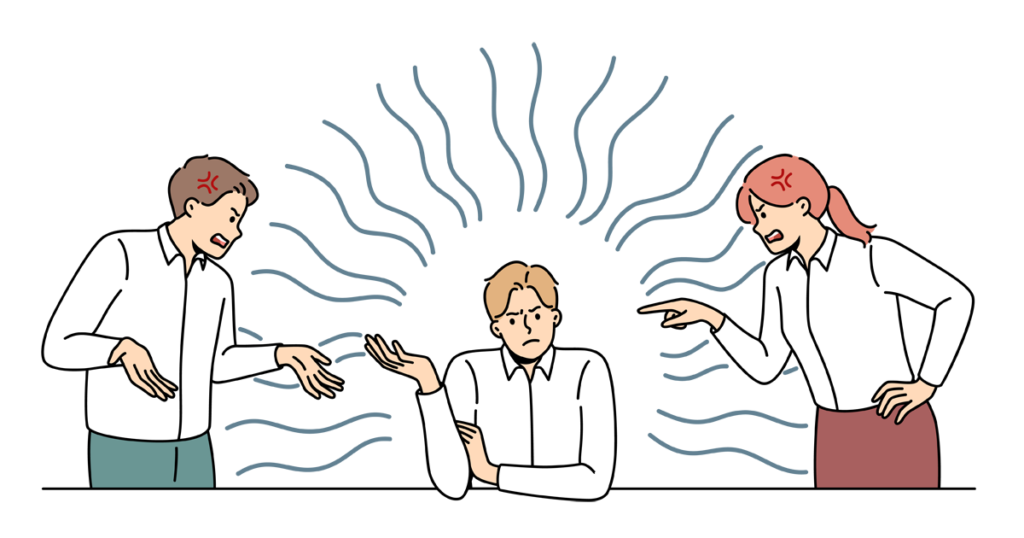お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

企業には採用の自由があり、採用人数・募集方法・採用基準などを自由に決められます。採用に際して必要な調査も可能です。もっとも、男女差別の禁止など、採用の自由には一定の制限があります。損害賠償を請求されるおそれがあるため、ルールにしたがって採用活動をしなければなりません。
今回は、採用の自由について、内容や制限、代表的な判例を解説しています。人材を採用しようと考えている企業の経営者や人事担当者の皆様に知っておいて欲しい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
内定や試用期間も含めて知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
参考記事:採用・内定・試用期間の意味や企業が注意すべき法的問題点
採用の自由とは?

弁護士
岡本 裕明
企業には、事業を行うにあたって誰を採用して雇用契約を結ぶかについて自由が認められており、「採用の自由」と呼ばれます。
憲法22条、29条では経済的自由が保障されており、自由な経済活動を行ううえで不可欠となる「契約の自由」が民法の原則として認められています。中でも雇用契約を結ぶ場面における契約の自由を意味するのが「採用の自由」だとお考えください。
我が国においては「解雇権濫用法理」により一旦雇用した後の解雇が厳しく規制されています。そのため、入口にあたる採用の自由は、企業が有能な人材を獲得して事業を営むうえでとりわけ重要です。
解雇については、以下の記事で解説しています。
参考記事:解雇とは?退職勧奨とは?両者の違いや注意すべき点を会社側弁護士が解説
採用の自由の内容

弁護士
岡本 裕明
雇入れ人数決定の自由
まず、企業はそもそも採用をするか、するとしてその人数を自由に決められます。会社として事業を営んで利益をあげようとするうえで、何人採用するのかを自由に決定できるのは重要な要素のひとつです。
募集方法の自由
募集方法も会社が自由に決められます。いかなる方法で募集するかは、応募してくる労働者の人数・性質・属性を大きく左右するでしょう。
企業はハローワーク、広告情報誌、学校への求人など、募集方法を自由に決められます。公募せずに、縁故採用を選択しても構いません。
選択の自由
応募してきた労働者のうち誰を採用するかは自由です。どの人を採用するかだけでなく、いかなる基準で選考するかも自由に決められます。いかなる人材を採用するかによって会社の業績は変わってくるため、選択の自由は非常に重要です。
もっとも、一定の場合には選択の自由が制限されます。詳しくは後述します。
契約締結の自由
誰と雇用契約を結ぶかが自由であるだけでなく、特定の労働者との契約締結は強制されない点もポイントです。採用する人を外部から勝手に決められないということです。
たとえ採用過程に問題があって損害賠償が発生したとしても、雇用契約を結ぶことまでは基本的に強制されません。
調査の自由
採用過程では調査の自由も認められています。企業が採用・不採用を判断するにあたっては、能力・適性を見極めるために様々な情報が必要です。そこで、適切な選考のために必要な情報を収集できるものとされています。
もっとも、選考と関係ない情報を集めたり、プライバシー侵害になるような方法で調査したりすることは許されません。
採用の自由に対する制限

弁護士
岡本 裕明
法律により採用の自由を制限するものとしては、以下が挙げられます。
・労働組合の不加入・脱退を雇用条件とする「黄犬契約」の禁止(労働組合法7条1号)
・男女差別の禁止(男女雇用機会均等法5条)
・障害者に対する差別の禁止(障害者雇用促進法34条)
・年齢制限の原則禁止(労働施策総合推進法9条)
質問・調査をすべきでない事項としては、出生地、家族の職業、宗教・支持政党といった思想・信条に関係することなどが挙げられます。「業務に関係のないことは聞かない」と意識しておきましょう。
参考記事:不当労働行為とは?類型や具体例・会社側のリスクをわかりやすく解説
採用の自由に関する判例

弁護士
岡本 裕明
採用の自由に関する有名な判例が「三菱樹脂事件」です。
【事案の概要】
原告は、被告会社の採用試験に合格し、大学卒業と同時に雇用された。しかし、試用期間の満了にあたって、採用試験の際に提出した身上書に虚偽の記載をした(在学中に学生運動に参加した事実を記載しなかったなど)ことを理由に本採用を拒否された。原告が労働者としての地位を有することの確認を求めて提訴したところ、1審・2審ともに本採用拒否が無効とされたため、被告会社が最高裁に上告した。
【結論】
破棄差戻し
【ポイント】
最高裁は以下の通り判示しました。
「企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」
判決では、採用の自由が広く認められています。とはいえ、適正・能力に関係のない事項を採用基準としたり質問したりすることはないよう注意してください。
採用に関する法的問題は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、採用の自由について、内容や制限、判例などを解説してきました。
採用の自由は広く認められていますが、男女差別や無関係な質問などは許されません。選考にあたっては細心の注意を払いましょう。
採用に関する法的問題は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。ご相談いただければ、採用条件や方法に法的な問題はないかをアドバイスいたします。トラブルに発展している場合にも迅速に対応いたします。
「採用トラブルを避けたい」とお考えの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.採用の自由とは何で、なぜ企業にとって重要なのですか?
- A.採用の自由とは、企業が誰を雇うか、人数や募集方法・選考基準などを自由に決められる権利で、解雇が厳しく制限される日本において、有能な人材を確保するための重要な手段です。
- Q.採用自由に対してどんな法的制限がありますか?
- A.男女差別・障害者差別・年齢制限の禁止、労働組合加入・脱退を条件にした契約(黄犬契約)の禁止、そして業務に関係のない個人情報(出生地・宗教・支持政党等)の質問が禁止されています。
- Q.企業は政治的信条を理由に採用を拒否できますか?
- A.特定の法律で禁止されていない限り、政治的信条を理由に採用を拒否することは原則として可能ですが、無関係な基準での差別は禁止されているため注意が必要です。
- Q.三菱樹脂事件の判決は採用自由にどんな影響を与えましたか?
- A.最高裁判決は、企業が特別な法的制限がない限り採用自由を広く認めるとし、雇用条件や選考基準は企業側が自由に決定できると判断しました。ただし、無関係な事項を採用基準にすることは避けるべきと示しました。
- Q.企業が採用時に法的リスクを避けるためには何をすべきですか?
- A.業務に直結する選考基準のみを用い、個人のプライバシーや差別に関わる質問は行わないこと。疑問点がある場合は弁護士に相談し、適正な採用手続きを徹底することが重要です。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。