お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
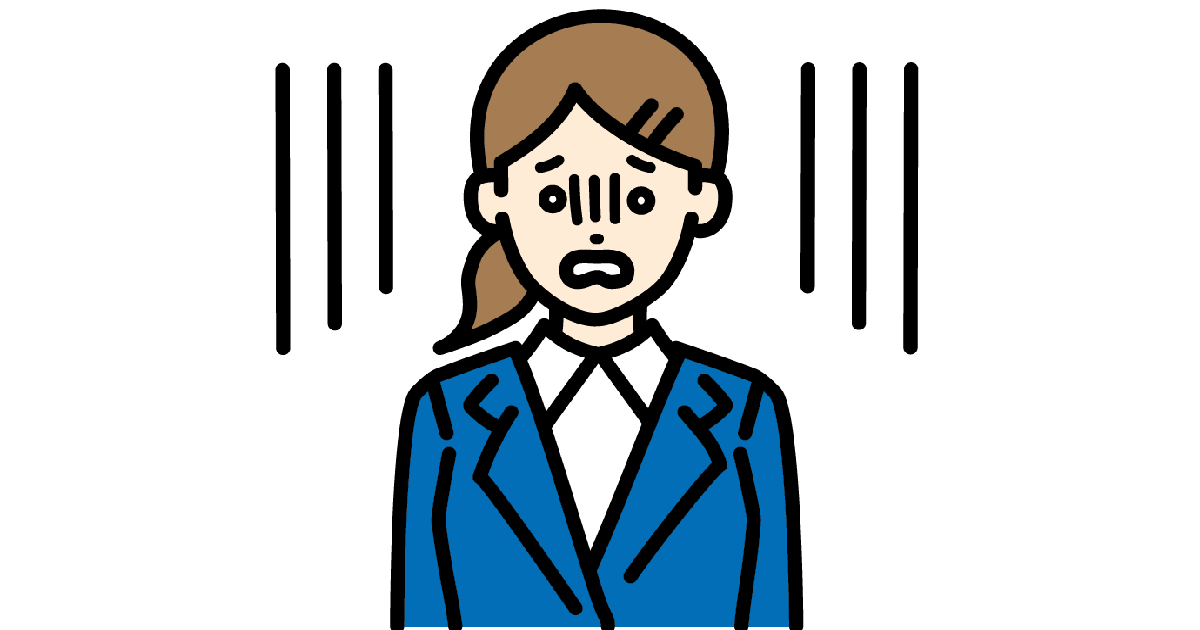
セクハラ(セクシュアルハラスメント)とは、相手の意思に反する性的な言動です。
職場においては「対価型」「環境型」といった種類があります。
セクハラがあると社内環境が悪化し、加害者本人だけでなく企業も法的責任を問われるリスクが高いです。
会社として対策をとらなければなりません。
今回はセクハラの定義や種類、会社がとるべき対策などを解説しています。
セクハラ対策にお悩みの会社経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
セクハラ・パワハラに関する基礎知識は、以下の記事でも解説しています。
参考記事:セクハラ・パワハラとは?会社が負う責任やとるべき対策を解説
セクハラとは?

弁護士
岡本 裕明
意味を把握していないと対策はとれません。まずは、職場におけるセクハラについて定義を見ていきましょう。
法律における定義
法律上、職場でのセクハラに関しては男女雇用機会均等法に定めがあります。
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
セクハラとは、職場において行われる、労働者の意思に反する性的な言動です。
以下では「職場」「労働者」「性的な言動」の意味につき順に説明します(参考:職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です|厚生労働省)。
セクハラの判断基準について詳しくは、以下の記事でも解説しています。
参考記事:セクハラはどこから?判断基準や裁判例を弁護士が解説
職場の範囲
職場としてまずイメージするのは、事務職であれば勤務している事務所、現場仕事であれば作業現場など、普段業務にあたる場所でしょう。
もっとも、セクハラが行われるのはそうした場所に限られません。
たとえば、移動中の車内、取引先の事務所、打ち合わせや接待のために利用する飲食店など、業務中に訪れる場所も職場に含まれます。
業務時間外であっても、職務の延長として行われる宴会の最中に性的言動があれば、セクハラに該当し得ます。
セクハラが行われる場所は、一般的にイメージする職場に限らないことは頭に入れておきましょう。
対象となる労働者の範囲
労働者には、正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどが含まれます。
非正規労働者もセクハラの当事者になり得るということです。
派遣労働者については、派遣元だけでなく、派遣先の事業主もセクハラに関する必要な措置を講じなければなりません。
性的な言動
性的な言動とは、性的な発言や行動をいいます。
例としては以下が挙げられます。
・性的な質問をする
・顔や体の特徴をからかう
・卑わいな冗談を言う
・必要がないのに身体に触れる
・性的な物や写真を職場に置く、配布する
・執拗にデートに誘う
・性別による役割分担を押し付ける
・他の従業員の性的指向を暴露する
男性から女性に限らず、女性から男性への性的言動もセクハラです(逆セクハラ)。
同性間の言動もセクハラになり得ます。
セクハラの種類

弁護士
岡本 裕明
対価型
対価型とは、対応により労働条件につき不利益を受けるタイプのセクハラです。
例としては以下が挙げられます。
・社長との性行為に応じないことを理由に解雇する
・上司からの身体接触を拒んだ従業員を降格処分にする
・セクハラに抗議した従業員を別の部署に異動させる
対価型は、被害者が弱い立場にある状況に乗じたセクハラといえます。
環境型
環境型とは、性的な言動により就業環境が害されるタイプのセクハラです。
例としては以下が挙げられます。
・性的な会話をする
・ヌード写真を掲示する
・必要がないのに身体に触れる
性的な役割を押し付ける行為(例:宴会で女性に晩酌を強制する)、断られているのに食事・デートに執拗に誘う行為などもセクハラです。
環境型のセクハラは、対価型と比べて、加害者に自覚が薄い点が特徴といえます。
企業がセクハラ対策をとらないリスク

弁護士
岡本 裕明
行政指導・公表の対象になる
セクハラ対策は法的義務です(男女雇用機会均等法11条1項)。
十分な対策をとらないと、行政指導や勧告、企業名の公表といった処分がなされる可能性があります(同法29条、30条)。
損害賠償を請求される
会社が被害者から損害賠償を請求されるおそれもあります。
加害者本人だけでなく、会社にも法的責任が生じ得るためです。
法的な根拠は、加害者の行為に関する使用者責任(民法715条)である場合が多いです。
「職場環境調整義務違反」として直接不法行為責任(民法709条)や債務不履行責任(民法415条)を負うケースもあります。
生産性の低下・離職
セクハラが発生する職場では、直接の被害者はもちろん、周囲の従業員も働きづらくなり、生産性が低下するおそれがあります。
会社に失望して離職の動きが出る可能性もあるでしょう。
職場全体でセクハラが蔓延しているケースはもちろん、ひとりでも問題のある従業員がいれば周囲に悪影響を及ぼしてしまいます。
社会的イメージの悪化
セクハラ対策が進んでいない会社は「価値観が古い」との印象を持たれてしまい、社会的なイメージが悪化するリスクが高いです。
取引や採用への影響も懸念されます。
現代は、SNSを通じて簡単に情報が拡散されてしまう時代です。
「セクハラが当たり前の会社」とのイメージが広がってしまうと、致命的なダメージが生じるでしょう。
会社がとるべきセクハラ対策

弁護士
岡本 裕明
参考:職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です|厚生労働省
方針の明確化・周知啓発
まずは、セクハラに該当する行為の内容・セクハラをしてはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発しなければなりません。
就業規則等において加害者に厳しく対処する旨を規定し、社内報や研修を通じて周知徹底するようにしましょう。
相談体制の整備
相談体制の整備も重要です。
単に相談窓口を設置するだけでなく、従業員に存在を知らせて相談しやすいようにしておかなければなりません。
マニュアルの整備や研修を通じて、相談を受ける側が適切に対応できるようにする必要もあります。
発生後の対応
万が一発生した場合には、まずは事実関係を正確に確認しましょう。
当事者双方への聴き取りだけでなく、第三者への事情聴取等の調査が必要な場合もあります。
セクハラの事実が確認できたら、状況に応じて加害者への懲戒処分や配置転換、被害者のメンタルヘルス不調への対応などを進めましょう。
他の従業員に改めて研修を実施するなど、再発防止のための取り組みも不可欠です。
その他の措置
ここまで紹介したものに加えて、当事者のプライバシーの保護も必要になります。
また、相談や調査への協力を理由に不利益に取り扱ってはならない旨を定め、社内で周知・啓発するのも重要です。
セクハラ対策は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、セクハラの定義や会社がとるべき対策などを解説してきました。
セクハラとは、相手の意に反した性的な言動です。
職場では、相手に不利益を生じさせるものや、職場環境を害するものなどがあります。
会社としては、研修等を通じてセクハラを防止しつつ、相談があった際には適切に対応しなければなりません。
セクハラへの対応にお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
研修や相談窓口設置などの事前対策だけでなく、発生時の対応もお任せいただけます。
「何がセクハラに該当するのかわからない」「発生時の対処法を知りたい」などとお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
- Q.セクハラとは何ですか?
- A.職場で相手の意思に反する性的な言動を行うことです。
- Q.対価型と環境型の違いは何ですか?
- A.対価型は労働条件に不利益を与える行為、環境型は就業環境を害する性的言動です。
- Q.会社が取るべき対策は何ですか?
- A.相談窓口の設置、研修実施、迅速な対応と報告体制を整備することです。
- Q.非正規労働者もセクハラの対象になりますか?
- A.はい、正社員だけでなく契約社員・派遣労働者も対象です。
- Q.逆セクハラや同性間のセクハラは違法ですか?
- A.はい、性別や性的指向に関係なくすべてのセクハラは違法です。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。





