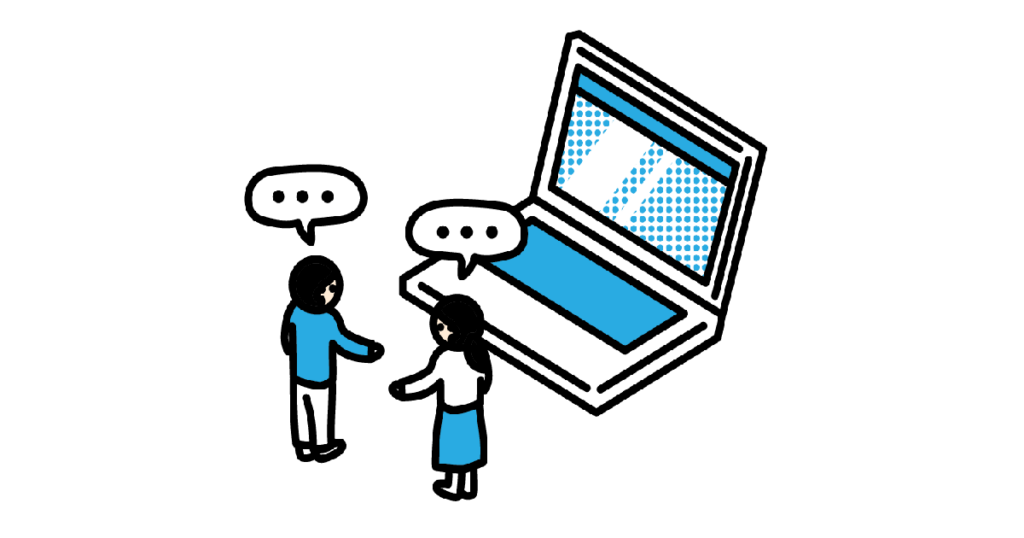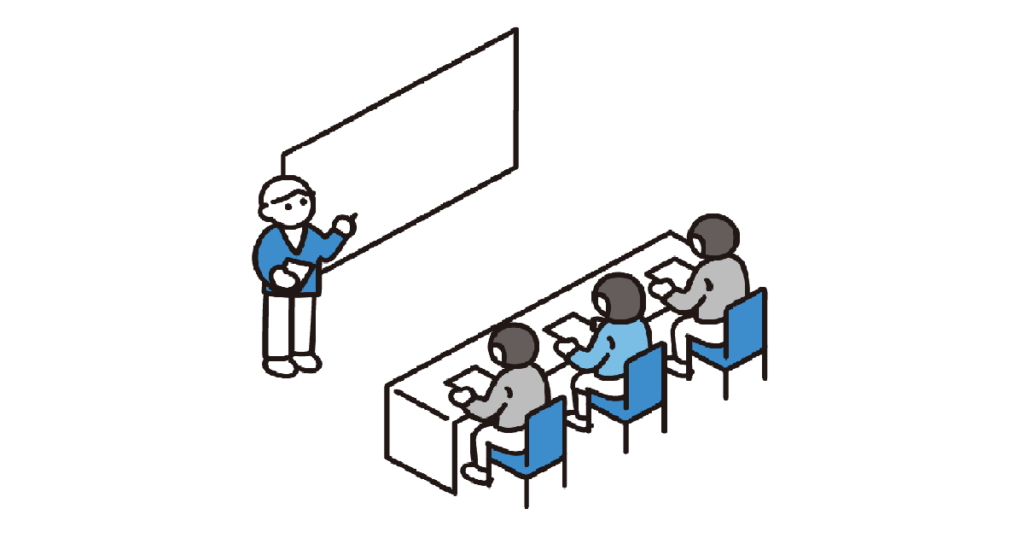お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

就業規則は職場のルールブックであり、労働契約の内容を決める、最低基準を定めるといった強い効力を有します。
ただし、法令や労働協約に反する部分は無効です。
就業規則の効力を知っておくことは、会社として職場のルールを把握するための基本といえます。
最低限の知識を持っておきましょう。
今回は、就業規則の効力や発生要件、発生時期などを解説しています。
会社経営者や人事労務担当者の皆様に知っておいて欲しい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
就業規則に関する全般的な基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:就業規則とは?効力や記載事項、作成・変更方法を弁護士が解説
就業規則の効力と発生要件

弁護士
岡本 裕明
以下で、就業規則の効力や発生要件を順に見ていきましょう。
労働契約の内容を決める
従業員を採用して労働契約を締結する際に、就業規則で定められた労働条件は労働契約の内容となります。
このことは、労働契約法7条に記載されています。
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない
労働者が会社に雇用される際には、就業規則に従うことが当然の前提とされています。
したがって、個別に同意をとっていなくとも、就業規則が労働契約の内容となります。
たとえば、会社が就業規則で役職定年を定めていれば、入社時に別途合意がなくとも従わせることが可能です。
なお、就業規則よりも労働者に有利な条件を個別に定めていたときには、個別に合意した条件が労働条件となります。
合理性と周知が要件
採用時に就業規則を労働契約の内容とするための要件としては、
- 合理的な労働条件であること
- 就業規則が周知されていること
が定められています。
まず、就業規則が定める労働条件がそれ自体不合理であれば労働契約の内容とはなりません。
とはいえ、ほとんどのケースで合理性が認められています。
たとえば、健康確保のために必要な場合の精密検査受診義務(電電公社帯広局事件判決・最高裁昭和61年3月13日)や会社の時間外労働命令権(日立製作所武蔵工場事件判決・最高裁平成3年11月28日)は合理的と判断されました。
また、就業規則の周知も要件となっています。
ここでいう周知とは、実質的に見て事業場の労働者に対して就業規則の内容を知り得る状態に置いていることをいいます。
就業規則が見られる場所を伝えるなどして、必要なときに簡単に確認できる状態であれば構いません。
したがって、実際に採用時に労働者が就業規則の内容を知っていたかは問われません。
なお、労働基準監督署への届出(労働基準法89条)や従業員の代表への意見聴取手続き(同法90条)を踏んでいなくとも、採用時の労働条件を決める効力に影響はないとされています。
変更したときに労働条件が変わる
採用後においては、個々に合意をとれば労働条件を変更できますが(労働契約法8条)、合意なく就業規則の変更により労働条件を変更することはできないとされています(労働契約法9条本文)。
ただし、周知と合理性の要件が満たされれば、就業規則の変更による労働条件の変更が可能です(労働契約法10条)。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
周知と合理性の要件が満たされれば、就業規則の変更に反対する従業員に対しても、変更後の労働条件が適用されます。
最低基準を定める
就業規則には、労働条件の最低基準を定める効力があります。
就業規則を下回る労働条件を労働者と個別に定めたとしても無効となり、就業規則で定められた労働条件が適用されます。
このことを規定したのが労働契約法12条です。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
たとえば、就業規則で「定年は70歳」とされているのに個別に「定年は65歳」と定めても無効であり、就業規則にしたがって70歳になります。
就業規則が最低基準を定めるという効力を有するには、周知(実質的に見て事業場の労働者が就業規則の内容を知り得る状態であること)が必要です。
この効力は、会社が労働基準監督署への届出や従業員代表への意見聴取を怠ったとしても発生します。
法令・労働協約に反する部分は無効
就業規則が法令や労働協約に反している場合、反している部分は無効です。
労働契約法13条に定められています。
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
たとえば、「有給は付与しない」と就業規則で定めても、労働基準法39条に反するため無効です。
就業規則が、会社と労働組合で定めた労働協約に反する場合も同様です。
就業規則と他のルールの優先順位
法令・労働協約・就業規則・労働契約の優先関係をまとめると以下の通りになります。
なお、前述の通り、労働契約で就業規則よりも労働者に有利な条件を定めていたときには、個別に合意した条件が労働条件となります(労働契約法7条ただし書)。
就業規則の効力はいつからいつまで?

弁護士
岡本 裕明
退職後の従業員には基本的に効力を有しませんが、競業避止義務や秘密保持義務は生じ得ます。
周知したときに発生
就業規則の各種効力は、従業員に周知された日から発生します。
作成日や労働基準監督署への届出日ではありません。
なお、就業規則に施行日が規定されており、それが周知された日よりも後であるときには、記載された施行日に効力が生じます。
退職後も一部は効力が続く
就業規則の効力は在職中の従業員に及ぶのであり、退職後は基本的に効力を有しません。
例外的に、競合他社への転職、競合会社の起業などを禁じる「競業避止義務」や、職務上知った機密事項を外部に漏らすことを禁じる「秘密保持義務」が残る場合があります。
とはいえ、これらは労働者の職業選択の自由や営業の自由を制限する規定です。
内容によっては無効になり得るので注意してください。
参考記事:退職後の競業避止義務|有効範囲や会社ができることを解説
効力のある就業規則の作成・変更は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、就業規則の効力や発生要件、発生時期などを解説してきました。
就業規則には、労働契約の内容を決める、最低基準を定めるといった強い効力があり、周知などの要件を満たすことで効力を発生させられます。
とはいえ何でも規定できるわけではなく、法令や労働協約に反する部分は無効です。
就業規則の作成・変更を検討している方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
ご相談いただければ、就業規則の作成・変更の内容や必要な手続きについてアドバイスいたします。
会社の実情に即した内容とするには、ひな形のままでは不十分です。
専門家への相談・依頼をオススメします。
「自社にとって効果的な就業規則を作りたい」とお考えの方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.就業規則は何を決定する効力がありますか?
- A.労働契約の内容や最低基準を定める強い効力があり、従業員の労働条件に直接影響します。
- Q.就業規則が有効になるための要件は何ですか?
- A.合理的な労働条件であることと、従業員に周知されている状態が必要です。
- Q.就業規則の変更は従業員にどのように影響しますか?
- A.周知され合理的であれば、変更後の規則が労働条件となり、従業員は新しい条件を受け入れなければならず、反対しても適用されます。
- Q.就業規則が法令や労働協約に反した場合、どうなりますか?
- A.その部分は無効となり、法令・協約が優先されます。
- Q.退職後も就業規則の効力は残りますか?
- A.基本的には効力がなくなりますが、競業避止義務や秘密保持義務などは残る場合があります。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。