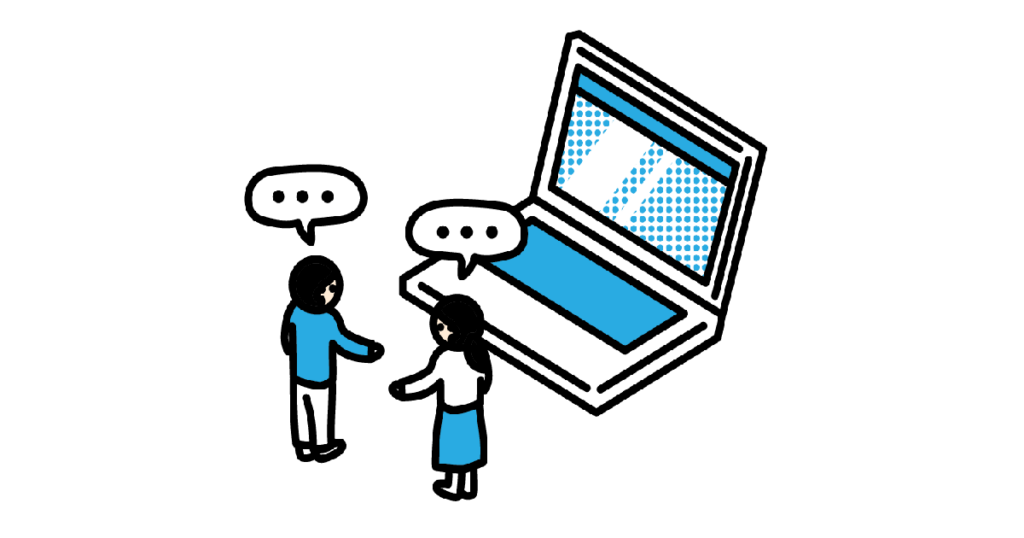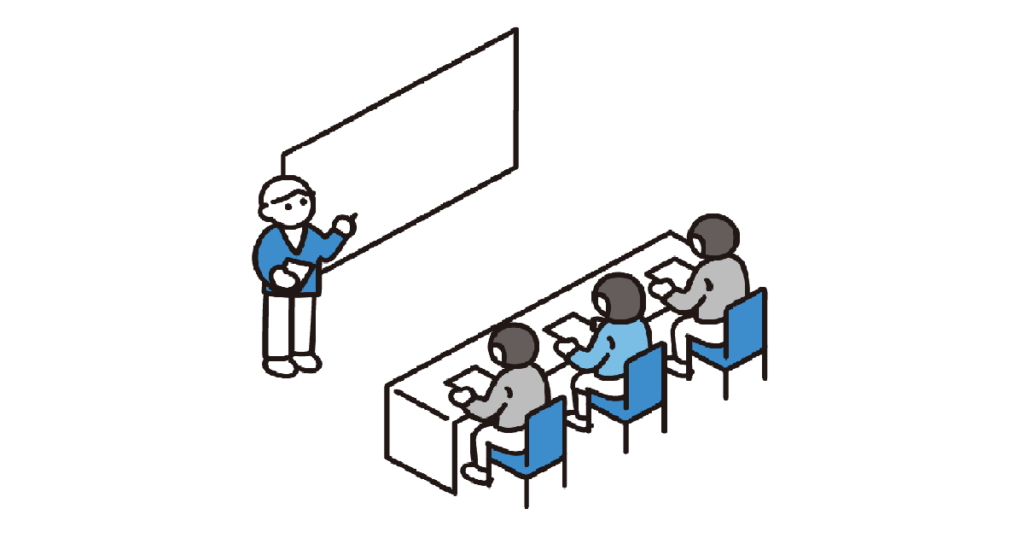お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

就業規則を作成・変更した際には、従業員に周知しなければなりません。
周知方法としては、職場での掲示、従業員への交付、データの共有などが挙げられます。
周知を怠ると法令違反です。
効力を否定されるリスクもあるため、必ず実施するようにしましょう。
今回は、就業規則の周知について、方法や違反するリスクなどを解説しています。
就業規則を作成している会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
就業規則に関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:就業規則とは?効力や記載事項、作成・変更方法を弁護士が解説
就業規則には周知義務がある!

弁護士
岡本 裕明
周知する意義
会社は、作成・変更した就業規則を従業員に周知しなければなりません(労働基準法106条1項)。
内容を閲覧できる状態にしておく必要があります。
就業規則の周知義務が規定されているのは、従業員が職場におけるルールを把握できるようにするためです。
ルールを労使間で共有することで、ルールを遵守させトラブルを予防する意味があります。
懲戒理由や処分内容の明示により、不正防止の効果も期待できるでしょう。
いくら立派な就業規則を作成しても、従業員が内容を把握していないと意味がありません。
周知は、就業規則に実効性を持たせるために重要です。具体的な周知方法については後述します。
全従業員が対象
周知は、適用されるすべての従業員を対象に行ってください。
適用される従業員が全員把握することにより、就業規則が実効的なものとなります。
正社員はもちろん、契約社員、パート、アルバイトに対しても周知が必要です。
もっとも、派遣労働者や業務委託契約により働いている労働者には周知する必要がありません。
10人未満でも作成したら周知が必要
各事業場(営業所・支店など)において常時雇用している労働者が10人未満の場合、法律上は就業規則の作成・届出義務(労働基準法89条)はありません。
ただし、義務ではないだけで、統一ルールを定めるために就業規則を作成することは可能です。
就業規則を作成したのであれば、対象者が10人未満であっても周知しなければなりません。
人数が少ないとしても、ルールを定めた以上は把握させる必要があるためです。
規模の小さい職場であっても、周知は欠かさないようにしてください。
参考記事:就業規則に関する4つの義務|10人未満でも作成すべき理由
就業規則の周知方法

弁護士
岡本 裕明
見やすい場所に掲示する・備え付ける
就業規則の周知方法としては、法令上3つの方法が定められています(労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2)。
1つ目は「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける」方法です(労働基準法施行規則52条の2第1号)。
印刷して掲示する、あるいは冊子にして置いておく方法になります。
掲示・備え付けをしておくのは、自由に行き来ができ従業員が誰でも閲覧できる場所にしましょう。
たとえば、事務所の掲示板、休憩室、給湯室などが考えられます。
複数の事業場(営業所・支店など)があるのであれば、それぞれに掲示・備え付けしておかなければなりません。
すべての従業員が「見ようと思えばすぐに見られる」状態にしておく必要があります。
就業規則に変更があった際には、速やかに新しいものに更新するようにしましょう。
書面を従業員に交付する
2つ目は「書面を労働者に交付する」方法です(労働基準法施行規則52条の2第2号)。
印刷して従業員一人ひとりに渡す方法になります。
全員に渡すため、印刷コストや手間を要します。渡し忘れがないように注意しなければなりません。
また、書面を社外に持ち出され、機密情報が漏えいするリスクも高いです。
社外への持ち出しを禁じる規定を置くなど、対策をとる必要があります。
データを閲覧できる状態にする
3つ目は「使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は(中略)電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する」方法です(労働基準法施行規則52条の2第3号)。
わかりづらい定めですが、簡単に言えばデータ化してPCで閲覧できるようにしておくということです。
一般的なのは、社内システムなどでデータを共有しておく方法になります。
従業員が多くても対応しやすい、変更時の修正が容易である、テレワーク中にも確認できるといったメリットがあります。
従業員が誰でも閲覧しやすいように、わかりやすいフォルダに保存しておきましょう。
情報漏えいリスクに対応する観点からは、ダウンロードや印刷に制限をかけておくのが有効です。
周知したとは認められないケース
上記3つの方法以外では、周知したとは認められません。
たとえば、口頭で説明しただけのケースです。
また、一部の従業員しか内容を閲覧できないのであれば、周知したとは認められません。
書面を交付する方法をとった際に交付を忘れる、データにパスワードをかけていて一部の従業員しか開けないといった事態は避けてください。
就業規則を周知しないリスク

弁護士
岡本 裕明
労働基準監督署の是正勧告の対象となる
就業規則の周知は法的義務です。
周知を怠ると労働基準法違反となり、労働基準監督署による是正勧告の対象になり得ます。
是正勧告がなされた際には、早急に改善・報告をしなければなりません。
労働基準監督署の是正勧告について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考記事:労働基準監督署の是正勧告を受けたら?対処法を弁護士が解説
罰則を科される
周知義務違反には罰則も規定されています。
刑罰の内容は「30万円以下の罰金」です(労働基準法120条1号)。
いきなり罰則を科される可能性は低いものの、労働基準監督署の指導・勧告を無視すれば刑事処分の可能性もあります。
万が一刑罰を科されたことが明るみになれば、社会的なイメージの低下は避けられません。
無効とされる
周知しないと、作成・変更した就業規則の効力が否定されてしまいます。
就業規則には労働条件を定める効果がありますが、効果を生じさせるための要件のひとつが周知です(労働契約法7条)。
また、就業規則を従業員に不利益に変更する際にも、効力を生じさせるには合理性のほかに周知が必要とされています(労働契約法10条)。
労働者に対して就業規則の内容を知り得る状態に置いていないときには、無効とされてしまいます。
実際に無効とされたケースが中部カラー事件です。
【事案の概要】
資産運用利率の低下のため、被告会社は適格年金制度を維持できなくなり、制度を変更した。
会社は朝礼で制度変更の概要を説明し、従業員の同意書を取得した。
変更後の就業規則は休憩室に掲示されていた。
結果として退職金が減額されたところ、原告(元従業員)が変更の無効を主張した。
【結論】
実質的な周知がなく変更は効力を有しない。
【ポイント】
裁判所が周知がなされていないと判断した理由としては、以下が挙げられます。
・朝礼での説明は不十分だった
・変更後の退職金の計算を可能にする資料の掲示はなかった
従業員が内容を把握できるようにしておかないと、就業規則の効力が否定されるおそれがあります。注意しましょう。
就業規則の効力について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考記事:就業規則の効力|発生要件は?いつから発生する?会社側弁護士が解説
従業員に浸透しない
法的な問題だけでなく、従業員にルールが浸透しない点もリスクです。
周知が不十分で従業員が就業規則のルールを把握できないと、社内秩序が乱れトラブルが起きやすくなります。
何が処分対象かわからず、不正行為が発生する可能性もあるでしょう。
就業規則の周知が求められるのは、従業員が内容を把握するためです。
作成・変更しただけで満足しないようにしてください。
就業規則の周知に関する疑問は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、就業規則の周知について、必要となる理由、方法、怠るリスクなどを解説してきました。
周知が不十分だと、処分対象になるだけでなく、効力が否定される、職場にルールが浸透しないといった問題が生じます。
トラブルを防止するために、就業規則は正しい方法で周知しましょう。
就業規則を作成・変更しようとしている方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
- Q.就業規則を従業員に周知する法的義務は何ですか?
- A.労働基準法106条1項により、作成・変更した就業規則を従業員に周知し、閲覧できる状態にしておく義務があります。
- Q.就業規則を周知するための許容される方法は何ですか?
- A.掲示・備え付け、書面の交付、データ共有(PC等で閲覧可能にする)の3つが法令上認められています。
- Q.従業員数が10人未満でも周知義務はありますか?
- A.はい。規則作成の義務自体はありませんが、作成した場合は10人未満でも従業員全員に周知する必要があります。
- Q.就業規則を適切に周知しないとどんなリスクがありますか?
- A.法令違反となり、労働基準監督署の是正勧告や30万円以下の罰金、さらに規則自体が無効とされる恐れがあります。
- Q.従業員が就業規則を簡単に確認できないと何が起こりますか?
- A.社内秩序の乱れやトラブルが増え、処分対象を把握できないため不正行為が起きやすくなります。
ご相談いただければ、周知を含めて、就業規則の作成・変更方法についてアドバイスいたします。
「就業規則はどう周知すればいいのか」とお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。