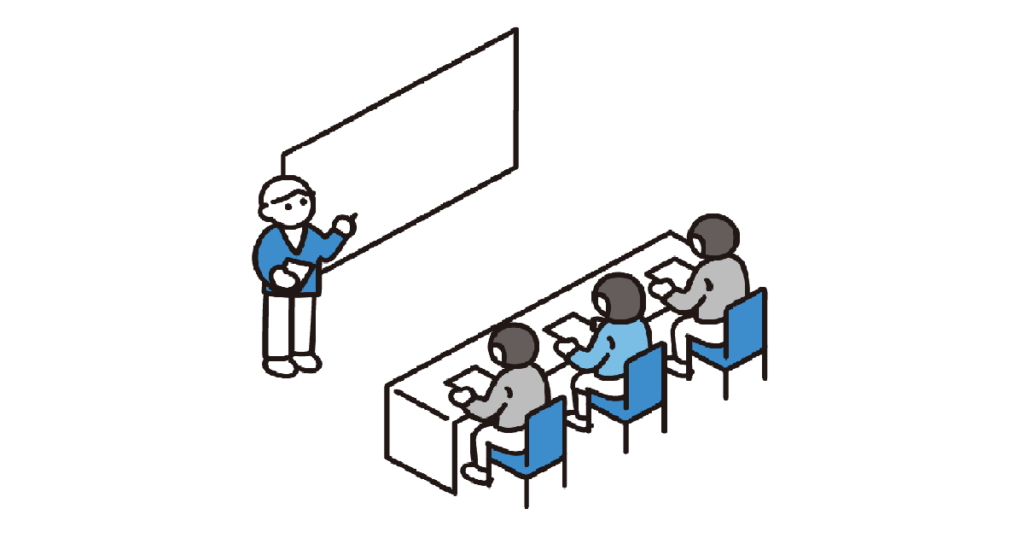お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
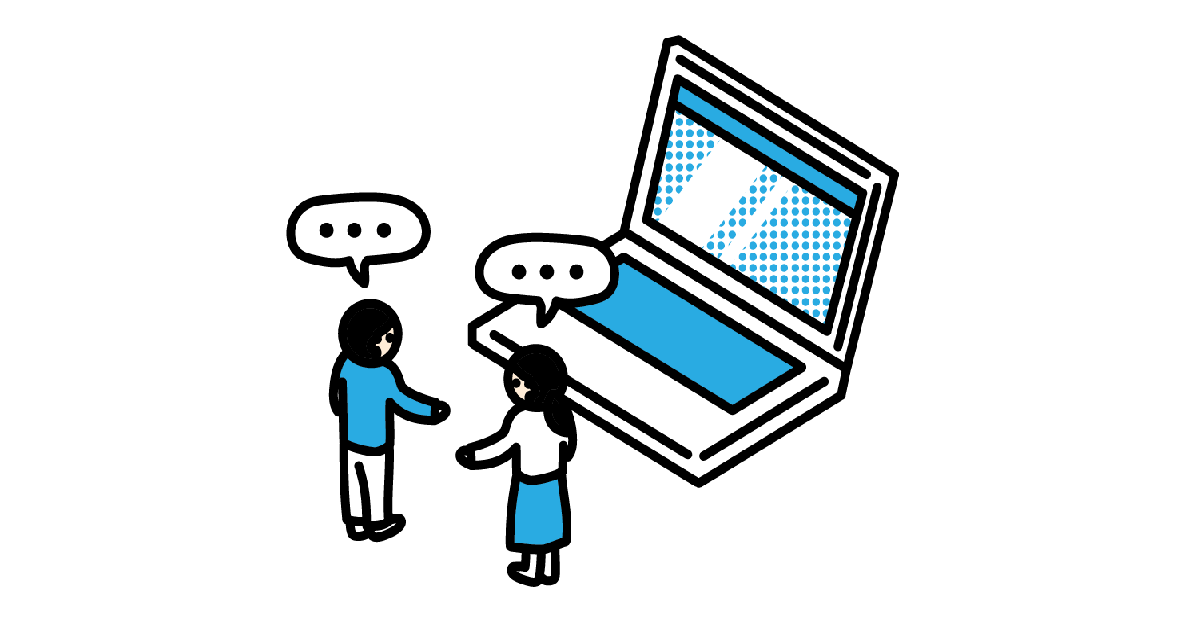
就業規則は、法令改正や会社をめぐる環境の変化に伴って変更が必要になる場合があります。
変更に際しては、作成時と同様に、従業員代表への意見聴取、労働基準監督署への届出、従業員への周知といった手続きを踏まなければなりません。
社員にとって不利益な変更も可能ではあるものの、法的ハードルは高いです。
今回は、就業規則の変更方法や不利益変更の有効性などを解説しています。
就業規則の変更を検討している会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
就業規則に関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:就業規則とは?効力や記載事項、作成・変更方法を弁護士が解説
就業規則の変更が必要になる理由

弁護士
岡本 裕明
法令が改正された
労働関係の法令が改正されたために、就業規則を法令に適合するように変更すべきケースがあります。
法令を遵守するために不可欠な変更であれば、早急に進めなければなりません。
近年では、育児介護休業法の改正や、月60時間超の時間外労働における割増率引き上げの中小企業への適用拡大などが挙げられます。
最低賃金の引き上げに伴い、就業規則の変更が必要になる場合もあるでしょう。
法令改正によりルールが導入・変更された際には、会社の方針にかかわらず就業規則に反映させる必要があります。
勤務形態を見直したい
社会情勢や社内環境の変化に伴って、勤務形態を見直すべき必要性が生じる場合もあります。
たとえば、働き方の多様性を確保するために、フレックス制、在宅勤務といった新たな制度を導入するケースです。
就業規則が実態にそぐわなくなり、始業・終業時刻や労働時間などを変更する場合もあるでしょう。
就業規則はただ作成するだけでなく、状況の変化に応じて変更していかなければならないのです。
賃金体系を変更したい
賃金体系や手当を変更したいケースもあるでしょう。
たとえば、従業員のモチベーションを上げるために、年功序列から能力主義の賃金体系に変更したり、新たな手当を導入したりする場合です。
前向きなものだけでなく、業績悪化を理由に手当の廃止・減額や賃金の引き下げをせざるを得ないケースもあります。
もっとも、賃金体系の変更により不利益を被る従業員が出る場合には、法的なハードルが高いです。
就業規則の不利益変更について詳しくは後述します。
就業規則の変更手順

弁護士
岡本 裕明
参考記事:就業規則の作成方法|流れや注意点を弁護士が解説
変更案を作成する
まずは、変更部分について条項案を作成します。
関連する条項をピックアップし、どう変更すればよいかを検討しましょう。
漠然と文言を考えるのではなく、何のために変更するのかを明確にしたうえで、変更の影響を考えつつ内容や定め方を検討するようにしてください。
後述する通り、従業員にとって不利益な変更であれば法的ハードルが上がります。
不利益変更に該当しないかを確認するのも重要です。
従業員代表に意見を聴く
作成時と同様に、変更時にも従業員の意見を聴かなければなりません。
すなわち「労働者の過半数で組織する労働組合」あるいは「労働者の過半数を代表する者」の意見を聴くことが義務とされています(労働基準法90条1項)。
「労働者の過半数を代表する者」とは、選出の目的を明らかにしたうえで、投票や挙手などの方法で選出された代表を意味します(労働基準法施行規則6条の2)。
管理監督者(労働基準法41条2号)は代表者となれません。
変更内容に関して意見を聴けばいいのであり、同意を得る義務まではありません。
とはいえ、丁寧な説明をして理解を得る努力をするべきです。
労働基準監督署に変更届や意見書を提出する
意見聴取をしたら、労働基準監督署に変更届を提出しなければなりません(労働基準法89条)。
同時に従業員代表の意見書を提出するのも義務です(労働基準法90条2項)。
届出は、事業場(営業所・支店など)ごとに、管轄する労働基準監督署に対して行います。
内容が同じであれば、本社所在地での一括の届出も可能です。
従業員に周知する
変更した就業規則は従業員に周知しなければなりません(労働基準法106条1項)。
周知の方法としては以下が挙げられます。
・作業場の見やすい場所に掲示する
・冊子にして備え付ける
・印刷した書面を交付する
・社内システムから閲覧できるようにする
従業員の誰もが変更内容を確認できるようにしておきましょう。
参考記事:就業規則の周知方法|義務違反のリスクも解説
同意なく従業員にとって不利益な変更はできる?

弁護士
岡本 裕明
合理性が認められれば可能
原則として、労働者との合意なく、就業規則の変更により労働者にとって不利益になるように労働条件を変更することはできません(労働契約法9条本文)。
ただし、変更が合理的であるときは不利益な変更も可能です(労働契約法9条ただし書、10条本文)。
変更が合理的であるかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
・労働者が受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合との交渉状況
・その他就業規則の変更に係る事情
これらの事情に照らして変更が合理的であると認められるときは、変更後の就業規則を周知させることにより、従業員にとって不利益であっても労働条件を変更できます。
就業規則の不利益変更に関する判例
上記の判断要素は、過去の判例をもとに条文に明示したものです。
代表的な判例として第四銀行事件とみちのく銀行事件をご紹介します。
【事案の概要】
被告(銀行)において、就業規則の変更により、55歳から60歳への定年延長と、55歳以上の労働条件が定められた。
変更前でも58歳までは定年後在職制度の利用により勤務が可能であったが、制度変更により55歳以降の賃金が54歳時の約63%〜67%にまで引き下げられ、同じ賃金を得るには60歳近くまで働く必要が生じた。
【結論】
就業規則の変更は合理的であり有効。
【ポイント】
賃金は労働者にとって重要な労働条件であるため、高度の必要性に基づいた合理的な内容でなければならないとしたうえで、結論としては有効と判断されました。
理由としては以下が挙げられています。
・60歳定年制の実現が国家的な政策課題とされていた
・人件費の負担増加に対応するために55歳以降の賃金水準を変更する必要があった
・変更後の内容でも、他行や社会一般の賃金水準と比較してかなり高額であった
・福利厚生制度の適用延長や拡充等の措置がとられ不利益が緩和されていた
・行員の約90%で組織される労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結したうえで行われた
みちのく銀行事件も似た事案ですが、結論としては無効と判断されています。
【事案の概要】
被告(銀行)では既に60歳定年制を採用していたが、就業規則の変更により55歳以上の賃金が平均値で約33%〜46%削減された。
【結論】
就業規則の変更は無効。
【ポイント】
行員の高齢化が進行しており賃金の抑制を図る必要性があるとしつつも、以下の理由を挙げて無効と判断されました。
・ほぼ同じ職務を担当するのに賃金の削減幅が大きい
・代償措置は不十分
・高年層の事務職員として、変更後の賃金水準が高いものとはいえない
・中堅層の賃金は改善する内容であり全体の人件費は上昇している
第四銀行事件と判断が異なった理由としては、もとから60歳が定年であった、高齢層にだけしわ寄せがいく内容であった、といった点が考えられます。
就業規則の不利益変更が合理的なものであるかは、一見似た事例でも判断が分かれており、ケースバイケースといえます。
自社の場合にいかに判断されるかを知りたければ、専門家への相談がオススメです。
とりわけ賃金や退職金の引き下げはハードルが高いとされているので、ご注意ください。
就業規則の変更は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、就業規則の変更について、手続きや不利益変更の有効性などを解説してきました。
就業規則を変更する際には、作成時と同様の手続きが必要です。
特に不利益変更に該当する場合には、法的に許されるかを慎重に検討しましょう。
就業規則を変更しようとしている方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
ご相談いただければ、就業規則の変更方法についてアドバイスいたします。
不利益変更に該当するかの判断はもちろん、既にトラブルになっている場合の対応も可能です。
「就業規則はどう変更すればいいか」「従業員に不利益が生じる変更はできるのか」とお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.就業規則を変更する必要があるケースは何ですか?
- A.法令改正や勤務形態・賃金体系の見直しなど、会社環境が変わったときに必要です。
- Q.変更手続きの基本的な流れは?
- A.原案作成→従業員代表への意見聴取→労働基準監督署への届出・意見書提出→従業員への周知の順で進めます。
- Q.従業員代表に意見を聴く義務はありますか?
- A.はい、労働基準法90条1項により、過半数の従業員を代表する者から意見聴取が義務付けられています。
- Q.従業員に不利益な変更は可能ですか?
- A.原則不可ですが、合理性が認められれば変更できます。判断基準は不利益の程度・必要性・相当性などです。
- Q.判例で示された不利益変更の有効性はどんな条件が重要ですか?
- A.第四銀行事件では合理的と判断されましたが、みちのく銀行事件では無効と。重要なのは賃金削減幅、代償措置の有無、労働組合との協議などです。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。