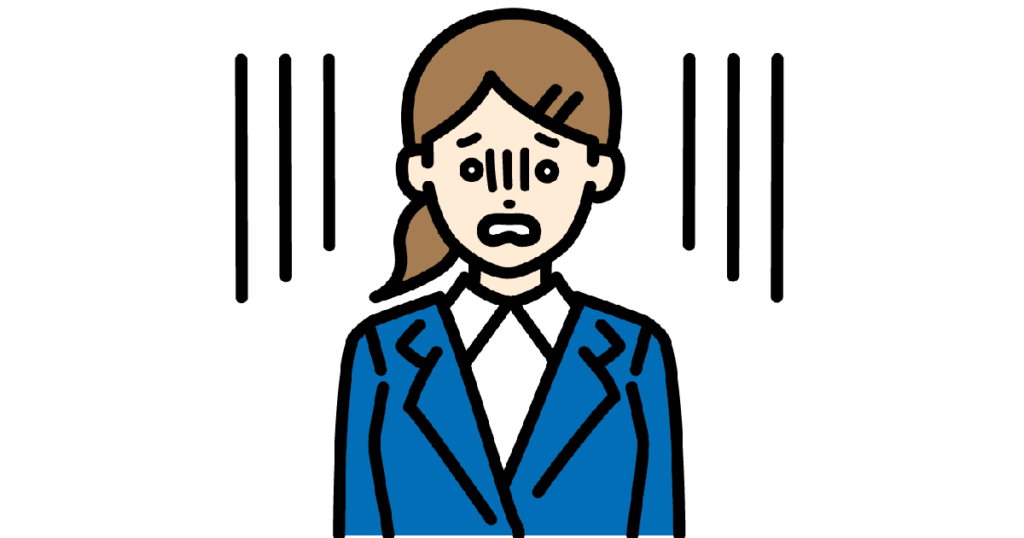お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

セクハラを受けた被害者が、加害者本人だけでなく、会社にも慰謝料を請求してくるケースはよくあります。
実際に、会社に賠償責任が認められる事例も多いです。
セクハラの慰謝料相場は数十万円から300万円程度です。
金額は、セクハラ行為の内容や被害者に与えた影響等により変わります。
請求を受けた際には、事実を確認したうえで誠実に対応しなければなりません。
今回は、セクハラの慰謝料相場や実際の事例、請求された会社の対応などについて解説しています。
セクハラが発生した会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
セクハラに関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:セクハラ・パワハラとは?会社が負う責任やとるべき対策を解説
慰謝料の対象になるセクハラとは?

弁護士
岡本 裕明
セクハラとは、職場で行われる、相手方の意思に反する性的な言動です。
例としては以下が挙げられます。
・昇進の対価として性行為に応じさせる
・性的な発言をして職場環境を害する
・必要がないのに身体に触れる
・断られているのにデートに執拗に誘う
「男性から女性」だけでなく、男性が被害者となるセクハラや、同性間でのセクハラも存在します。
セクハラの判断基準について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考記事:セクハラはどこから?判断基準や裁判例を弁護士が解説
セクハラ慰謝料は会社にも請求される!

弁護士
岡本 裕明
実は、加害者本人だけでなく、会社にも法的責任が生じます。会社も被害者から慰謝料を請求され得るということです。請求の法的根拠としては「使用者責任」や「職場環境配慮義務違反」が挙げられます。
使用者責任
セクハラで会社が賠償義務を負う理由として、まずは「使用者責任」が挙げられます(民法715条)。
使用者責任とは、雇われている人が事業の執行にあたって他者に損害を与えたときに、会社が負う賠償責任です。
職務に際して行われたセクハラにより従業員に損害賠償義務が生じた際には、会社も賠償責任を負います。
職場での業務時間中だけでなく、業務の延長として行われる宴会などで行われたセクハラについても、職務関連性が認められ、会社が責任を負います。
使用者責任を根拠とする請求に会社が反論するのは難しいです。
職場環境配慮義務違反
使用者責任とは別に、会社は従業員に対して「働きやすい職場環境を維持する義務」を負っています。
会社は、セクハラをしてはならない旨の周知啓発、相談窓口の設置、発生後の適切な対応などを行わなければなりません。
セクハラへの対策・対応が不十分だと、職場環境配慮義務を果たしていないとして、債務不履行(民法415条)あるいは不法行為(民法709条)を根拠として会社に責任が生じるおそれがあります。
加害者本人の責任を前提とする使用者責任に対して、職場環境配慮義務違反は、会社が直接負う責任です。
被害者は、いずれを根拠として請求してもよく、両方を主張しても構いません。
会社がとるべきセクハラ対策については、以下で解説しています。
参考記事:セクハラとは?定義・種類・会社がとるべき対策を解説
セクハラの慰謝料相場

弁護士
岡本 裕明
数十万円から300万円が一般的
過去の裁判例からすると、セクハラの慰謝料相場は、数十万円から300万円程度になります。
程度が軽いときには10万円以下、著しく悪質なときは300万円超となり得ますが、大半のケースでは数十万円から300万円程度です。
慰謝料額を左右する要素
一応の相場があるとはいえ、個々のケースで認められる慰謝料額は千差万別です。
慰謝料額を左右する要素としては、以下が挙げられます。
行為の悪質さ
実際に行われたセクハラ行為そのものの悪質性は、慰謝料額に影響を与えます。
影響が大きいのは身体接触の有無です。
性的な発言があったのみで身体接触がないときには、慰謝料は低くなります。
身体接触があると賠償額が上がり、特に不同意わいせつ罪・不同意性交等罪といった重大犯罪に該当するときは高額になりやすいです。
期間・頻度・回数
行為が継続した期間・頻度・回数も慰謝料額を左右します。
長期間・高頻度・多数回であれば、金額は高くなりやすいです。
休職・退職や精神疾患の有無
被害者にもたらした結果も重要です。
セクハラにより休職・退職に追い込まれたときは、高額になります。
セクハラが原因でうつ病などの精神疾患を発症したときも同様です。
仕事ができなくなると、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償金)だけでなく、休業損害や逸失利益も発生するため、賠償総額が増加する傾向にあります。
参考記事:うつ病は労災認定される?認定基準や会社の対応を弁護士が解説
セクハラで慰謝料が認められた事例

弁護士
岡本 裕明
まずは、性的発言のみで身体接触がなかったケースです。
【事案の概要】
被告会社の従業員からセクハラ発言を受けたことを理由に、被害者である原告(別の従業員)が、使用者責任に基づく損害賠償を請求した。加害者の従業員は性的発言を繰り返し、原告に苦情を申立てられると、かつて原告につきまといしていた者の名前を挙げ、その者に連絡を取るかのような発言をした。
【結論】
セクハラ発言について、20万円の慰謝料支払いを命じた。
【ポイント】
性的な発言を繰り返したものの、身体接触はしていなかったため、慰謝料は低額になりました。
次に紹介するのは、異性関係に関する噂を流したケースです。
【事案の概要】
原告は、上司から、異性関係が派手である旨の噂を流されるなどの嫌がらせを受けた。会社は、原告に対して話し合いがつかなければ退社してもらう旨を述べ、原告は退社の意思を示した。原告は、加害者本人と会社に対して損害賠償を請求した。
【結論】
加害者本人と会社の責任を認め、150万円の慰謝料と15万円の弁護士費用の支払いを命じた。
【ポイント】
原告に退職を求めたのに対し、加害者には3日間の自宅謹慎と賞与の減額を命じただけであったため、会社として職場環境を調整するよう配慮する義務を怠ったとされ、責任が認められました。事後的な対応の誤りが特に問題視されています。
最後に、高額な賠償金が認められたケースをご紹介します。
【事案の概要】
原告の従業員は、会社の代表取締役から身体接触や性交渉の強要などのセクハラを繰り返し受け、退職に追い込まれた。代表取締役と会社に対して損害賠償請求をした。
【結論】
慰謝料300万円と弁護士費用30万円の支払いを命じた。
【ポイント】
性的な言動を繰り返した挙げ句、性交渉にまで及び、退職を余儀なくさせているため、高額の慰謝料が認められました。す
以上の通り、ケースによって慰謝料額は大きく異なります。
セクハラで慰謝料を請求された会社がとるべき対応

弁護士
岡本 裕明
事実確認
いまだ事実関係を十分に把握していない状態であれば、まずは確認が必要です。
セクハラの有無や内容がわからない限り、適切な対応はできません。
調査では、当事者からの聴き取りだけでなく、関係者への事情聴取、客観的な証拠の収集も行ってください。
加害者の処分
事実関係が明らかになり、セクハラの事実が確定したら、加害者への処分を検討します。
加害者への適切な処分は、会社に課された義務の一環です。
もちろん軽すぎる処分ではいけませんが、行為に対して重すぎる処分をすると、加害者から無効を主張されるおそれがあります。
処分内容は慎重に検討してください。
主張の検討
請求を受けている以上、内容を確認したうえで主張を検討しなければなりません。
被害者の主張が事実と認められるのであれば、損害賠償が発生することを前提に、行為態様等から慰謝料額が適切かを判断します。
セクハラの事実がないのであれば、慰謝料を支払わない旨の反論を行います。
いずれにしても、請求を軽視せず、誠実に対応するようにしてください。
セクハラで慰謝料を請求された会社は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、セクハラの慰謝料について、法的根拠や金額の相場、会社がとるべき対応などを解説してきました。
セクハラが発生した際には、使用者責任や職場環境配慮義務違反を理由として、会社にも損害賠償責任が生じる可能性があります。
事実を調査したうえで、行為態様などから慰謝料額の相場を判断し、対応を検討しなければなりません。
セクハラで慰謝料を請求された会社関係者の方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
事実関係に誤りはないか、請求額が相場に比して過大ではないかなど、被害者の請求内容を吟味したうえで適切な対応をいたします。
「会社にセクハラへの責任が生じるのか」「請求された慰謝料額は妥当なのか」などと疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
- Q.セクハラ被害者が会社に慰謝料を請求できる理由は何ですか?
- A.会社は「使用者責任」や「職場環境配慮義務違反」により、従業員が被害を受けた場合に賠償責任を負うためです。
- Q.セクハラ慰謝料の相場はどのくらいですか?
- A.一般的には数十万円から300万円程度で、行為の悪質さや期間・影響によって変動します。
- Q.何が慰謝料額を大きく左右する要因ですか?
- A.行為の悪質さ(身体接触有無)、期間・頻度、休職・退職や精神疾患の発症などが主要な要因です。
- Q.会社が慰謝料請求を受けた際に取るべき初期対応は?
- A.まず事実確認を徹底し、証拠収集・関係者聴取を行い、加害者の処分や適切な対応策を検討します。
- Q.会社が慰謝料請求に対してどのように対応すべきですか?
- A.被害者の主張を真摯に検討し、損害賠償が認められる場合は適正な慰謝料額を算定し、必要に応じて弁護士へ相談します。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。