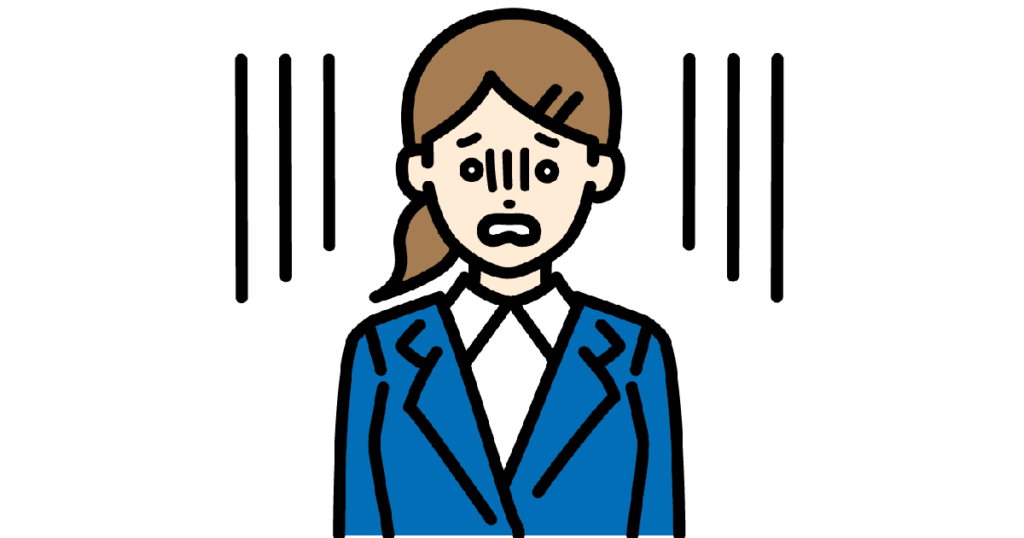お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
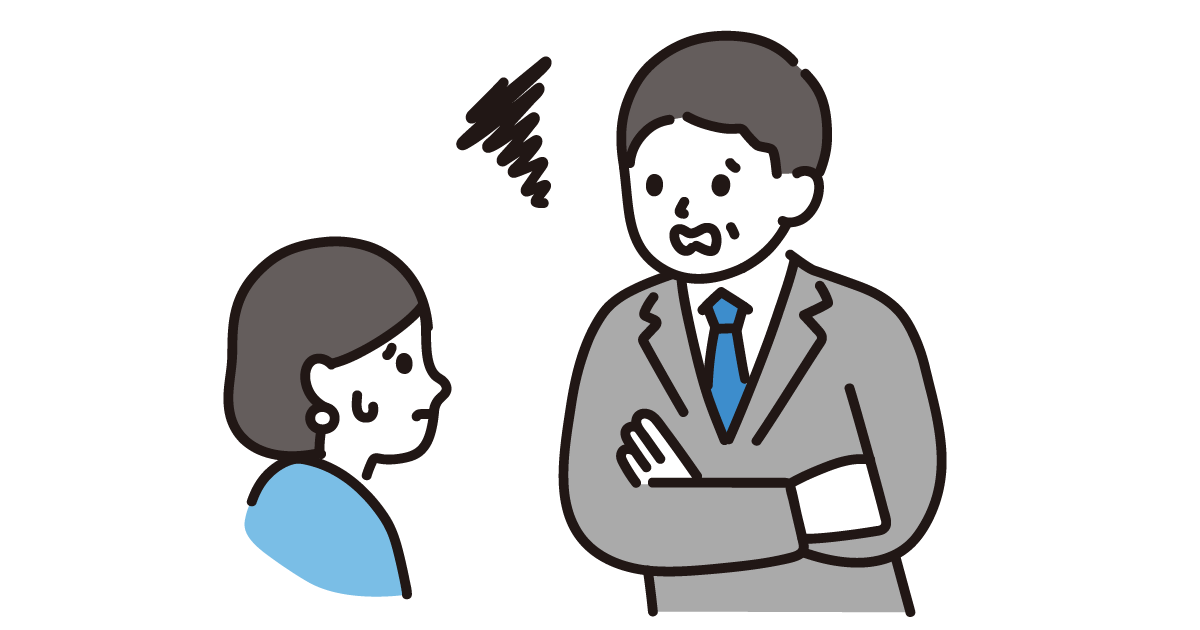
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場における上下関係などを利用して、業務上の適正範囲を超えて精神的・肉体的に苦痛を与える行為をいいます。
暴行・暴言のほか、仲間外れにする、過大なノルマを課す、仕事を与えないといった行為もパワハラに該当します。
パワハラが発生すると、職場の雰囲気が悪くなるだけでなく、損害賠償請求やイメージダウンのリスクも高いです。
企業としては、十分な事前対策をとったうえで、発生時には適切に対応しなければなりません。
今回は、パワハラの定義・類型や、会社に生じるリスク、適切な対応などについて解説しています。
パワハラへの対応を検討している会社経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
ハラスメントに関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:セクハラ・パワハラとは?会社が負う責任やとるべき対策を解説
パワハラの定義

弁護士
岡本 裕明
法律上、職場におけるパワハラは、
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えている
③労働者の就業環境が害される
という、3つの要件をすべて満たしたものをいいます(労働施策総合推進法30条の2第1項)。
パワハラの3つの要件につき、順に見ていきましょう。
以下参考:職場におけるハラスメント対策パンフレット|厚生労働省
優越的な関係を背景とした言動
まずは、「職場」における「優越的な関係を背景とした」言動であることが要件とされています。
「職場」には、普段仕事をしている事務所や工場などだけでなく、業務をする場所全般が含まれます。
出張先、移動中の車内、打ち合わせする取引先なども「職場」です。強制参加の宴会など、仕事の延長といえる場も職場に該当します。
「優越的な関係を背景とした」言動とは、被害者が抵抗・拒絶するのが難しい関係を背景にして行われるものです。
「上司と部下」「先輩と後輩」といった上下関係がある場合だけでなく、次の場合も含まれます。
・経験豊富な同僚や部下の協力が不可欠である状況を利用した言動
・同僚や部下が集団となって行う言動
上司だけでなく、同僚や部下からの言動もパワハラになり得ます。
業務上必要かつ相当な範囲を超えている
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会常識から見て明らかに業務上必要のない行為、あるいは必要であっても方法が不適切な行為です。
業務にあたって、ある程度厳しい注意・指導が必要な場合も当然あるでしょう。
「業務上必要かつ相当」かどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断します。
・行為の目的
・行為に至った経緯・状況(受けた側の問題行動の有無や内容・程度を含む)
・業種・業態
・業務の内容・性質
・行為の態様・頻度・継続性
・労働者の属性(経験年数、年齢、障害がある、外国人であるなど)
・労働者の心身の状況(精神的・肉体的な状況、病気の有無など)
・当事者の関係性
たとえば、危険を伴う作業中に事故を招きかねない不注意があった際には、多少厳しい言葉での指導が認められやすいでしょう。
とはいえ、人格否定にまで及べばパワハラになってしまいます。
「業務上必要かつ相当」かどうかは、個々の状況に応じてケースバイケースです。
一概に「〇〇をすればパワハラ」とは断定できません。
労働者の就業環境が害される
「労働者」には、正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなども含まれます。
「就業環境が害される」とは、言動により身体的・精神的な苦痛を与えられ、業務の際に能力が発揮できないなど、見過ごせないほどの支障が生じることです。
就業環境が害されたといえるかは、平均的な労働者の感じ方を基準にして判断します。
被害を受けたとする従業員が「苦痛を感じたからパワハラだ」と主張していても、必ずしもパワハラに該当するとは限りません。
パワハラの6類型

弁護士
岡本 裕明
身体的な攻撃
身体的な攻撃とは、暴行・傷害です。殴る・蹴るといった直接の暴行だけでなく、物を投げつける行為も該当します。
暴行は目に見えるものであり、傷跡などの証拠も残りやすいため、比較的わかりやすいパワハラといえるでしょう。
精神的な攻撃
精神的な攻撃とは、脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言といった行為です。
例としては以下が挙げられます。
・人格を否定する発言(例:「生きてる価値がない」「使えねえな」)
・他の従業員がいる場所で大声で叱責する
・必要以上に長時間にわたって叱責を繰り返す
業務上の問題行為に対して、適切な言葉・方法で注意・指導するのはパワハラには該当しません。
特に問題行動が深刻であれば、多少強い言葉での指導も認められます。
ただし、人格否定に及ぶ発言や、必要以上にダメージを与えるような場所・方法での叱責はしてはなりません。
人間関係からの切り離し
仲間外れや無視といった、人間関係からの切り離しも許されません。
たとえば、長期間別室に隔離する、集団で無視するといった行為は、パワハラに該当します。
研修等の合理的な理由で、一時的に別室に居させるのは構いません。
過大な要求
達成できないことを求める、明らかに必要のない業務をさせるのもパワハラです。
達成困難なノルマを課す、業務と一切関係のない雑用をさせる、新卒者に教育をせずに遂行不可能な業務を命じるといった例が挙げられます。
過小な要求
能力や経験に比してあまりに程度の低い業務を命じる、仕事を与えないといったこともパワハラになります。
退職させるために「追い出し部屋」に追い込むようなケースです。
参考記事:退職勧奨が違法になるケース|仕事を与えないなど強引な方法はNG!
個の侵害
プライベートに過度に立ち入ることもパワハラになり得ます。
職場外でも監視する、個人情報を暴露するといった例が挙げられます。
パワハラによる会社へのリスク

弁護士
岡本 裕明
職場環境が悪化する
定義にもあるように、パワハラは就業環境を害する行為です。
発生すると職場の雰囲気が悪くなってしまいます。
被害者が退職するおそれがあるほか、その他の従業員も、パワハラが横行する会社に見切りをつける可能性があります。
生産性低下や業績悪化といった影響が生じるケースもあるでしょう。
損害賠償を請求される
被害者から会社に損害賠償請求がなされるリスクも高いです。
加害者本人に法的責任が生じるのは当然として、会社も、使用者責任や職場環境配慮義務違反を根拠として賠償を請求され得ます。
特に被害者がうつ病になる、自殺に至るといった深刻な結果が生じれば、多額の賠償金が発生します。
参考記事:パワハラの慰謝料相場|事例や会社がとるべき対応を解説
社会的イメージが低下する
パワハラが発生すると、会社への社会的なイメージが低下する可能性もあります。
現代は、SNSを通じて簡単に情報が拡散される時代です。
ひとたびパワハラが発生すると、被害者自身や他の従業員の投稿により、事実が世間に知られてしまうかもしれません。
会社へのイメージが低下すると、売上減少や採用難といった影響が生じ得ます。
企業がとるべきパワハラ対策

弁護士
岡本 裕明
企業がとるべきパワハラ対策の例としては、以下が挙げられます。
・パワハラをしてはならない旨の方針の周知・啓発(研修など)
・相談窓口の設置
・事後対応(事実確認、加害者への処分、再発防止策など)
企業にパワハラ防止措置を義務づけた、いわゆる「パワハラ防止法」は、中小企業にも適用が拡大されています。
企業規模にかかわらず、対策をとるようにしましょう。
パワハラ対策について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:パワーハラスメント防止法の内容|パワハラ防止措置はどうする?
パワハラへの対応は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、パワハラの定義や類型、会社に生じるリスクや対策などを解説してきました。
パワハラは、優越的な関係を背景に、業務上の適正範囲を超えて肉体的・精神的に苦痛を与え、勤務環境を害する行為です。
発生した会社には、損害賠償だけでなく、人材流出や業績悪化も生じ得ます。
事前に対策をとったうえで、発生した際には迅速かつ適切に対応しなければなりません。
社内でのパワハラについてお悩みの会社関係者の方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
パワハラの事前対策だけでなく、発生後も事実確認から被害者との交渉・訴訟、加害者の処分などにつき徹底的にサポートいたします。
「従業員がパワハラ被害を主張している」「加害者にいかなる処分をすればいいかわからない」などとお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
- Q.パワハラとは何ですか?
- A.職場で優越関係を利用し、業務上必要・相当な範囲を超えて精神的・肉体的苦痛を与える行為です。
- Q.パワハラの法的要件は何ですか?
- A.①優越的関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えること、③労働者の就業環境が害されるという3要件を満たす必要があります。
- Q.代表的なパワハラの6類型は何ですか?
- A.身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個人情報侵害の6類型があります。
- Q.パワハラが発生した場合、会社にどんなリスクがありますか?
- A.職場環境の悪化・生産性低下、損害賠償請求、社会的イメージ低下などが生じます。
- Q.会社はパワハラを防止・対処するために何をすべきですか?
- A.方針の周知・研修、相談窓口設置、事後対応(確認・処分・再発防止策)を実施し、法的義務に従うべきです。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。