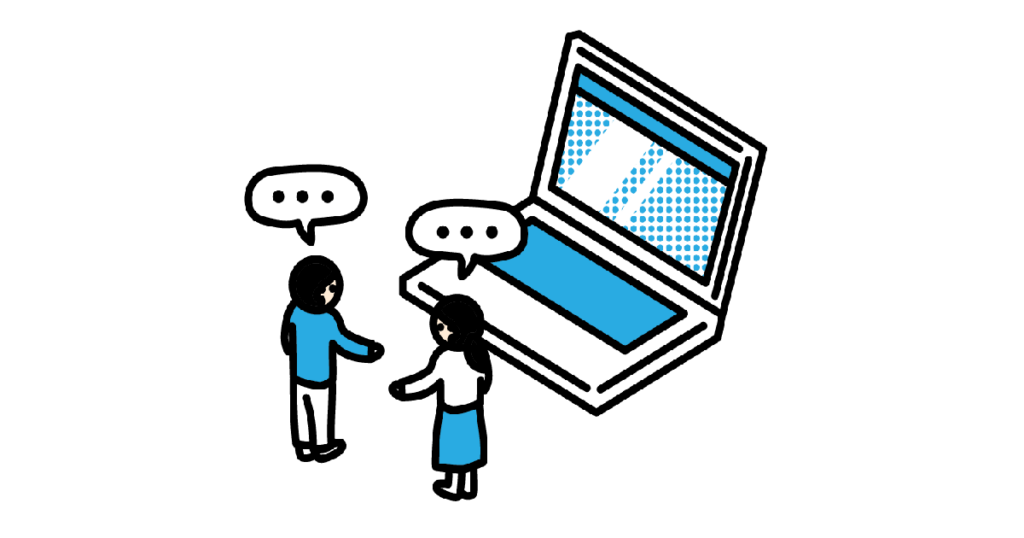お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

「就業規則に何を記載すればいいのか」とお悩みではないですか?
就業規則に必ず記載しなければならない事項は、法律で定められています。
たとえば、労働時間、賃金、退職などについては記載が必須です。
記載していないと違法になってしまうため、漏れがないようにしなければなりません。
今回は、就業規則の記載事項を解説しています。
就業規則の作成を予定している会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
就業規則に関する全般的な基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:就業規則とは?効力や記載事項、作成・変更方法を弁護士が解説
就業規則の記載事項の種類

弁護士
岡本 裕明
就業規則の記載事項には、絶対に書かなければならない「絶対的必要記載事項」、制度を設けるときに記載する「相対的必要記載事項」、企業が自由に定める「任意的記載事項」があります。
絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項とは、いかなる会社でも就業規則に必ず記載しなければならない項目です。
具体的には、労働基準法89条1〜3号に定められています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
これらの事項を記載していない場合、就業規則の作成義務を守っていないことになります。
労働基準監督署の指導・是正勧告の対象になり得るほか、「30万円以下の罰金」という罰則も定められています(労働基準法120条1号)。
絶対的必要記載事項は、どんな会社でも必ず就業規則に記載しなければなりません。
詳しい内容は後述します。
参考記事:労働基準監督署の是正勧告を受けたら?対処法を弁護士が解説
相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、会社が制度を定める場合に就業規則に書き込む必要がある項目です。
労働基準法89条3号の2~10号に定められています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(中略)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これらの事項は、会社が制度を置くときには就業規則への記載が必須となる項目です。
たとえば、退職手当(退職金)がある会社では、必ずルールを記載しなければなりません(就業規則の中に詳細を書かずに、「退職金規程」を別途作成しても構いません)。
もっとも、退職金の支払いは法的義務ではないため、支払わない会社では記載は不要です。
制度を設けるときに限って記載が義務となるのが「相対的必要記載事項」です。
制度を作るのに記載を怠ると、作成義務違反となります。
絶対的必要記載事項の場合と同様に、「30万円以下の罰金」というペナルティが用意されています(労働基準法120条1号)。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、会社が自由に就業規則に書き込める項目です。
法的な義務ではありません。
具体例としては、就業規則の目的や企業理念などが挙げられます。
就業規則の絶対的必要記載事項

弁護士
岡本 裕明
労働時間
まず、労働時間や休日に関する以下の事項は必ず記載しなければなりません。
始業・終業時刻
「始業:午前9時、終業:午後6時」のように、始業時刻と終業時刻を明示する必要があります。
「1日8時間、週40時間」といった記載では足りません。
休憩時間
「12時から13時まで」のように示します。
法律上は、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上与えるものとされています(労働基準法34条1項)。
休日
休日も規定が必要です。
「土曜日」「日曜日」「国民の祝日」「年末年始(12月〇日〜1月〇日」「夏季休日(〇月〇日~〇月〇日)」などが考えられます。
休暇
年次有給休暇だけでなく、産前産後休暇、生理休暇、慶弔休暇などについても日数等を記載してください。
交替制をとるときの就業時転換
2交替制や3交替制といった交替制をとるときには、始業終業時刻や休憩時間だけでなく、何日ごとに勤務時間帯を変えるかなどを記載しましょう。
賃金
定期的に支払われる賃金についても絶対的必要記載事項となっています。
以下の事項を記載しましょう。
・決定要素
・計算方法
・支払い方法(銀行振込など)
・締め日と支払日(月末締め翌月25日払いなど)
・昇給に関する事項
基本給だけでなく、通勤手当、住宅手当、家族手当、時間外手当、役職手当などの各種手当も記載してください。
なお、ボーナスや退職手当については後述する相対的必要記載事項となっています。
退職・解雇
退職に関する事項も記載しなければなりません。
具体的には以下の事項です。
・定年制(年齢など)
・任意退職、合意解約(手続きなど)
・解雇(解雇理由、手続きなど)
とりわけ解雇はトラブルになりやすいため、解雇理由を明示しておく必要があります。
参考記事:解雇とは?退職勧奨とは?両者の違いや注意すべき点を会社側弁護士が解説
就業規則の相対的必要記載事項

弁護士
岡本 裕明
退職手当
退職金は法的な義務ではありません。
ただし、制度を置く場合には、就業規則(退職金規程含む)に記載する義務があります。
適用される労働者の範囲、支給要件、計算方法、支払方法、支払時期などを記載してください。
賞与など臨時の賃金・最低賃金
賞与(ボーナス)など臨時の賃金の支払い自体は法的義務ではありませんが、支払うのであれば就業規則に記載しなければなりません。
支給基準、時期、支払方法などを規定しましょう。
会社として最低賃金額を定めるときも就業規則に記載します。
法令上の最低賃金は年々上昇しているため、社内の最低賃金が法令の金額を下回らないように注意してください。
労働者に負担させるもの
業務に必要な物品や費用を従業員に負担させるときは定めを置く必要があります。
仕事で必要なものを従業員に用意させるときは忘れず記載しましょう。
安全衛生
安全衛生に関する事項も相対的必要記載事項です。具体的には、安全衛生のために守るべきことや、安全衛生教育に関する事項などが挙げられます。
職業訓練
スキルアップのために会社が職業訓練を行うのであれば、訓練を受ける義務、訓練中・訓練後の処遇などを就業規則に記載します。
災害補償・業務外の傷病扶助
業務上・業務外のケガ・病気への補償について、法令通りの補償だけでなく、会社としての上乗せ分なども記載します。
表彰・懲戒
表彰や制裁(懲戒)についてのルールも記載しなければなりません。
とりわけ、懲戒の理由や種類、手続きの記載は重要です。
すべての労働者に適用される制度
以上の他にも、事業場のすべての労働者に適用される制度を設ける場合には、就業規則に明記しましょう。
たとえば、休職制度、配転・出向、旅費規定などが挙げられます。
就業規則の任意的記載事項

弁護士
岡本 裕明
会社の裁量で定められる「任意的記載事項」としては、就業規則の目的、企業理念、従業員の心得、服務規律、就業規則の解釈・適用に関する規定などが挙げられます。
基本的に何を定めるかは自由ですが、公序良俗には反しないようにしてください。
就業規則の記載事項に関する注意点

弁護士
岡本 裕明
最低基準を下回らない
就業規則で定めるルールは、法令上の最低基準を下回らないようにしましょう。
たとえば、年次有給休暇を法定日数より少なくする、都道府県ごとの最低賃金より低い賃金を設定するといったことがあってはなりません。
就業規則が法令を下回っていたときは、その部分は無効です(労働契約法13条)。
参考記事:就業規則の効力|発生要件は?いつから発生する?会社側弁護士が解説
従業員に意見聴取する
就業規則を作成する際には、内容につき従業員に意見聴取しなければなりません。
具体的には、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合には過半数を代表する者の意見を聴くこととされています(労働基準法90条1項)。
ただし、意見を聴けばよいのであり、同意を得たり意見に従ったりする義務まではありません。
参考記事:就業規則に関する4つの義務|10人未満でも作成すべき理由
適宜見直す
いったん作成した就業規則の記載事項は適宜見直すようにしてください。
変化が激しい現代社会においては、すぐに内容が古くなってしまいます。
たとえば、テレワークや副業など新しい働き方に対応した規定が求められるようになりました。
最低賃金の上昇など、法令上のルールが変わるケースも少なくありません。
時代や環境の変化に対応するためには、就業規則のアップデートが不可欠です。
就業規則の記載事項は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、就業規則の記載事項について解説してきました。
就業規則の記載内容は、会社の行く末を決めるともいえるほど重要です。
最低限の事項を書くだけにとどまらず、理想の会社を目指すために中身を吟味するのがよいでしょう。
就業規則の記載事項にお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
ご相談いただければ、就業規則の記載事項や必要な手続きについてアドバイスいたします。
会社の実情に即した内容とするには、ひな形のままでは不十分です。
専門家への相談・依頼をオススメします。
「法律上の記載事項を漏らさないようにしたい」「自社に適した就業規則を作りたい」とお考えの方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.就業規則に必ず記載しなければならない絶対的必要事項は何ですか?
- A.労働時間(始業・終業時刻、休憩時間)、賃金の決定・計算・支払方法、退職に関する事項(解雇理由や手続きなど)です。
- Q.相対的必要記載事項はどのような場合に必須になりますか?
- A.会社が制度を設けるとき(退職手当、賞与、最低賃金設定など)に就業規則へ記載が必要です。
- Q.任意的記載事項として会社が自由に書ける項目にはどんなものがありますか?
- A.就業規則の目的・企業理念、従業員の心得や服務規律など法的義務ではなく自由に定められる項目です。
- Q.就業規則の作成義務違反に対する罰則はありますか?
- A.労働基準法120条1号により、作成義務違反の場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
- Q.企業は就業規則を法令に沿った最低基準で作成するためにどのような注意点がありますか?
- A.法定最低基準(有給休暇日数、最低賃金など)を下回らないようにし、従業員の意見聴取や定期的な見直しを行うことが重要です。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。