お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
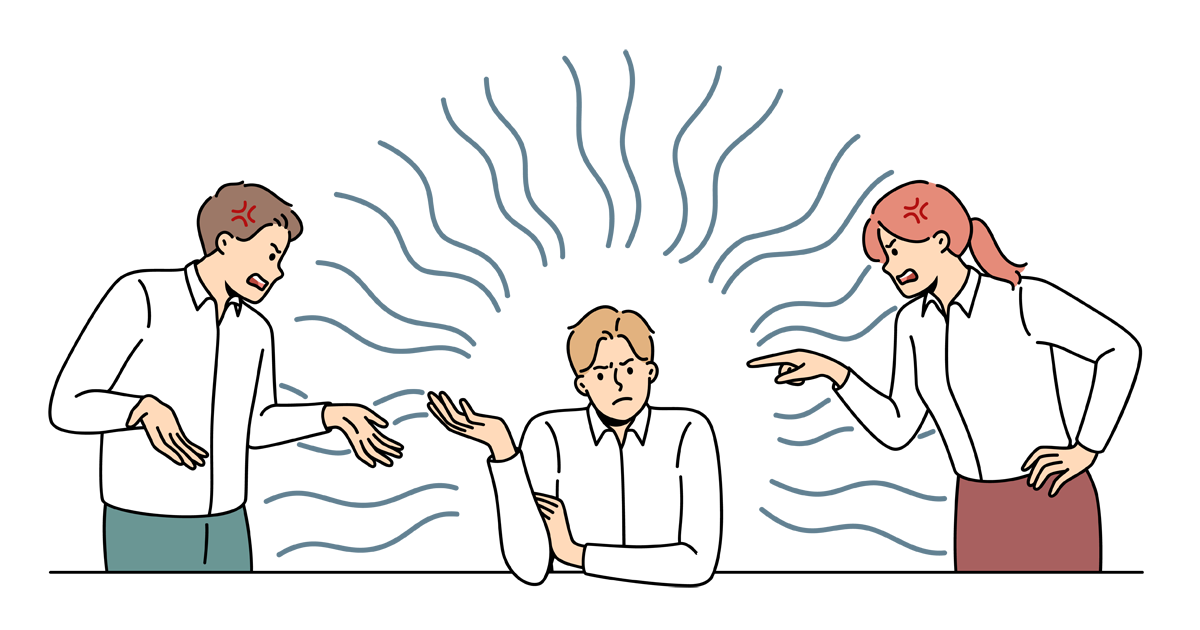
「試用期間中の従業員を解雇したい」とお悩みでしょうか?
試用期間はいわば「お試し期間」であり、適性がなければ自由に解雇していいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、いったん雇用関係に入っている以上、簡単には解雇できません。
多少の能力不足や遅刻・欠席では解雇できないとお考えください。
今回は、試用期間における解雇について、理由になることや注意点を解説しています。
試用期間中の従業員の解雇を検討している会社経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
採用や内定を含めた基礎知識は、以下の記事で紹介しています。
参考記事:採用・内定・試用期間の意味や企業が注意すべき法的問題点
試用期間における解雇の基礎知識

弁護士
岡本 裕明
試用期間は適性を見極める期間
そもそも試用期間とは、入社させた状態で従業員の能力や適性を見極めるための期間です。
採用の過程だけでは、労働者の適性を正確に判断するのは難しいでしょう。
そこで、採用後に会社が能力を評価し、本採用するかどうかを判断するための期間として試用期間が設けられます。
一般的に、試用期間の法的性質は「解約権留保付き労働契約」であるとされています(三菱樹脂事件判決・最高裁昭和48年12月12日)。
適性がないと判明すれば解約できるとの条件がついているものの、労働契約は成立している状態ということです。
試用期間にする解雇の種類と違い
解約権がついている以上、会社が従業員として不適格であると判断した際には解約権の行使(解雇)は可能です。
もっとも、本採用後の解雇が「解雇権濫用法理」(労働契約法16条)により厳しく制約されているのと同様に、簡単にはできません。
試用期間における解雇は、試用期間の途中での解雇と、期間満了時の解雇(本採用拒否)に分けられます。
たとえば試用期間が3ヶ月のときに、1ヶ月の時点で解雇すると試用期間中の解雇、3ヶ月経過時点だと期間満了時の解雇(本採用拒否)となります。
参考記事:解雇とは?退職勧奨とは?両者の違いや注意すべき点を会社側弁護士が解説
期間中の解雇
試用期間中の解雇は特にハードルが高いです。
試用期間は適性を見極めるための期間として設定されている以上、期間が満了した時点で結論を出すのが通常です。
にもかかわらず期間の途中で解雇するとなると、相当の理由が必要になります。
【事案の概要】
原告は証券会社に営業職として中途採用された。試用期間は6ヶ月であったが、成績不振で営業担当の資質に欠けるとして3ヶ月で解雇された。
【結論】
解雇は無効
【ポイント】
解雇を無効と判断した理由のひとつとして、試用期間の経過を待っていないことが挙げられました。
試用期間は適性を見極めるために必要な期間である以上、よほどの理由がない限り期間中の解雇は認められないとお考えください。
期間満了時の解雇(本採用拒否)
試用期間満了時の本採用拒否は、通常の解雇より広い範囲で解雇の自由が認められるとされています。
とはいえ、「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許され」るに過ぎません(三菱樹脂事件判決・最高裁昭和48年12月12日)。
本採用拒否が有効とされたケースとして、ブレーンベース事件をご紹介します。
【事案の概要】
原告は、医療機器製造販売業を営む被告会社に試用期間3ヶ月で雇用されたが、試用期間満了時に解雇された。
【結論】
本採用拒否は有効
【ポイント】
会社が本採用を拒否した理由としては以下が挙げられます。
- パソコンに精通していると申告していたのに満足に使用できなかった
- 緊急を要する業務指示に応じなかった
- 重要な商品発表会の翌日は必ず出勤する慣行であったのに休暇を取得した
判決では、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い範囲で認められる旨を指摘したうえで、本件における解雇には客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当であると認めました。
一般的に、試用期間中の解雇や本採用後の解雇と比べて、試用期間満了時における本採用拒否のハードルは低いとされています。
とはいえ、自由に解雇できるわけではありません。
慎重に進めるようにしてください。
試用期間の従業員を解雇できる理由

弁護士
岡本 裕明
参考記事:解雇できる理由は?ケースごとのポイントを会社側弁護士が解説
能力不足
能力不足を理由に解雇を考える方は多いです。
しかし、多少の能力不足では解雇できません。
特に、新卒や未経験者であれば、教育によって能力を身につけさせることが前提となっています。
試用期間だけでは時間が足りない場合も多く、期間終了後も指導を続ける必要があると判断される可能性が高いです。
一定のスキルを有する経験者であることを前提に中途採用した場合には、能力不足を理由とする解雇でも多少ハードルが下がります。
とはいえ、会社によって仕事の進め方が異なり、すぐには能力を発揮できないケースも少なくありません。
試用期間の途中での解雇はとりわけ難しいです。
病気・ケガ
病気やケガで物理的に働けない場合もあります。
そもそも業務が原因で生じたケガや病気の場合には、原則として解雇できません(労働基準法19条1項)。
プライベートが原因であっても、まずは就業規則に沿って休職させるのが通常です。
いきなり解雇しないようにしてください。
勤務態度の不良
無断遅刻・欠席や業務命令違反といった勤務態度の問題を理由とする場合もよくあります。
遅刻・欠席があっても、数回では解雇できません。
指導しても改善が見られず繰り返すような場合に限って解雇を検討しましょう。
業務命令違反については、程度によっては解雇の対象になり得ます。
もっとも、正当な命令か、十分な指導を行っているか、従業員の側に従えない事情がないかといった点は確認してください。
なお、社内での横領など、重大な違法行為がある場合には解雇が可能です。
ただし、事前に十分な事実調査を行うようにしましょう。
協調性の欠如
協調性の欠如を解雇の理由として挙げる方は多いです。
しかし、協調性の評価は難しく、周囲との相性の問題である可能性もあります。
あいまいな理由であり、通常は解雇まではできません。
経歴詐称
経歴詐称は解雇の理由になり得ます。
とりわけ、大卒採用であるのに大学を卒業していない、資格が必要な職種で資格を有していなかったなど、事前に知っていれば採用していないような重大な詐称があれば解雇が可能です。
ただし、採用を左右するとは思われない些細な部分であれば、解雇はできません。
試用期間における解雇の注意点

弁護士
岡本 裕明
指導・改善を試みる
能力や適性に問題があるときには、まずは指導・改善を試みてください。
とりわけ新卒採用や未経験者採用の場合には、最初から十分な働きは期待できません。
社会マナーが身についていない従業員もいるでしょう。
会社が教育を施すのが前提となっているため、試用期間中はもちろん、期間経過後も根気強く指導をする必要があります。
簡単には解雇できないとお考えください。
結果だけで判断しない
新卒や未経験者と比べると、経験者採用の場合には解雇のハードルが下がります。
たとえば、一定のスキルを要求していることが採用条件や採用過程で明らかになっているケースでは、求める能力がなかったとして解雇できる可能性があります。
しかし、職場によって仕事の進め方が異なるうえ、はじめは周囲とのスムーズな連携が難しい場合もあるでしょう。
そのため、結果だけで見ると判断を誤ってしまうおそれがあります。
結果だけで解雇を決めるのではなく、過程を含めて評価するようにしてください。
解雇予告を行う
解雇できる場合であっても、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法20条1項本文)。
手続きは踏むようにしてください。
なお、試用期間に入って14日以内の従業員を解雇する際には、解雇予告は不要です(労働基準法21条4号)。
ただし、解雇予告が不要となるだけであり、自由に解雇できるわけではありません。
解雇予告について詳しくは、以下の記事で解説しています。
参考記事:解雇予告手当とは?支払い時の注意点や計算方法を解説
不当解雇とされるリスク
裁判所に不当解雇と判断されると、復職させたうえで未払い賃金(バックペイ)を支払わなければなりません。
慰謝料も発生する可能性があり、会社の金銭的負担は大きいです。
加えて、SNSで悪評が拡散されるなどして会社のイメージが低下するおそれもあります。
解雇はリスクが高いため、十分な指導をして改善しない場合でも、まずは退職勧奨をするなど別の対応をとるべきケースもあります。
参考記事:退職勧奨の進め方・言い方|円滑に進めるための注意点を弁護士が解説
試用期間での解雇をお考えの方は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、試用期間における解雇について、理由や注意点を解説してきました。
試用期間中でも労働契約が成立している以上、解雇はハードルが高いです。
能力不足だからといって安易に解雇してはなりません。まずは十分な教育・指導が不可欠となります。
試用期間における解雇については、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
ご相談いただければ、試用期間に解雇できるか、どう進めればいいかをアドバイスいたします。
既にトラブルに発展している場合にも迅速に対応いたします。
「試用期間中の従業員を解雇したい」「解雇したらトラブルになった」とお悩みの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.試用期間中に従業員を解雇することは可能ですか?
- A.はい、試用期間中に解雇は可能ですが、相当な理由が必要であり、通常の解雇よりもハードルが高いです。
- Q.試用期間終了時に本採用を拒否する場合、どのような理由が認められますか?
- A.客観的に合理的で社会通念上相当な理由(例:業務遂行能力不足、指示違反など)がある場合に限り、本採用拒否が有効とされます。
- Q.試用期間中に解雇する場合、労働基準法で定められた予告義務はありますか?
- A.試用期間中の14日以内に雇用された従業員を解雇する場合は予告義務は不要ですが、14日以降の場合は30日前の予告または30日分の賃金を支払う必要があります。
- Q.能力不足が理由で解雇できるケースはどのようなものですか?
- A.経験者で一定スキルを有することが前提の採用の場合は能力不足でも解雇できる可能性がありますが、新卒や未経験者では教育期間として扱われ、解雇は難しいです。
- Q.試用期間中に不当解雇と判断された場合、企業はどのような負担を負うことになりますか?
- A.不当解雇と判断されると、復職させたうえで未払い賃金や慰謝料を支払う必要があり、企業の財務・イメージに大きな影響を与えます。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。


