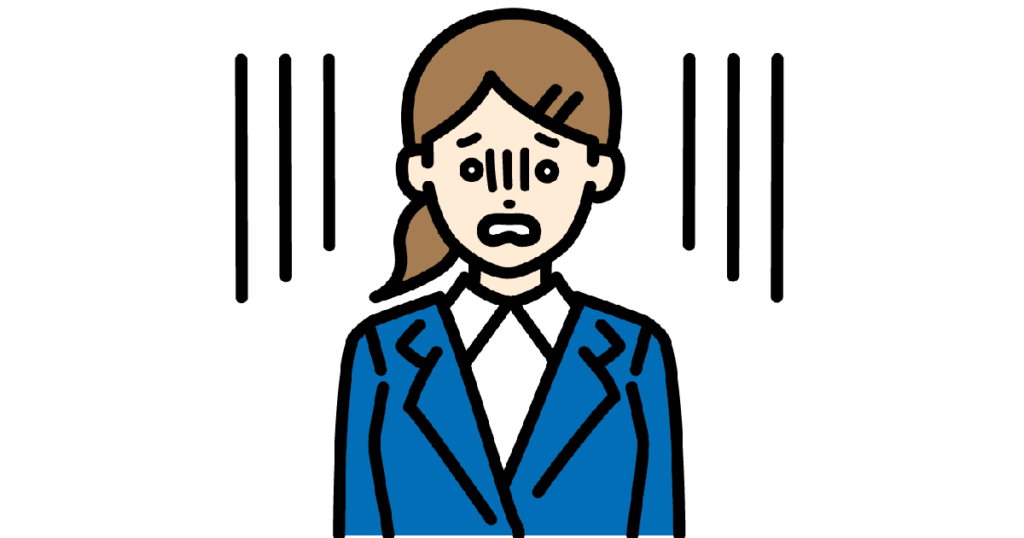お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
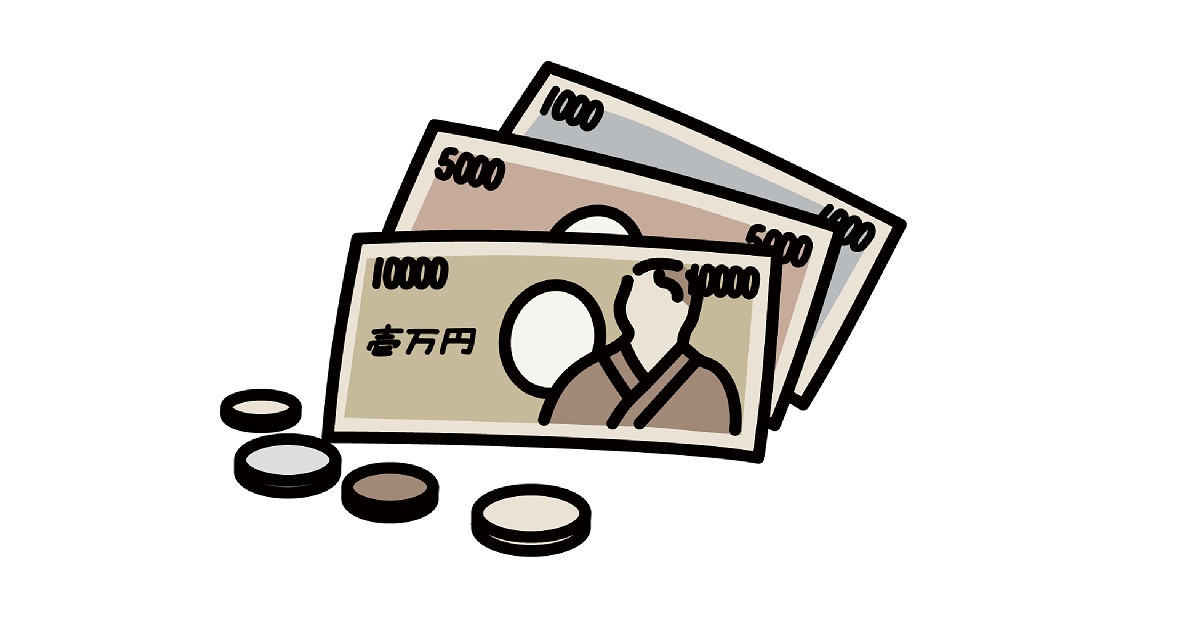
パワハラがあると、加害者本人だけでなく、会社にも慰謝料が発生します。
慰謝料額の相場は数十万円から200万円程度です。
行為の悪質性、継続性、被害者に生じた結果(精神疾患・自殺)などにより金額が変動します。
今回は、パワハラによる慰謝料相場や裁判例、会社がとるべき対応などを解説しています。
パワハラが発生した会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
ハラスメントに関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:セクハラ・パワハラとは?会社が負う責任やとるべき対策を解説
慰謝料が生じるパワハラとは?

弁護士
岡本 裕明
法律上の定義によると、パワハラとは、職場において行われる、以下の①〜③の要件をすべて満たす言動をいいます(労働施策総合推進法30条の2第1項)。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えている
③労働者の就業環境が害される
①に該当する典型例は、上司から部下への行為です。
ただし、同僚や部下からの行為でも、状況によってはパワハラに該当し得ます。
②にあたるのは、社会常識から見て明らかに業務上不要な行為、あるいは必要であっても度が過ぎた行為です。
適切な方法で行われる注意・指導は、パワハラには該当しません。
③は、言動の影響により、働くうえで見過ごせないほどの支障が生じることを意味します。
平均的な労働者の感じ方を基準に判断します。受けた側が「パワハラだ」と主張しても、必ずしもパワハラになるとは限りません。
パワハラの定義について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考記事:パワハラとは?定義・事例・会社がとるべき対応を解説
パワハラで会社が慰謝料を請求される法的根拠

弁護士
岡本 裕明
使用者責任
使用者責任とは、会社に雇われている人が事業の執行にあたって他者に損害を与えたときに、会社が負う賠償責任です(民法715条)。
従業員がしたパワハラについて、加害者本人のみならず、会社も法的責任を負います。
業務時間中だけでなく、業務の延長といえる宴会等でパワハラが行われた際にも、職務関連性が認められ、会社に賠償責任が生じます。
安全配慮義務違反
使用者責任とは別に、会社は従業員に対して安全配慮義務(職場環境配慮義務)を負います。
働きやすい職場環境を維持する義務を果たしていないと認定されると、債務不履行(民法415条)あるいは不法行為(民法709条)として、会社自身に賠償責任が生じます。
たとえば、パワハラを黙認する、被害の訴えに取り合わないといった状況であれば、安全配慮義務(職場環境配慮義務)に反しているとされてしまいます。
参考記事:パワーハラスメント防止法の内容|パワハラ防止措置はどうする?
パワハラの慰謝料相場

弁護士
岡本 裕明
数十万円から200万円程度が相場
過去の裁判例からすると、パワハラの慰謝料相場は数十万円から200万円程度といえます。
ただし、軽いものだと10万円以下、自殺に至るようなケースだと1000万円超となり、実際に認められる金額は事案によって大きく異なります。
金額を左右する要素
パワハラの慰謝料額を左右する要素としては、以下が挙げられます。
行為の悪質性
まず重要になるのが、パワハラ行為そのものの悪質性です。
パワハラには、暴言、暴力、無視、過大な要求など多種多様なバリエーションがあります。
また、暴言とひとくちにいっても、比較的軽いものからひどい人格否定に及ぶものまで程度は様々です。
より悪質なものであれば、慰謝料は高額になりやすいです。
行為の継続性
行為の継続性もひとつのポイントです。
一つ一つはそれほど程度の重いパワハラではなくとも、長期間にわたって繰り返されれば、被害者が受ける精神的な苦痛は大きくなります。
継続的なパワハラでは慰謝料は高くなる傾向にあります。
被害者に生じた結果
被害者に生じた結果は慰謝料を大きく左右します。
パワハラが原因で被害者がうつ病などの精神疾患を発症したときには、慰謝料が高額になりやすいです。
特に自殺にまで追い込まれてしまったケースでは、1000万円を超える慰謝料が発生します。
慰謝料のほかに、逸失利益(将来得られるはずであった収入)も請求されるため、会社が負担する賠償総額が大きくなるおそれがあります。
精神疾患の発症や自殺に至ったケースでは、パワハラとの間の因果関係の有無が争いになりやすいです。
参考記事:うつ病は労災認定される?認定基準や会社の対応を弁護士が解説
被害者側の問題
被害者側の事情で慰謝料が減額されるケースもあります。
たとえば、被害者に以前から精神疾患による通院歴があったケースです。
原因のすべてがパワハラにあるわけではないと判断され、慰謝料が減額される方向に働きます。
また、パワハラの背景に被害者の問題行動があったときにも、減額の可能性があります。
パワハラで慰謝料が認められた裁判例

弁護士
岡本 裕明
まずは、上司の部下に対する叱責が問題となった事案です。
【事案の概要】
原告が同僚を誹謗中傷したことを理由として、人事課長との面談が行われた。人事課長は「会社の秩序を乱すような者は要らん」「何が監督署だ、何が裁判所だ」「とぼけんなよ、本当に。俺は、絶対許さんぞ」などと発言した。原告が人事課長と会社に対し提訴した。
【結論】
不法行為の成立を認め、慰謝料10万円の支払いが命じられた。
【ポイント】
人事課長が大きな声を出し、原告の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責していたため、慰謝料の支払いが命じられました。ただし、原告にも問題行動があり、面談を行った目的自体は正当であったとの事情もあり、慰謝料は低額にとどまっています。
次に、上司の暴言により部下がうつ病になった事例をご紹介します。
【事案の概要】
指示通りの資料を提出せず改善しない、システム開発が無理だと言い出すなどした原告に対し、上司が「新入社員以下だ。もう任せられない」「何でわからない、お前は馬鹿」といった発言をした。また、うつ病に罹患したとして、原告から診断書を提出して休職願い出があったのに対し、上司は、今休職になれば異動できなくなるなどとして休職を先延ばしにさせた。
【結論】
上司と会社の責任を認め、慰謝料は150万円とした。
【ポイント】
上司の対応は不適切であったうえ、うつ病を発症していることから、最初に紹介した事例よりも慰謝料が高額になっています。ただし、悪質性が高いとはいえない等の理由から、本事例の1審よりも減額されています。
最後に紹介するのは、パワハラの結果、自殺に至った事例です。
【事案の概要】
消火器販売・消火設備の設計施工保守点検等を業とする会社において、新入社員が仕事上のミスについて、上司から「辞めればいい」「死んでしまえばいい」などと発言をされ、うつ状態になり自殺した。原告(遺族)が上司と会社に対し提訴した。
【判決】
慰謝料2300万円を含め、計7261万円の賠償が命じられた。
【ポイント】
人格否定を繰り返し精神疾患を発症させ、自殺にまで至らせたため、高額の慰謝料・賠償金が認められた事例です。
このように、行為の悪質性や生じた結果等によって慰謝料額は大きく変わります。
パワハラで慰謝料を請求された会社の対応

弁護士
岡本 裕明
事実調査
パワハラに関して事実を把握できていないのであれば、まずは事実調査をしなければなりません。
対応方針を決める際の前提になります。
調査では、当事者への聴き取りはもちろん、必要に応じて関係者への事情聴取や客観的な証拠の確認を行います。
パワハラの事実が明らかになったら、加害者への処分も検討しましょう。
交渉による解決
被害者とは、まずは交渉により解決を図るのが一般的です。
交渉で合意できれば早期に解決でき、ダメージが広がるのを回避できます。
口外禁止など、細かい条件を柔軟に定められる点もメリットです。
交渉の際には、認めるべき点は認め、謝罪も行うなど、誠実な対応が求められます。
慰謝料相場を把握したうえで、妥当な解決策を模索するようにしてください。
訴訟での主張
交渉で合意できなければ、訴訟等の裁判所での争いに移ります。
訴訟における会社の主張は、そもそもパワハラに該当しない、該当するにしても請求額が過大であるといったものになります。
裁判所は証拠を重視するため、証拠を入念に準備したうえで、法的に適切な主張をしなければなりません。
なお、訴訟では、判決に至る場合だけでなく、途中で和解して終了となるケースも多いです。
パワハラで慰謝料を請求されたら弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、パワハラによる慰謝料について、慰謝料相場や裁判例、会社がとるべき対応などを解説してきました。
パワハラがあると、使用者責任や安全配慮義務違反を根拠として、会社にも慰謝料が発生します。
慰謝料相場は多くのケースで数十万円から200万円程度の範囲に収まりますが、ケースバイケースです。
行為態様や被害者に生じた結果によって大きく変動します。
パワハラで慰謝料を請求された会社関係者の方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
事実関係に誤りはないか、請求額が相場に比して過大ではないかなど、被害者の請求内容を吟味したうえで適切な対応をいたします。
「パワハラで会社に責任が生じるのか」「請求された慰謝料額は妥当なのか」などと疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
- Q.パワハラによる慰謝料相場はどのくらいですか?
- A.一般的に数十万円から200万円程度が相場で、軽いケースは10万円以下、自殺に至るような重度の場合は1000万円超になることもあります。
- Q.会社がパワハラで慰謝料を請求された場合、法的根拠は何ですか?
- A.主に「使用者責任」(民法715条)と「安全配慮義務違反」(民法415条・709条)が根拠となり、会社が賠償責任を負うことがあります。
- Q.慰謝料額に影響を与える主な要素は何ですか?
- A.行為の悪質性・継続性、被害者に生じた精神疾患や自殺などの結果が大きく影響し、悪質で長期にわたる場合や重度の精神疾患が発症した場合は高額になります。
- Q.会社が慰謝料請求に対して取るべき対応は何ですか?
- A.まず事実調査を行い、加害者への処分や証拠収集をし、交渉で合意できない場合は訴訟に備えて法的主張と証拠を整えることが重要です。
- Q.具体的な裁判例で慰謝料がどの程度認められたか?
- A.叱責による慰謝料は10万円、うつ病発症での慰謝料は150万円、自殺に至ったケースでは2300万円の慰謝料と計7261万円の賠償金が認められた事例があります。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。