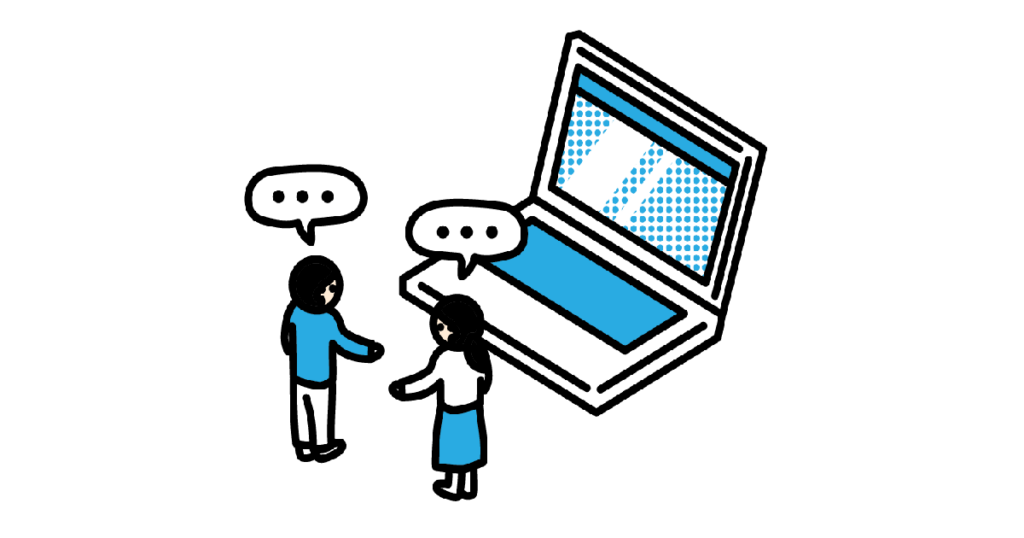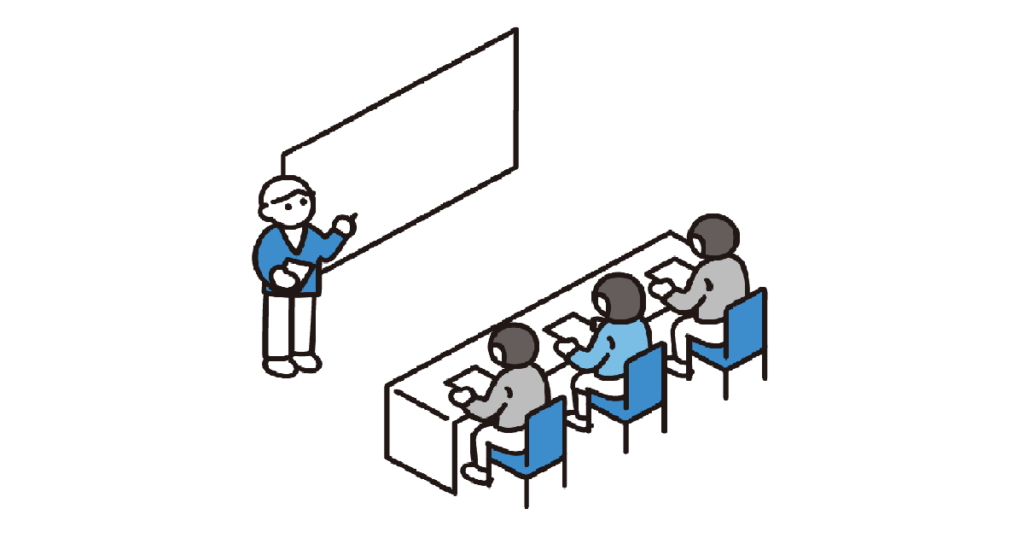お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
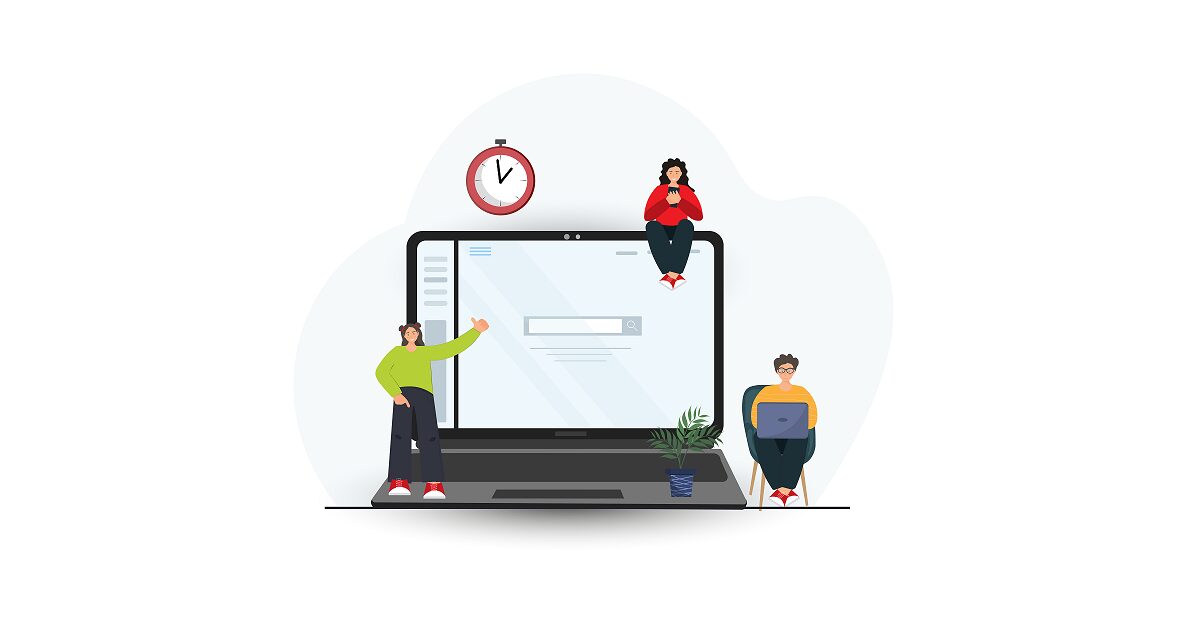
「就業規則はどんな会社に作成義務があるのか」と疑問をお持ちでしょうか。
事業場(事務所・店舗・工場など)に10人以上の従業員がいるときは、企業に就業規則の作成義務が生じます。
作成するだけでなく、届出・周知など、就業規則に関して様々な義務が存在します。
必須でないケースでも就業規則のメリットは大きいため、作成するのが望ましいです。
今回は、就業規則に関する4つの義務や、義務がないときでも作成すべき理由を解説しています。
就業規則の作成を予定している会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
就業規則に関する全般的な基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:就業規則とは?効力や記載事項、作成・変更方法を弁護士が解説
就業規則に関する義務①作成義務

弁護士
岡本 裕明
以下で、就業規則の作成義務が生じるケースや、義務がなくとも作成すべき理由を解説します。
常時10人以上雇用している事業場は作成必須
就業規則の作成については、労働基準法89条に定めが置かれています。
条文によると、就業規則の作成義務があるのは「常時10人以上の労働者を使用する使用者」です。
この要件を詳しく見ていきましょう。
パート・アルバイトも含む
「労働者」には、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも含まれます。
したがって、正社員1人、アルバイト9人であっても「10人以上」に該当するため、就業規則の作成が必要です。
もっとも、派遣社員や業務委託により働いている人はカウントしません。
「常時10人以上」とは、「毎日10人以上出勤している」という意味ではありません。
出勤頻度や稼働時間が少なくとも、雇っている状態にある従業員が10人以上いれば作成義務が生じます。
ただし、繁忙期だけ一時的に人手を増やした結果として10人を超えているようなケースは「常時10人以上」に該当しません。
事業場単位でカウントする
10人以上かどうかは、事業場単位でカウントします。企業単位ではありません。
同じ会社であっても、別の場所にあるのであれば事務所・支店・店舗などごとに人数を数えます。
たとえば、A営業所とB営業所に5人ずつ(計10人)の場合には、作成は不要です。
A営業所に10人、B営業所に5人のときは、A営業所についてのみ作成義務が生じます。
違反するとペナルティあり
作成義務があるのに違反した会社には「30万円以下の罰金」というペナルティも定められています(労働基準法120条1号)。
作成義務だけでなく、以下で紹介する他の義務についても同様です。
通常はいきなり罰則を科されることはありませんが、労働基準監督署による指導や是正勧告の対象になり得ます。
参考記事:労働基準監督署の是正勧告を受けたら?対処法を弁護士が解説
10人未満でも作成すべき理由
事業場で雇っている人が10人未満の場合、法律上は就業規則の作成義務は課されません。
とはいえ、雇用している従業員がいるのであれば作成が望ましいです。理由としては以下が挙げられます。
効力は発生する
義務がなくとも、就業規則を作成した際には効力が発生します。
たとえば、採用時にひとりひとりの労働者と個々に合意しなくとも、就業規則のルールを適用できます(労働契約法7条本文)。
また、変更の際には、合理的な変更であれば反対する労働者に対しても適用が可能です(労働契約法10条)
就業規則には従業員に統一的なルールを適用できるメリットがあるため、作成する意義は大きいです。
なお、正社員とパートで別の就業規則を定めるなど、職種に応じてルールを定めることもできます。
参考記事:就業規則の効力|発生要件は?いつから発生する?会社側弁護士が解説
トラブルに対処できる
就業規則には様々なルールを置くことができ、トラブルの予防や解決につながります。
たとえば、懲戒の要件や種類を定めておけば、問題社員への懲戒処分が可能です。
してはいけないことが明確になっていることで問題行為の抑止にもつながり、社内の規律を保つ効果が期待できます。
従業員の行動を制限するものだけでなく、休職制度、在宅勤務、フレックス制といった、働きやすさを高めるルールも定められます。
労働基準法をはじめとする法令は、多くの場合、最低限のルールを規定しているに過ぎません。
就業規則を作成して社内ルールを決めると、目指している会社を実現しやすくなるでしょう。
就業規則に関する義務②届出義務

弁護士
岡本 裕明
常時10人以上の労働者を使用する事業場において就業規則を作成したときは、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
新規作成だけでなく、変更の際も同様です。
届出は、事業場を管轄する労働基準監督署に対して行います。
原則として、事業場ごとに管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
ただし、就業規則の内容が同じであれば、本社の所在地で一括で届け出ることも可能です。
就業規則に関する義務③意見聴取義務

弁護士
岡本 裕明
労働基準法90条に、意見聴取義務が定められています。
1項
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2項
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
条文に記載されている通り、就業規則を作成する際には、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合には過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
就業規則を届け出る際には、聴いた意見を記した書面を添付する必要があります。
意見聴取義務が定められているのは、従業員に内容を確認させるためです。
もっとも、意見を聴けばいいのであり、同意を得たり意見に従ったりする義務はありません。
会社が話し合いに応じる義務があるわけでもありません。
就業規則に関する義務④周知義務

弁護士
岡本 裕明
作成した就業規則は、従業員がいつでも確認できるようにしておかなければなりません。
就業規則の周知義務は労働基準法106条1項に定められています。
使用者は、(中略)就業規則(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
具体的には、たとえば以下の方法で労働者に周知する必要があります。
- 作業場の見やすい場所に掲示する、冊子にして備え付ける
- 印刷した書面を交付する
- 社内システムから閲覧できるようにする
就業規則があっても、従業員が簡単に確認できなければ意味がありません。
周知したうえで、できる限りルールを把握させるようにしてください。
就業規則の作成は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、就業規則に関する義務を解説してきました。
就業規則には、作成・届出・意見聴取・周知といった義務があります。
作成義務がない10人未満の職場においても、統一的ルールを定めるメリットは大きいです。
就業規則の作成を検討している方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。ご相談いただければ、就業規則の内容や必要な手続きについてアドバイスいたします。
会社の実情に即した内容とするには、ひな形のままでは不十分です。専門家への相談・依頼をオススメします。
「就業規則の作成義務があるかわからない」「自社に適した就業規則を作りたい」とお考えの方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.就業規則の作成義務はどのような会社に課せられますか?
- A.常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して、労働基準法89条で作成義務が課せられます。
- Q.10人未満の事業場でも就業規則を作成すべき理由は何ですか?
- A.作成すると労働契約法によりルールが効力を持ち、従業員の統一的な規定やトラブル防止に役立ちます。
- Q.就業規則を作成した後、どのような届出義務がありますか?
- A.事業場ごとに管轄の労働基準監督署へ届出し、変更時も同様に提出が必要です。
- Q.就業規則の作成・変更時に従業員から意見を聴く義務はありますか?
- A.はい、労働基準法90条により過半数の組合または代表者から意見を聴き、届出時にその記録を添付します。
- Q.就業規則は従業員にどのように周知すべきですか?
- A.見やすい場所への掲示、書面の交付、社内システムで閲覧可能にするなど、労働基準法106条の方法で周知します。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。