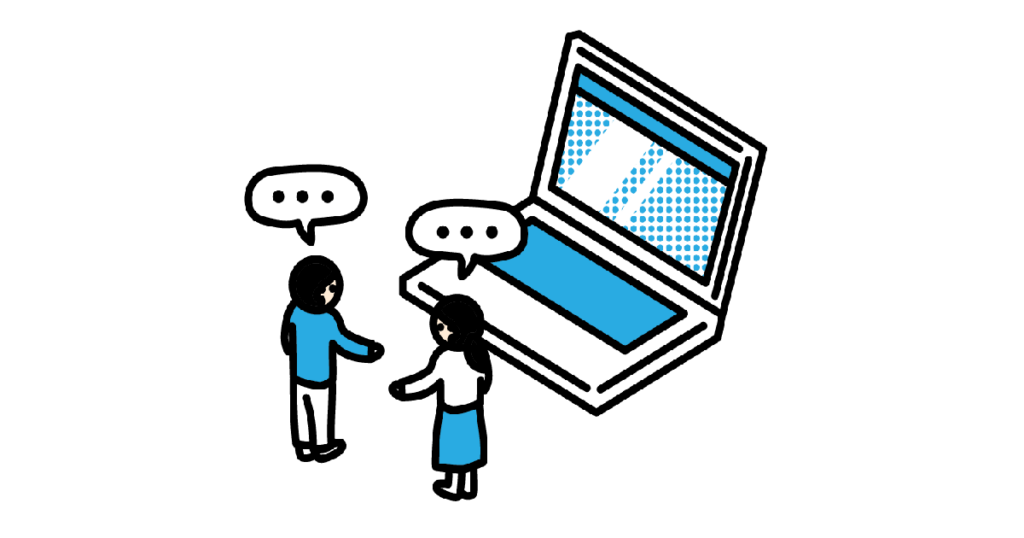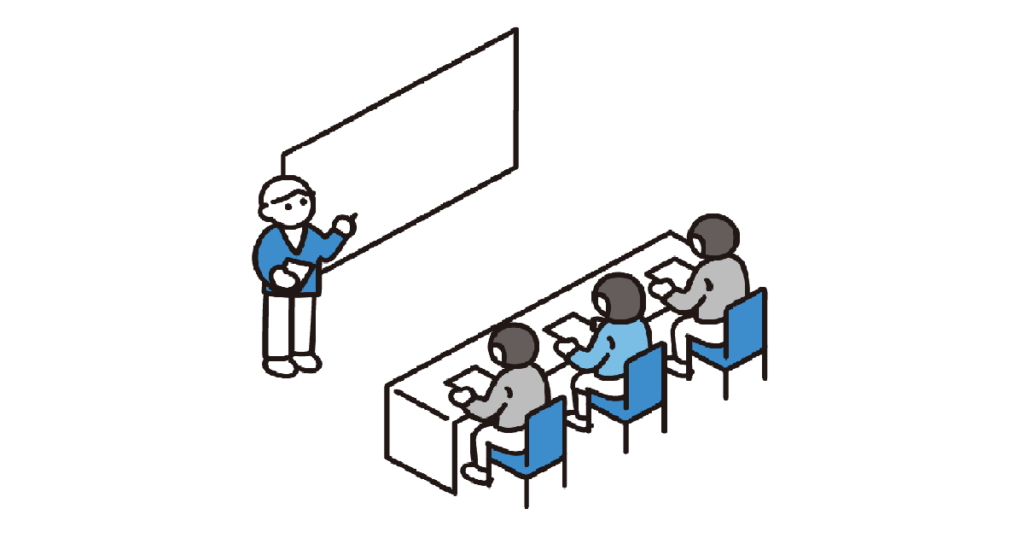お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

「就業規則の作成方法がわからない」とお悩みではないですか?
常時10人以上を雇っている事業場では、就業規則を作成しなければなりません。
盛り込む内容を決めたうえで従業員代表の意見を聴き、労働基準監督署に提出する必要があります。
従業員への周知も不可欠です。
今回は、就業規則の作成方法や注意点などを解説しています。
就業規則の作成を考えている会社経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
就業規則に関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:就業規則とは?効力や記載事項、作成・変更方法を弁護士が解説
就業規則の作成義務があるのはどんな会社?

弁護士
岡本 裕明
まずは、就業規則の作成義務があるのはどんなケースかを解説します。
常時10人以上を雇用している事業場
就業規則の作成義務があるのは「常時10人以上の労働者を使用する使用者」です(労働基準法89条)。
人数は、事業場単位でカウントするとされています。
したがって、事務所・営業所・支店・店舗ごとに10人以上の従業員がいるときには、就業規則を作成しなければなりません。
会社全体の従業員が10人であっても「A営業所に5人、B営業所に5人」のときには作成義務はありません。
「A営業所に10人、B営業所に5人」であれば、A営業所のみに作成義務が生じます。
正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトも人数にカウントします。
週1日しか働いていないパート従業員であっても含まれます。
ただし、派遣社員や業務委託により働いている労働者は数えません。
なお、職種ごとに異なる就業規則を作成することも可能です。
作成義務違反には「30万円以下の罰金」という罰則も定められています(労働基準法120条1号)。
就業規則の作成義務について詳しくは、以下の記事も参照してください。
参考記事:就業規則に関する4つの義務|10人未満でも作成すべき理由
10人未満でも作成するメリットは大きい
雇用している従業員が10人未満の事業場では、就業規則の作成義務はありません。
ただし作成自体は可能であり、作成すれば就業規則としての各種効力が発生します。
就業規則には、従業員に統一的なルールを定められる、ルールが明確化されトラブル防止につながるといったメリットがあります。
法律上の義務がなくとも作成が望ましいです。
就業規則の効力について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考記事:就業規則の効力|発生要件は?いつから発生する?会社側弁護士が解説
就業規則の作成方法

弁護士
岡本 裕明
条項案を作成する
まずは、就業規則の条項案を作成します。何を記載するかを決めるということです。
就業規則の記載事項としては、以下が挙げられます(労働基準法89条各号)。
・労働時間(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇など)
・賃金(決定・計算・支払方法、締切り・支払時期、昇給に関する事項。ボーナスや退職手当は除く)
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
【相対的記載事項(制度を定める場合に記載する事項)】
・退職手当(適用される労働者の範囲、決定・計算・支払方法、支払時期)
・臨時の賃金や最低賃金額
・物品・費用等の負担
・安全衛生
・職業訓練
・災害補償・業務外の疾病扶助
・表彰・制裁
・以上のほか、事業場の労働者すべてに適用される事項(例:休職)
【任意的記載事項(記載するか自由である事項)※以下に挙げられていない事項も記載可能】
・就業規則の目的
・企業理念
・服務規律
すべてを「就業規則」というタイトルの書面にまとめる必要はありません。
記載が多くなりやすい事項について独立させて、別途「賃金規定」「退職金規程」などを作成しても構いません。
別に定めた規程も就業規則の一部になります。
各項目について具体的にいかなる内容とすべきかは、企業の現状や目指す方向によってケースバイケースです。
厚生労働省が示す「モデル就業規則」をはじめとするひな形を利用して構いませんが、ひな形をそのまま用いると各企業に適さない内容となってしまいます。
会社の実情に応じた内容にカスタマイズするのが重要です。
就業規則の記載事項について詳しくは、以下の記事で解説しています。
参考記事:就業規則の記載事項|必ず記載すべき内容を弁護士が解説
従業員代表の意見を聴く
作成した条項案については、従業員の意見を聴かなければなりません。
就業規則への従業員の関心を高め、内容をチェックさせるためです。
具体的には、以下のいずれかの意見を聴くことが法律上の義務となっています(労働基準法90条1項)。
・労働者の過半数で組織する労働組合
・労働者の過半数を代表する者
「労働者の過半数を代表する者」は、選出の目的を明らかにしたうえで、投票や挙手などの方法で選出された代表をいいます(労働基準法施行規則6条の2)。
代表者は管理監督者(労働基準法41条2号)であってはなりません。
就業規則の作成にあたって、従業員代表の意見を聴くことは義務です。
もっとも、意見に従ったり、同意を得たりする義務まではありません。
内容を確認させて意見を聴いていれば、義務を果たしたと認められます。
なお、意見聴取義務に反すると、作成義務違反と同様に「30万円以下の罰金」が科される可能性があります(労働基準法120条1号)。
労働基準監督署に届け出る
作成した就業規則は、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
「賃金規定」など、就業規則の一部となっている規定も届出が必要です。
届出の際には、従業員に聴いた意見を記した書面を添付することも義務となっています(労働基準法90条2項)。
10人以上の従業員を雇用するに至った際には、事情の許す限り早く提出しましょう(労働基準法施行規則49条1項)。
原則として事業場ごとに管轄の労働基準監督署に提出しますが、内容が同じであれば本社の所在地に一括で届け出る方法も認められています。
届出を怠った場合にも「30万円以下の罰金」というペナルティが定められています(労働基準法120条1号)。
従業員に周知する
作成した就業規則は、従業員に周知しなければなりません(労働基準法106条1項)。
従業員が内容を把握していないと、ルールを定めた意義が損なわれるためです。
周知の方法としては、たとえば以下が挙げられます。
・作業場の見やすい場所に掲示する
・冊子にして備え付ける
・印刷した書面を交付する
・社内システムから閲覧できるようにする
社内でルールを浸透させるには、就業規則を定めるだけでなく、従業員に内容を知ってもらうのが重要です。
誰でも閲覧可能な状態にしておきましょう。
なお、周知義務違反も「30万円以下の罰金」の対象です(労働基準法120条1号)。
参考記事:就業規則の周知方法|義務違反のリスクも解説
就業規則を作成する際の注意点

弁護士
岡本 裕明
また、ひな形をそのまま利用せず、自社に合った内容にカスタマイズするのも重要です。
法令や労働協約に反しない
就業規則は、労働基準法をはじめとする法令や、労働組合と締結した労働協約におけるルールに反してはなりません。
反する部分は無効です(労働契約法13条)。
たとえば、「有給休暇は付与しない」と就業規則で定めたとしても、労働基準法39条に反するため無効になります。
いくら会社がルールを定められるとはいっても、法令や労働協約を無視してはなりません。
ひな形をそのまま使わない
就業規則を作成する際には、ひな形を利用するのが一般的です。
就業規則をゼロから作るのは難しいため、ひな形を参考にするのは構いません。
ただし、ひな形の文言をそのまま使い形だけ整えるのは避けてください。
厚生労働省のモデル就業規則をはじめとするひな形はあくまで一例であり、万能ではありません。
企業の業種や規模、経営理念などによってルールは異なって当然です。
ひな形をそのまま利用すると、足りない点・余計な点が出てきてしまいます。
自社の実情に合った最適な就業規則とするために、内容を吟味しなければなりません。
いったん就業規則を作成すると、変更するには手間がかかります。
「困ったら後から変えればいい」と考えずに、最初から適切な内容にするようにしてください。
参考記事:就業規則の変更手続きの流れ|従業員に不利益な変更はできる?
専門家に相談する
就業規則を作成する際には、弁護士や社労士といった専門家に相談するのがオススメです。
専門家に依頼すれば、実情をヒアリングしたうえで、会社に合った就業規則を作成できます。
法令遵守はもちろん、企業の目指す方向に合致したルールの作成が可能です。
とりわけ弁護士は紛争対応のプロであるため、トラブル予防・解決の観点も取り入れられます。
会社だけでも作成は可能ですが、より良いものを作るには、専門家に相談するようにしましょう。
就業規則の作成は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、就業規則の作成方法や注意点などを解説してきました。
10人以上を雇用する事業場においては、就業規則を作成しなければなりません。
従業員代表への意見聴取、労働基準監督署への届出、従業員への周知といった義務を守りつつ、会社の実情に合った就業規則を作成するのが重要です。
就業規則を作成しようとしている方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。ご相談いただければ、就業規則の作成方法や内容についてアドバイスいたします。
会社の実情に即した内容とするには、ひな形のままでは不十分です。
専門家への相談・依頼をオススメします。
「自社に合った就業規則を作りたい」とお考えの方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.就業規則の作成義務はどんな会社に課せられますか?
- A.常時10人以上を雇用している事業場(正社員・契約社員・パート・アルバイトを含む)が対象です。派遣社員や業務委託はカウントされません。
- Q.就業規則を作成する際の基本的な手順は何ですか?
- A.条項案を作成 → 従業員代表の意見聴取 → 労働基準監督署への届出(届出時に意見聴取書を添付) → 従業員への周知、という流れです。
- Q.就業規則に必ず記載しなければならない項目は何ですか?
- A.労働時間・賃金・退職に関する事項(解雇事由を含む)が絶対的記載事項として必須です。
- Q.就業規則の届出や周知を怠った場合、どんな罰則がありますか?
- A.労働基準法により30万円以下の罰金が科される可能性があります。
- Q.ひな形をそのまま使うと問題になるのはなぜですか?
- A.ひな形はあくまで例であり、企業の実情に合わないと無効・不適切な条項が入る恐れがあります。カスタマイズして実情に合わせることが重要です。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。