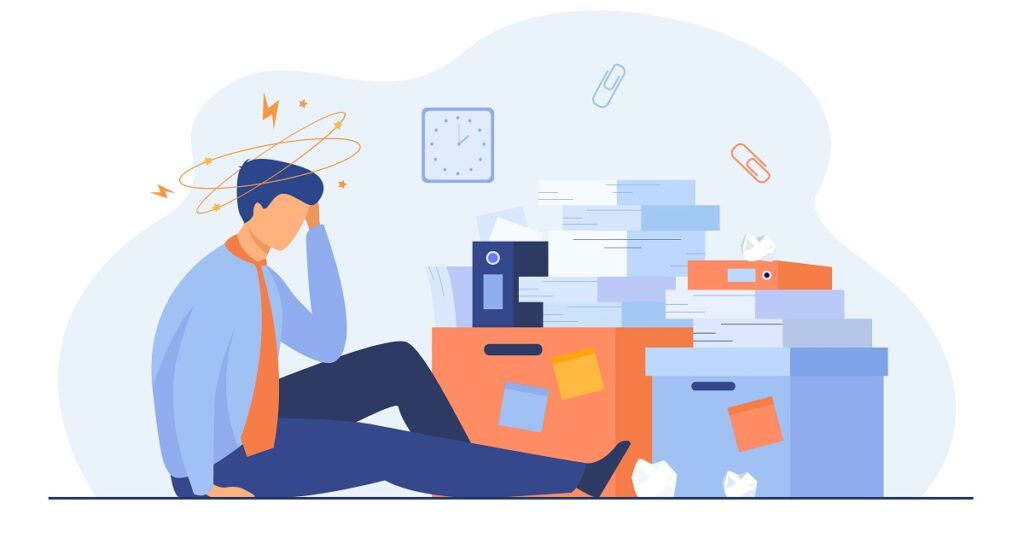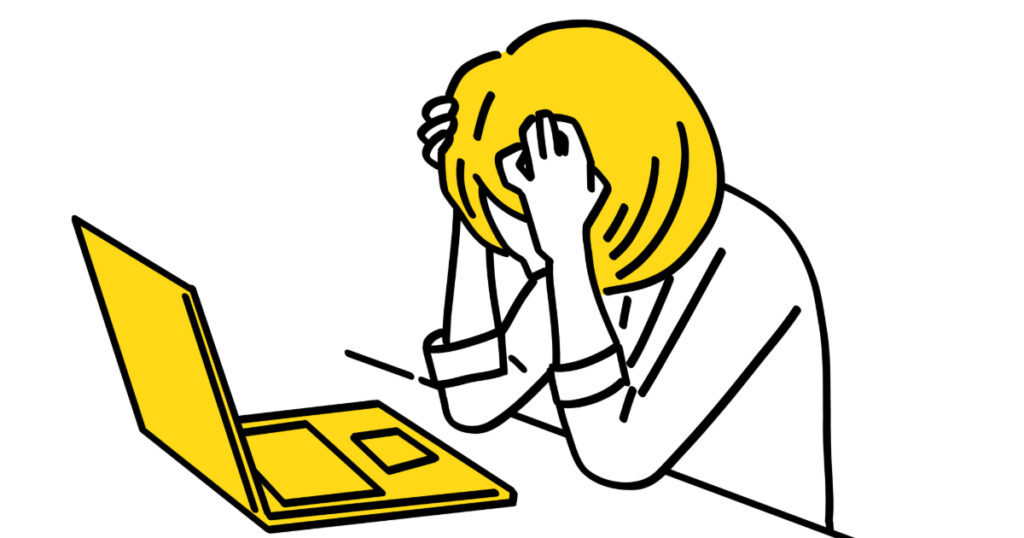お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
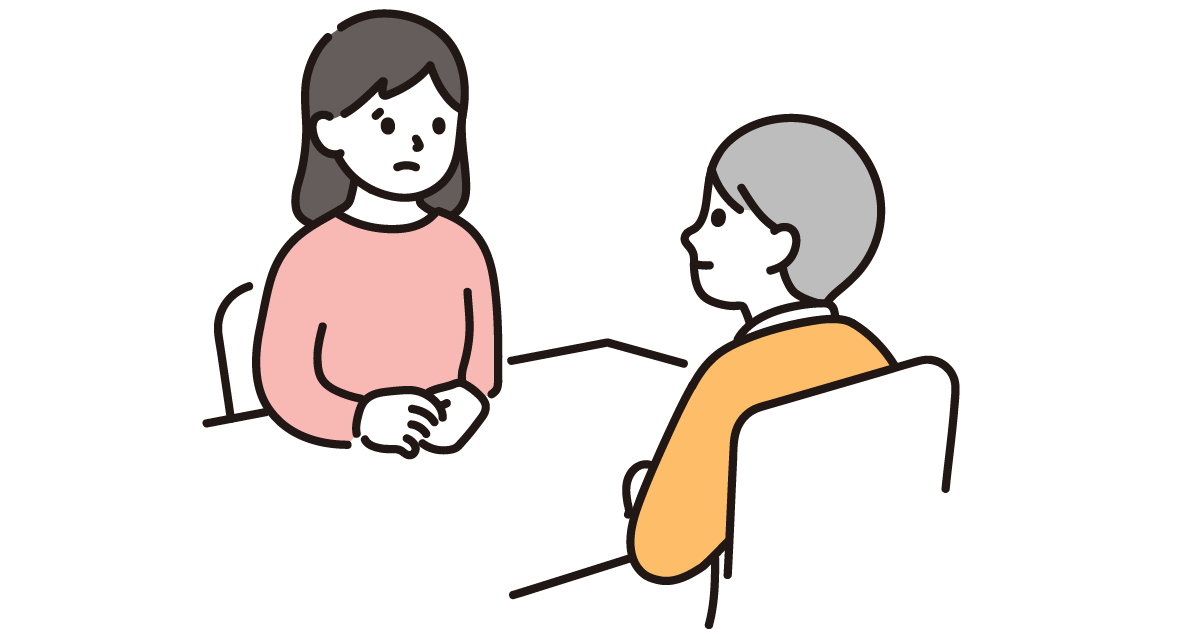
うつ病で休職中の従業員に復職を申し入れられてお困りではないですか?
十分に回復していない状態で復職させると、再発や周囲への悪影響が懸念されます。
申し出があった際には、診断書を提出させて医師の意見を確認するなど慎重に検討しなければなりません。
今回は、うつ病の従業員を復職させる流れや判断基準、注意点を解説しています。
うつ病をはじめとする精神疾患で休職中の従業員を抱える会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
メンタルヘルス不調を抱えた従業員への対応全般については、以下の記事で解説しています。
参考記事:メンタルヘルス不調の従業員への対処法・防止策を会社側弁護士が解説
うつ病から復職させる流れ

弁護士
岡本 裕明
休職中から状態を把握する
前提として、休職中から従業員の状態を把握しておくようにしましょう。
復職時にはじめて可否を検討するよりも、経過を知っておいた方が適切な判断を下しやすいです。
休職時に相談して連絡の頻度や方法を決めたうえで、症状に応じて柔軟に対応するのが望ましいといえます。
連絡する際には業務の話は極力避け、プレッシャーを与えないようにしてください。
休職までの流れについて詳しくは、以下の記事で解説しています。
診断書を提出させる
復職の申し出がなされた際には、主治医が作成した診断書を提出させるようにしてください。
とりわけ精神疾患は外見からは回復度合いが判断しづらいため、診断書が最低限必要となります。
確実に提出させるには、就業規則に復職時の診断書提出を明記しておくのがよいでしょう。
医師の意見を確認する
正確に復職の可否を判断するためには、診断書を提出させるだけでなく、主治医へのヒアリングや産業医との面談が効果的です。
診断書に「復職可能」との記載があっても、主治医が詳細な業務内容を考慮しているとは限りません。
会社が求めるレベルとギャップがあり、復職後に問題が生じるおそれがあります。
場合によっては、復職を希望する従業員が、主治医に依頼して実態にそぐわない診断書を書いてもらっているケースも存在します。
そこで、本人の同意を得たうえで、主治医との面談や書面での質問を通じて、本当に自社で業務ができる状態か確認するのが有効です。
主治医の判断に疑問がある場合など、必要に応じて従業員に産業医との面談を受けさせる方法もあります。
本人と面談する
本人との面談も不可欠です。
通院状況や体調を確認して復職の可否の判断材料にするだけでなく、復職した際に配慮すべき事項も確認できます。
より万全を期するには、本人の了承を得たうえで家族にも状況や意見を聴くとよいでしょう。
うつ病からの復職における判断基準

弁護士
岡本 裕明
参考記事:うつ病の従業員を解雇できる?パターン別に流れを解説
判断時期
業務が行える状態かを判断する時期は、原則としては復職時です。
もっとも、多くの裁判例では、当初は負荷の軽い業務に従事させればほどなく元の業務に復帰させることができるような場合には、復職を認めるべきとされています(エール・フランス事件判決・東京地裁昭和59年1月27日など)。
したがって、休職期間の満了時に完全に従前の業務ができる状態にまで回復していなくとも、多少軽い業務で仕事に慣れる時間を与えることで元の業務に復帰可能であるかを、会社として検討する必要があります。
対象業務
復職できるかを判断する際には、休職前の業務を遂行できるかを基準にするのが基本です。
ただし、元の業務が困難であっても、別の業務ができないかを検討すべきケースもあります。
具体的には、職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合には、労働者が配置される現実的可能性がある他の業務が存在し、従業員も他の業務での復帰を申し出ている場合には、復職を認めなければなりません(JR東海事件判決・大阪地裁平成11年10月4日など)。
検討する際には、従業員の能力・経験・地位、企業の規模・業種、会社における配置・異動の実績や難易などを考慮するものとされています。
たとえば、休職した正社員が従来通り多くの人との接触・交渉が必要な部署での復帰は難しくても、自分のペースで進めやすい事務作業であれば復帰でき、会社としても配置する余裕があるようなケースでは復職を認める必要があります。
反対に、会社の規模が小さく他に任せられる業務がない場合には、無理に復職させる義務は生じません。
いずれにせよ、職種や業務内容が特定されていない従業員については、従前の業務が難しくとも他の業務では復職できないかを検討してください。
うつ病から復職させる際の注意点

弁護士
岡本 裕明
試し出勤を活用する
復職できる状態かを判断する際には、医師の意見を聴くだけでなく、試し出勤(リハビリ出勤)させるのも効果的です。
たとえば、勤務時間に合わせて会社まで来て業務以外の読書等をして一定時間過ごし、帰宅してもらうといった方法が考えられます。
正式な復職ではないため無給で構いませんが、その旨を事前に説明し、納得してもらうようにしてください。
出勤すらままならない状態であれば、復職は困難です。
試し出勤を活用すれば、復職の可否を判断しやすくなるでしょう。
復職後も配慮する
復職後も配慮は欠かせません。
うつ病をはじめとする精神疾患は再発リスクが高く、とりわけ気を配る必要があるためです。
たとえば、最初は時短勤務とする、残業させない、出社頻度を少なめにする、精神的負荷の小さい業務を行わせるといった配慮が考えられます。
再発防止のため、通院への配慮や症状の確認も怠らないようにしましょう。
うつ病の従業員の復職は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、うつ病からの復職について、流れや判断基準、注意点を会社の立場から解説してきました。
うつ病は他人からは症状がわかりづらく、医師であっても復職の可否をめぐって判断がわかれるケースがあります。
診断書、面談、試し出勤等を通じて状態を確認し、慎重に検討するようにしてください。
当初は時短勤務で軽い業務を任せるなど、復職後の配慮も不可欠です。
精神疾患から復職しようとする従業員への対応にお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
復職の可否や適切な対処法についてアドバイスいたします。
既にトラブルになっている場合も迅速に対応いたします。
「うつ病で休職中の従業員からの復職申し出を認めるべきかわからない」とお悩みの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください
よくある質問
- Q.うつ病で休職中の従業員から復職を申し出られた場合、会社はどのように判断すべきですか?
- A.診断書を提出させ、主治医・産業医と面談し、従前の業務が可能かを判断します。
- Q.復職時に診断書の「復職可能」と記載があっても、会社はどんな確認を行うべきですか?
- A.主治医への詳細ヒアリングや業務内容の適合性確認を行い、必要なら産業医面談も実施します。
- Q.うつ病従業員の試し出勤はどんな目的で行い、注意点は何ですか?
- A.試し出勤で会社への適応を確認し、無給である旨を事前に説明して同意を得ることが重要です。
- Q.復職後に配慮すべきポイントは何がありますか?
- A.時短勤務・残業制限・出社頻度調整・精神的負荷の低い業務を設定し、通院への配慮も忘れずに行います。
- Q.会社側がうつ病従業員の復職に不安を感じた場合、どこへ相談すべきですか?
- A.弁護士法人ダーウィン法律事務所など、専門の弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることが推奨されます。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。