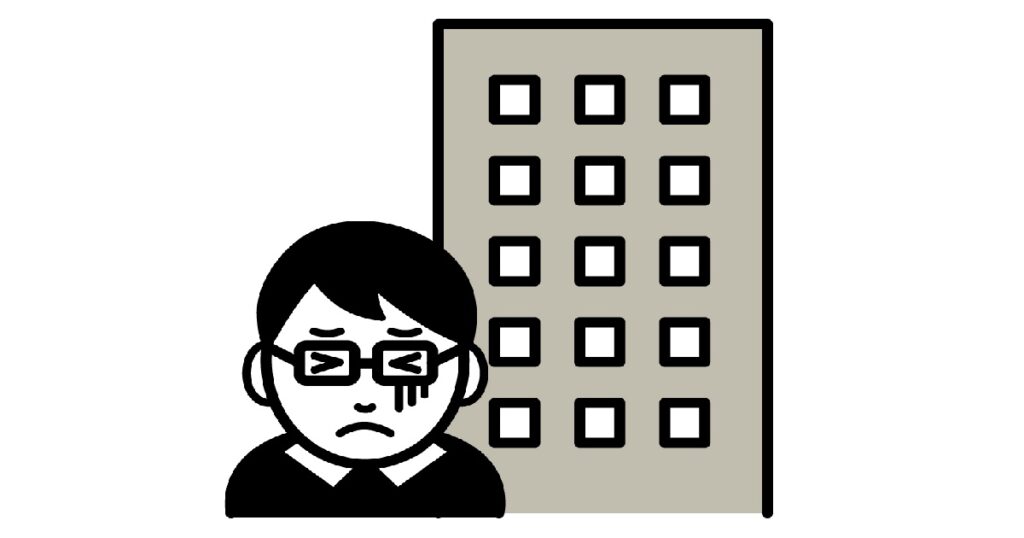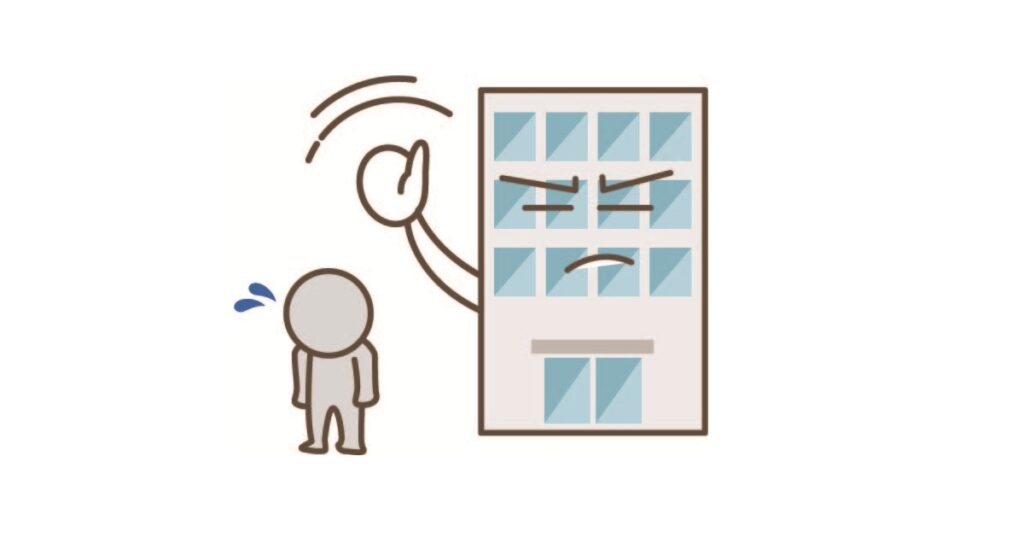お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
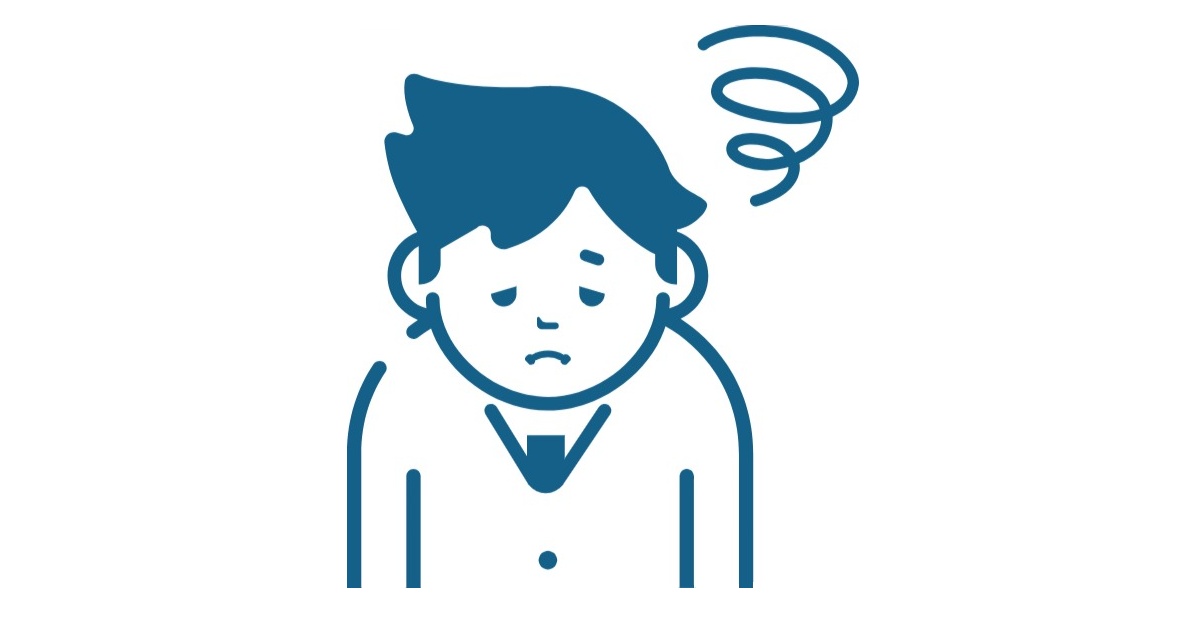
人件費削減の手段として、企業が希望退職者を募集する場合があります。
リストラ(一般的に整理解雇を意味する)の前段階として行われる場合が多く、より法的リスクが低い方法です。
ただし、本当は会社にとって必要な人材が流出してしまうなど、希望退職者の募集にはデメリットも存在します。
また、あくまで従業員が応じることが前提となっており、退職を強要してはなりません。
今回は、希望退職について、リストラとの違いやメリット・デメリットなどを解説しています。
人員削減を検討している会社経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
リストラ・人件費削減全般に関する基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:リストラによる人件費削減の方法やリスクを会社側弁護士が解説
希望退職とは?

弁護士
岡本 裕明
人件費削減のための退職者募集
希望退職とは、会社が退職者を募集し、従業員が応じる形でなされる退職です。
社内全体を対象とする場合もあれば、特定の部門や年齢の従業員を対象とする場合もあります。
希望退職は、主に人件費削減のために行われます。
リストラ(整理解雇)は法的なハードルが高いため、前段階として希望退職者の募集が行われるケースが多いです。
応じるインセンティブを与える
希望退職者を募集する際には、通常は従業員に応じるインセンティブを与えます。
代表的なのは退職金の割り増しです。
他にも、再就職支援、有給の買い取り、退職日までの出勤免除などが挙げられます。
従業員にこれらのメリットを示すことで、応募が集まりやすくなると期待できます。
参考記事:リストラする際の退職金|上乗せの相場や注意点を解説
希望退職とリストラの違い

弁護士
岡本 裕明
希望退職には従業員の意思が必要
希望退職に応じた従業員は、自らの意思により定年前に退職します。
従業員が同意している点が、希望退職の特徴です。
希望退職者の募集は、リストラ(整理解雇)の前段階で実施されるケースが多いです。退職に応じるかはあくまで任意であるため、法的なリスクは低いといえます。もっとも、実質的には退職を迫っている場合もあり、退職強要とならないように注意しなければなりません。
リストラ(整理解雇)は会社が一方的に行う
リストラには様々な意味がありますが、わが国では一般的に「整理解雇」の意味で用いられるケースが多いです。
整理解雇とは、会社が経営上の理由で行う解雇です。
解雇である以上、従業員の意思は関係なく、会社が一方的に行います。
整理解雇をするには、一般的に以下の4要件を満たさなければなりません。
・人員削減の必要性
・解雇回避努力
・人選の合理性
・手続きの相当性
4要件のうち、「解雇回避努力」の部分で、希望退職者の募集をしたかが考慮されます。
希望退職者の募集とリストラとは、人件費削減を目的とする点で共通しますが、従業員の同意の有無が大きな違いです。
なお、リストラとは、本来「事業の再構築」を意味し、人件費削減はリストラの手段のひとつです。
そのため、人件費削減を目的とする希望退職者の募集は、リストラの一種ともいえます。
もっとも、繰り返している通り、わが国ではリストラは整理解雇の意味で用いられる場合が多く、一方的に行われる点で希望退職者の募集とは異なります。
整理解雇について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考記事:整理解雇とは?4要件や実施の流れを会社側弁護士が解説
早期退職制度との違い
希望退職と似たものとして、早期退職制度があります。
早期退職制度においても、定年前に従業員の意思により退職が選ばれます。
退職金の上乗せなどの優遇措置がある点も、希望退職と同様です。
もっとも、早期退職制度は、人員の入れ替えだけでなく、従業員のセカンドキャリア支援という目的もあります。
ポジティブな意味を持つ点で、人件費削減を主目的とする希望退職者募集とは異なります。
また、期間を区切って行われる希望退職者募集とは異なり、一般に早期退職制度は恒常的な制度です。
退職勧奨との違い
希望退職者の募集は、退職勧奨とも若干異なります。
退職勧奨とは、会社が従業員に退職するよう勧める行為です。
会社からの働きかけにより従業員が退職を決める点で、希望退職と似ています。
両者の違いは、希望退職ではオープンに退職者を募るのに対して、退職勧奨は特定の個人を対象にしている点です。
もっとも、希望退職者の募集に際して個別に退職を求めるケースもあり、その場合にはあまり差がありません。
退職勧奨について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:解雇とは?退職勧奨とは?両者の違いや注意すべき点を会社側弁護士が解説
希望退職のメリット

弁護士
岡本 裕明
人件費を削減できる
希望退職に応じてもらえれば、人件費を削減できます。
特に給与が高くなりがちな中高年層が退職すれば効果的です。
効果を最大限に発揮するには、対象者、募集人数、優遇措置などを綿密に検討しなければなりません。
法的リスクが低い
同じ人員削減を目的とする行為でも、リストラでは厳しい要件が課されています。
希望退職は従業員が自らの意思で応じることが前提となっているため、法的なハードルが低いです。
自ら応募することを決めている以上、退職する従業員とのトラブルは生じづらいといえます。
希望退職のデメリット

弁護士
岡本 裕明
一時的にコストがかかる
希望退職に際して、通常は退職金の割り増しが条件となります。
割り増された退職金を一気に支払えば、会社にとっては大きな負担です。
長期的に見れば人件費が削減されますが、短期的には金銭的にデメリットが生じます。
倒産寸前のケースでは利用が困難です。
必要な人材が流出するおそれ
希望退職者を募集した結果、会社から見て辞めて欲しくない従業員が応募してしまう可能性があります。
能力のある従業員ほど再就職が容易であるため、「会社が危ない」と判断されると、人材流出のリスクは高いです。
残って欲しい従業員に対しては、個別にその旨を伝えるのがよいでしょう。
また、広く希望退職の募集をせずに、辞めて欲しい従業員に絞って退職勧奨をするのもひとつの方法です。
参考記事:退職勧奨の理由になること|能力不足・病気の従業員に退職勧奨できる?
希望退職を実施する際の注意点

弁護士
岡本 裕明
制度設計をよく考える
希望退職の募集に際しては、制度設計が非常に重要です。
人件費削減の効果を最大限に発揮するために、事前の十分な検討が不可欠となります。
会社の業務や財務状況を考慮して、対象者、募集人数、期間、優遇措置などを定めなければなりません。
目標人数に達しなかった場合にどうするかも考えておく必要があります。
従業員との面談の準備も必要です。
入念な準備をしていないと、効果が不十分になる、有能な人材だけが応募するといった事態が生じかねません。
事業の継続に関わる重要事項ですので、専門家への依頼もご検討ください。
強要しない
希望退職に応じるかは従業員の自由です。
辞めてもらいたい従業員がいても、強要してはなりません。
退職強要だとして違法と判断されると、退職後に復職され、バックペイや慰謝料の支払いが必要になってしまいます。
トラブルを防ぐため、慎重に進めるようにしてください。
参考記事:退職勧奨が違法になるケース|仕事を与えないなど強引な方法はNG!
希望退職を検討している会社は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、希望退職について、リストラとの違いやメリット・デメリットなどを解説してきました。
リストラとは異なり、希望退職では従業員が任意に応じるのが前提となります。
法的リスクは比較的低いものの、よく考えて制度設計をしたうえで、退職の強要とならないようにしましょう。
希望退職者の募集を検討している方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
ご相談いただければ、状況に応じて、法的リスクを考慮した制度設計、具体的な進め方などにつきアドバイスいたします。
「希望退職者を募集したい」とお考えの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.希望退職とは何ですか?
- A.会社が従業員に対して退職を募る制度で、従業員の同意が前提となり、人件費削減を目的に行われます。
- Q.リストラとの主な違いは何ですか?
- A.リストラ(整理解雇)は会社側が一方的に行う解雇で法的要件が厳しいのに対し、希望退職は従業員の自由意思で応じるため法的リスクが低い点です。
- Q.希望退職を実施する際に提供される主なインセンティブは?
- A.代表的には退職金の割増、再就職支援、有給買い取りや出勤免除などがあり、従業員の応募を促します。
- Q.希望退職のメリットとデメリットは何ですか?
- A.メリットは人件費削減と法的リスクの低さ、デメリットは一時的な退職金負担と必要人材の流出リスクです。
- Q.会社が希望退職を募集する際に注意すべき点は?
- A.制度設計を十分に行い、従業員への強要を避けることが重要で、退職後のトラブル防止に専門家への相談も推奨されます。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。