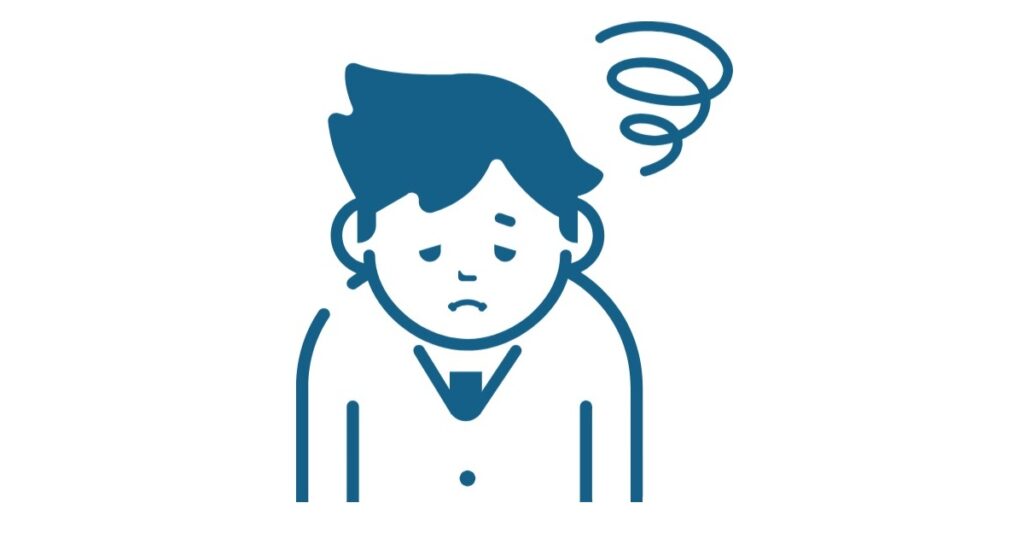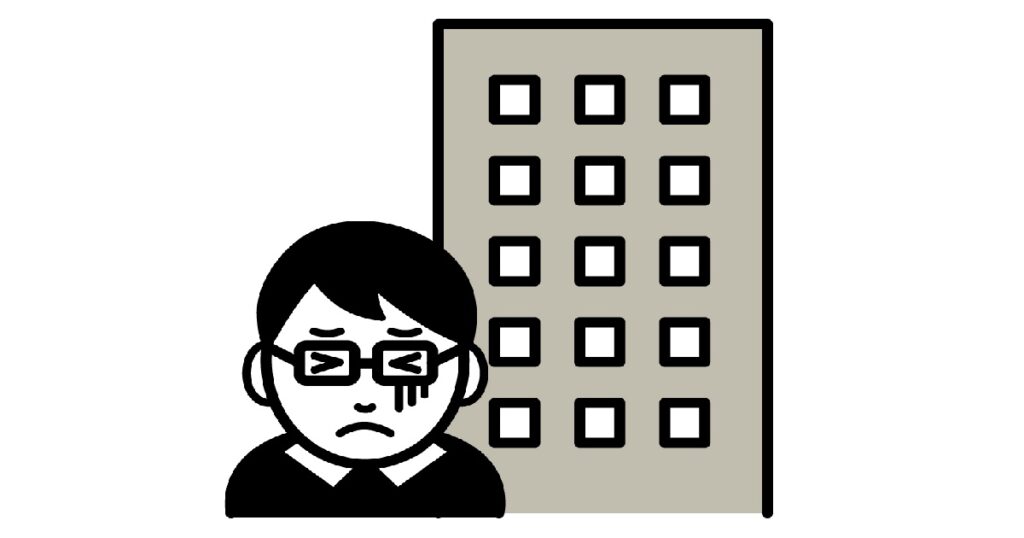お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください
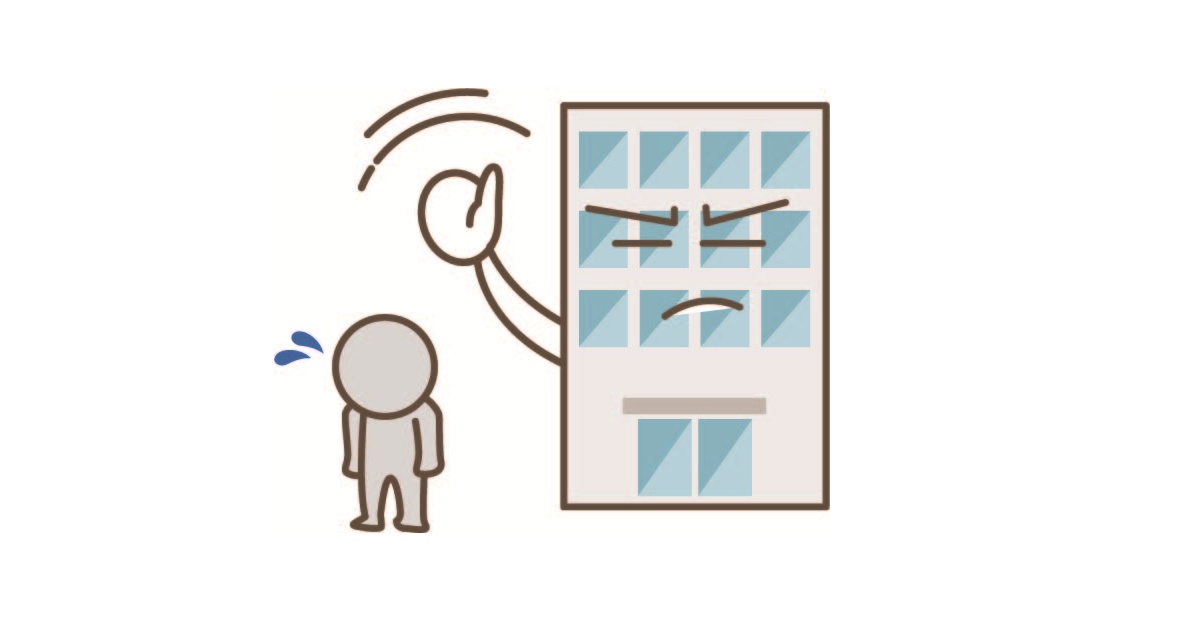
諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、従業員に退職を勧告する懲戒処分です。
「諭旨退職」と呼ぶ場合もありますが、意味はほとんど変わりません。
諭旨解雇・諭旨退職では退職金は支払われるケースが多く、懲戒解雇よりはワンランク軽い処分にあたります。
とはいえ、退職に応じないときは懲戒解雇する扱いになり、事実上懲戒解雇に近いです。
そのため法律上のハードルは高く、無効と判断されて復職やバックペイの支払いを強いられるケースも少なくありません。
会社としては、法律上の要件を満たしているか確認し、慎重に進めなければなりません。
今回は、諭旨解雇の意味や懲戒解雇との違い、実施する際の注意点などを解説しています。
従業員への諭旨解雇を検討している会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
解雇の一般的な知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:解雇とは?種類やできるケースを会社側弁護士が解説
諭旨解雇とは?

弁護士
岡本 裕明
まずは、諭旨解雇の意味について、似た処分との違いに触れつつ解説します。
退職届の提出を求める懲戒処分
諭旨解雇とは、問題行為をした従業員に対して、退職届を提出するよう求める懲戒処分です。
「諭旨」とは、趣旨や理由をさとし言い聞かせることを意味します。
従業員に理由を説明し、納得のうえ退職してもらうよう仕向ける処分といえます。
会社がする懲戒処分には、主に以下の種類があります。
- 戒告
- けん責
- 減給
- 出勤停止
- 降格
- 諭旨解雇
- 懲戒解雇
諭旨解雇は、懲戒解雇に次いで重い処分です。
懲戒解雇が相当であっても、情状酌量の余地があり、ワンランク軽い処分をしたいときに選択される傾向にあります。
退職届の提出を拒否すれば懲戒解雇するとされている場合が多く、重い処分であることは間違いありません。
懲戒解雇との違い
懲戒解雇は、懲戒処分として行われる解雇です。
諭旨解雇は従業員から退職届を提出させて辞めさせるのに対して、懲戒解雇は会社から一方的に辞めさせる処分である点が大きな違いです。
他の違いとしては、退職金の扱いが挙げられます。
懲戒解雇では不支給あるいは減額となる場合が多いですが、諭旨解雇では満額支給されるケースもあります。
諭旨解雇は懲戒解雇よりも軽い処分ですが、退職に応じないときは懲戒解雇する場合が多いです。
いずれにせよ従業員に辞めてもらう点で、両者は変わりません。
懲戒解雇について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考記事:懲戒解雇とは?普通解雇との違いや要件・注意点を解説
諭旨退職との違い
会社によっては「諭旨退職」と呼ばれている場合もあります。
諭旨解雇は解雇であるのに対して、諭旨退職は退職扱いになる点が異なるとされます。
とはいえ、いずれにせよ退職届の提出を求める処分であり、事実上ほとんど変わりません。
退職勧奨との違い
退職勧奨は、従業員に辞めてもらうよう会社が説得する行為です。
懲戒処分である諭旨解雇・諭旨退職とは異なり、退職勧奨がなされても、従業員が応じない限り退職の効果は発生しません。
退職勧奨は解雇でも懲戒処分でもなく、強制的な効力はない点が諭旨解雇と異なります。
退職勧奨に対する直接の法的規制はなく、法律上のハードルは諭旨解雇に比べると低いです。
退職勧奨については、以下の記事をお読みください。
参考記事:退職勧奨とは?解雇との違いやメリット・デメリットを解説
諭旨解雇の要件

弁護士
岡本 裕明
無効と判断されないために、諭旨解雇の要件を詳しく見ていきましょう。
就業規則に根拠規定が存在する
まずは前提として、就業規則に根拠となる規定が存在しなければなりません。
諭旨解雇が懲戒の種類として記載され、処分対象となる理由も定められている必要があります。
懲戒解雇とは異なり、諭旨解雇を就業規則に定めていない会社も存在します。
諭旨解雇を検討する際には、必ず就業規則を確認するようにしましょう。
懲戒事由に該当する
規定の存在を前提に、文言に該当する事実が認められなければなりません。
諭旨解雇ができる理由は、基本的に懲戒解雇に準じます。
代表的な理由としては以下が挙げられます。
- 社内での不正行為(横領・背任など)
- 業務命令違反
- 無断欠勤
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)
- 経歴詐称
- 私生活での犯罪行為
これらの理由が存在していなければ、諭旨解雇は無効です。
判例においては、諭旨解雇の理由とされた事実が発生してから長期間を経過していたために無効としたものがあります。
【事案の概要】
食品メーカーに勤務していた原告は、上司への暴行事件を理由に諭旨退職処分をくだされ、応じなかったため懲戒解雇となった。処分時点において、理由とされた暴行事件の発生から7年以上経過していた。
【結論】
長期間にわたって処分をしていなかった合理的な理由はなく、重い処分を必要とする事情も認められない。会社は権利を濫用しており、諭旨退職処分は無効。
相当である
懲戒処分をする理由があるとしても、相当な処分であるといえる必要があります。
したがって、従業員の行為に対して諭旨解雇が処分として重すぎる場合には無効です。
妥当かを判断する際の考慮要素としては、懲戒解雇の場合と同様に、行為の性質・態様、当該従業員の過去の処分歴、社内における先例との平等性などが挙げられます。
加えて、手続きも適正でなければなりません。
就業規則等で求められる手続きを踏んでいない、本人に弁明の機会を与えていないといった事情があれば、無効と判断されます。
諭旨解雇する際の注意点

弁護士
岡本 裕明
無効とされないよう慎重に進める
諭旨解雇が無効とされると、復職させたうえにバックペイの支払いを強いられます。
会社に与える影響が大きいため、無効にならないよう慎重に進めてください。
まずは、前提として事実の調査を十分に行い、理由が存在しているかを確認しなければなりません。
また、調査した後に、本人に弁明の機会を与えましょう。
そのうえで、様々な事情に鑑みて、諭旨解雇が妥当かを判断する必要があります。
安易に諭旨解雇とするのではなく、注意指導や軽い懲戒処分により改善を促せないかも検討しましょう。
退職金の扱い
諭旨解雇が妥当であるとしても、退職金の扱いには気をつけてください。
まずは退職金規程等を確認する必要があります。
一般的には、満額支給あるいは一部支給とされているケースが多いです。
満額支給とされている場合に、勝手に不支給としてはなりません。
減額が規定されている場合であっても、その通りにしてよいとは限りません。
裁判例によると、従業員の会社に対する功労を減殺するほど重大な行為があった場合に限り、減額が認められます。
規定があるからといって、安易に減額しないようにしましょう。
諭旨解雇する前に弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、諭旨解雇について、懲戒解雇との違いや要件、注意点などを解説してきました。
諭旨解雇は退職を求める懲戒処分であり、懲戒解雇と近い性質を有します。
法的なハードルは高いため、慎重に進めなければなりません。
諭旨解雇を検討している方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。
ご相談いただければ、法律上諭旨解雇の要件を満たすか、他の方法はないか、どう進めればいいかなどをアドバイスいたします。
もちろん、既にトラブルに発展している場合には迅速に対応します。
諭旨解雇に関してお悩みの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.諭旨解雇と懲戒解雇の主な違いは?
- A.諭旨解雇は退職届を提出させる点で従業員の意思を尊重しますが、懲戒解雇は会社側が一方的に解雇する点が異なります。
- Q.諭旨退職と諭旨解雇の違いはありますか?
- A.両者とも退職届を求める点ではほぼ同じですが、諭旨退職は退職扱い、諭旨解雇は解雇扱いとされる点が異なります。
- Q.諭旨解雇を行うために必要な要件は?
- A.就業規則に諭旨解雇の規定があり、懲戒事由が存在し、処分が相当であること、手続きが適正であることが必要です。
- Q.諭旨解雇とは何ですか?
- A.諭旨解雇は従業員に退職届を提出させる懲戒処分で、会社が退職を勧告する形で実施されます。
- Q.諭旨解雇と懲戒解雇の主な違いは?
- A.諭旨解雇は退職届を提出させる点で従業員の意思を尊重しますが、懲戒解雇は会社側が一方的に解雇する点が異なります。
- Q.諭旨退職と諭旨解雇の違いはありますか?
- A.両者とも退職届を求める点ではほぼ同じですが、諭旨退職は退職扱い、諭旨解雇は解雇扱いとされる点が異なります。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。