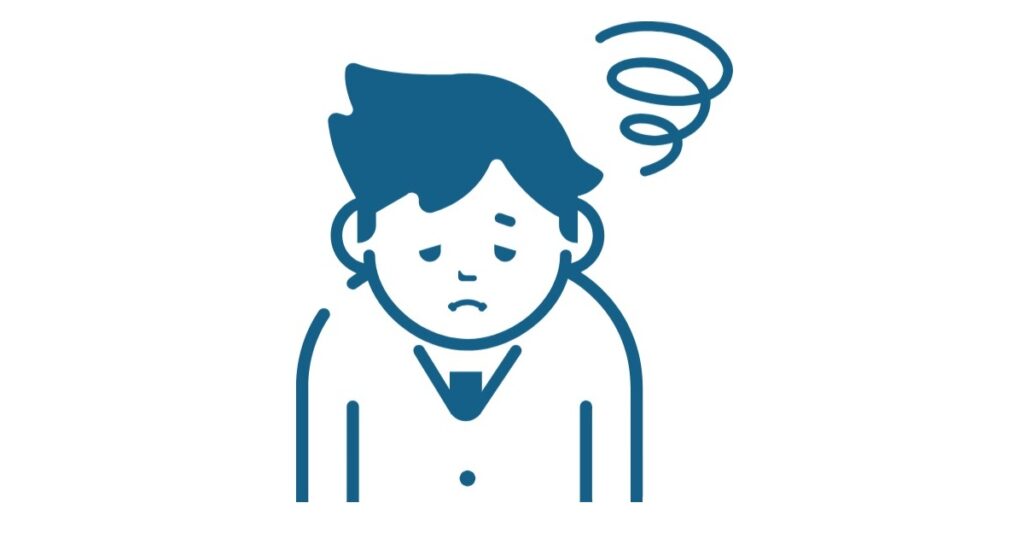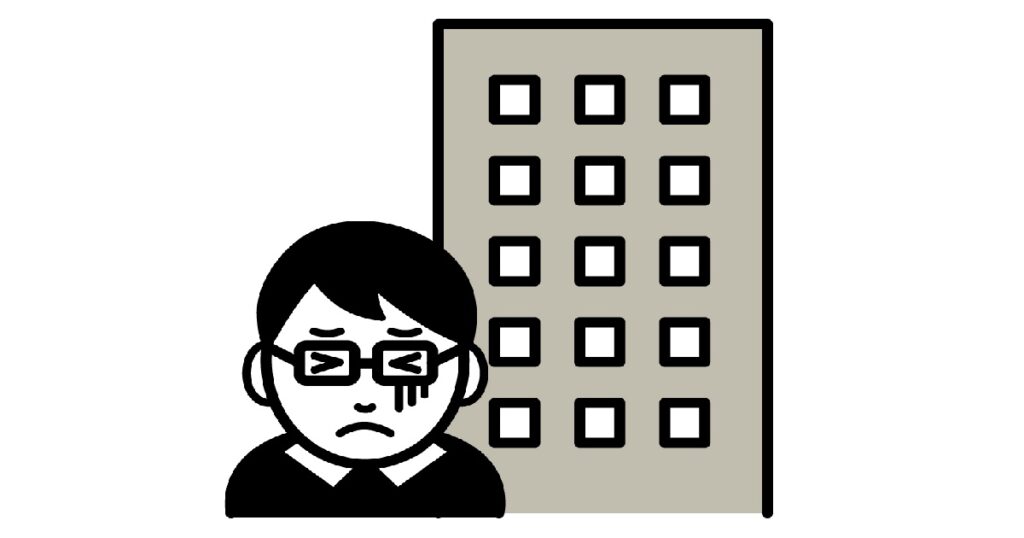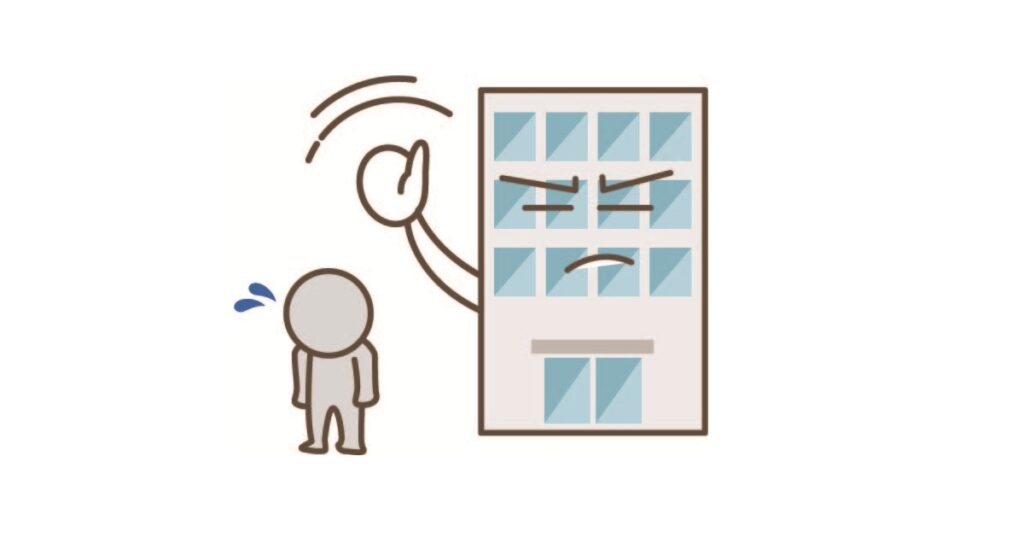お気軽にご相談ください
会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

退職勧奨をしても、金銭的な不安、感情的な対立などの要因で、従業員が応じてくれないケースは多いです。会社としては、原因に応じて解決金の提案、担当者の変更などで対処する必要があります。
解雇はあくまで最終手段です。拒否されたからといって、くれぐれも強引なやり方をとらないようにしてください。
今回は、従業員が退職勧奨に応じない場合の対処法や、してはいけないことを解説しています。辞めさせたい従業員が退職を断り続けていてお困りの会社の経営者や人事・労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
退職勧奨に応じない理由

弁護士
岡本 裕明
退職勧奨はあくまで説得です。従業員の側が応じるかは自由であり、拒否されるケースもしばしばあります。
応じない理由としては、以下が考えられます。
・決断できない
・自分が辞めることに納得がいかない
・環境を変えたくない
・再就職できる自信がない
・今後の生活に経済的不安がある
・会社や上司を感情的に許せない
理由は様々考えられ、ひとつには限られません。従業員の置かれた状況や面談時の様子から拒否する原因を見極めるのが、今後の指針を決めるためには重要です。相手の立場に立って考えるようにしましょう。
退職勧奨に応じない場合の対処法

弁護士
岡本 裕明
説得を続ける
はっきり拒否しているのではなく、単に決断できていないだけであれば、説得を続けても構いません。
従業員にとっては、仕事を辞めるかどうかは一大事です。簡単に決められるものではありません。特に家族を養う立場にあれば、ひとりでは決められず周囲との相談が必要でしょう。むしろ一度きりの面談で決めるのは困難です。
繰り返し説得する際には、後述する通り、従業員にとって有利な条件を提案するのもよいでしょう。ただし、明確に拒否の意思を示されたときは、強引に説得を続けないでください。
指導を重ねる
自分に問題があると考えておらず、なぜ辞める必要があるのか理解できていないケースもよくあります。自覚が薄い従業員には、問題点につき重ねて注意・指導するのが効果的です。繰り返し根気強く指導すれば、問題点を自覚してもらいやすくなります。
もし指導が成功して業務がスムーズにできるようになれば、辞めさせる必要もなくなり、会社・従業員の双方にとってプラスです。たとえ効果がなかったとしても、従業員の側に「自分はこの会社・仕事に向いていない」との意識を植えつけることができ、退職を受け入れてもらいやすくなるでしょう。
退職勧奨をする前に必要な指導ができればベストですが、事後的な指導で改善を促すのもよい方法です。
退職金上乗せや解決金支払いを提案する
今後の生活に経済的な不安を抱えている場合には、金銭面で退職に応じるメリットを与えるのが効果的です。退職金の上乗せ支給や、解決金の支払いを検討しましょう。
双方が合意さえできればよく、どの程度の金額で決まるかはケースバイケースです。再就職までの期間を考えると、月給の3〜6ヶ月分程度あれば当面の生活には困らないと考えられます。
問題ある従業員のために出費が発生するのには、抵抗感があるかもしれません。とはいえ、居続けるよりも今すぐに辞めてもらった方が、会社や他の従業員にとってはメリットが大きいです。トータルで見て得になると考えれば、前向きに検討できるはずです。
退職勧奨の際の退職金・解決金について詳しくは、以下の記事をご覧ください。参考記事:退職勧奨における退職金・解決金の相場|上乗せする?なしでいい?
転職をサポートする
再就職できる自信がない、環境を変えるのが不安といった思いを抱く人もいます。その場合、会社として転職をサポートするのも有効です。
具体的には、関連会社等に再就職できるようあっせんする、再就職支援を職業紹介事業者に委託する、転職活動のための休暇を認めるといった方法が考えられます。
とりわけ転職経験がない従業員は、転職はリスクが高いと考えやすいです。転職しやすい環境を整えれば、経済面の不安も解消され、退職に前向きになるでしょう。
担当者を変更する
単に感情的な問題で応じない場合もあります。「あの上司の言うことには絶対に従わない」などと考えているケースです。
説得を担当する上司との関係が悪いことが原因であれば、担当者を変更するのもひとつの方法です。会社全体への不信感が強いときには、第三者視点を持っている弁護士に依頼するのもよいでしょう。
感情のもつれが原因であれば、説得する人を変更しただけで、思いのほかあっさりと退職に応じてくれるケースもあります。
解雇する
他の手段をとってもうまくいかず、どうしても辞めさせたいときには、解雇するほかありません。
ただし、解雇はあくまで最終手段です。後述する通り無効とされるリスクが高いため、可能な限り別の方法を試みてください。
やむを得ず解雇する際には、解雇予告手当を支払うなど、必要な手続きを踏みましょう。解雇は特に慎重に進めるようにしてください。
解雇予告手当については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:解雇予告手当とは?支払い時の注意点や計算方法を解説
退職勧奨に応じない場合にしてはいけないこと

弁護士
岡本 裕明
断り続けているのに繰り返す
明確に拒否されているのに退職勧奨を繰り返すと、違法になるリスクがあります。
【事案の概要】
教員であった原告に対して、教育委員会が数ヶ月間で十数回の退職勧奨をした。1回あたりの時間は、長いときで2時間以上にも及んだ。原告は、精神的苦痛について損害賠償(慰謝料)を請求した。
【結論】
損害賠償の支払いが命じられた。
他に、暴言を吐いて従業員の自尊心を傷つけるのもいけません。また、「退職に応じないと解雇される」と誤解させると、退職の意思表示が無効とされるおそれがあります。
辞めさせたいからといって、度を過ぎた行為に及ばないようにしてください。なお、いったん拒否されたものの、時間が経って状況が変化したのであれば、再度退職勧奨をすることは可能です。
退職勧奨が違法になるケースや言ってはいけないことについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
・退職勧奨が違法になるケース|仕事を与えないなど強引な方法はNG!
・退職勧奨で言ってはいけないこと|言ったときのリスクも解説
拒否を理由に不利益な扱いをする
退職勧奨を拒否したことを理由に不利益な扱いをしてはなりません。
たとえば、退職に応じなかった従業員への配置転換・降格・減給などです。辞めるように仕向ける行為は違法と判断され、損害賠償が発生したり、退職が無効と判断されたりするおそれがあります。
退職の拒否とは別の業務上の理由であれば、配置転換は可能です。ただし、従業員から「退職に応じなかったのが理由に違いない」と主張されるリスクがあります。別の理由があったことを客観的に証明できるようにしておきましょう。
要件を満たしていないのに解雇をする
解雇の法律上の要件を満たしていないのに解雇しないようにしてください。
解雇への法的規制は厳しく、ハードルは思いのほか高いです。裁判所に解雇が無効だと判断されると、復職させたうえで、それまでの期間の賃金を支払わなければなりません。会社にとっては大きな負担になります。
最後の手段として解雇する際には、弁護士に相談するなど、法律上の要件を満たしているかを必ず確認してください。
退職勧奨に応じない場合は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
ここまで、従業員が退職勧奨に応じてくれない場合の対処法やしてはいけないことを解説してきました。
応じてもらうには、従業員の側にもメリットがあると思わせるのがポイントです。拒否する理由を探ったうえで、注意指導、金銭支給などの対策を検討しましょう。くれぐれも強引な手段はとらないでください。
退職勧奨に応じてもらえずお困りであれば、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。ご相談いただければ、拒否する理由を踏まえ、対処法をアドバイスいたします。
「従業員に辞めてもらえない」とお悩みの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
退職勧奨を弁護士に依頼するメリット・弁護士ができることについて詳しくはこちら
よくある質問
- Q.退職勧奨に応じない従業員への最初の対応は何ですか?
- A.まずは従業員の拒否理由を聞き、経済的・心理的不安を把握したうえで、解決金や転職支援など具体策を提示します。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。
企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。